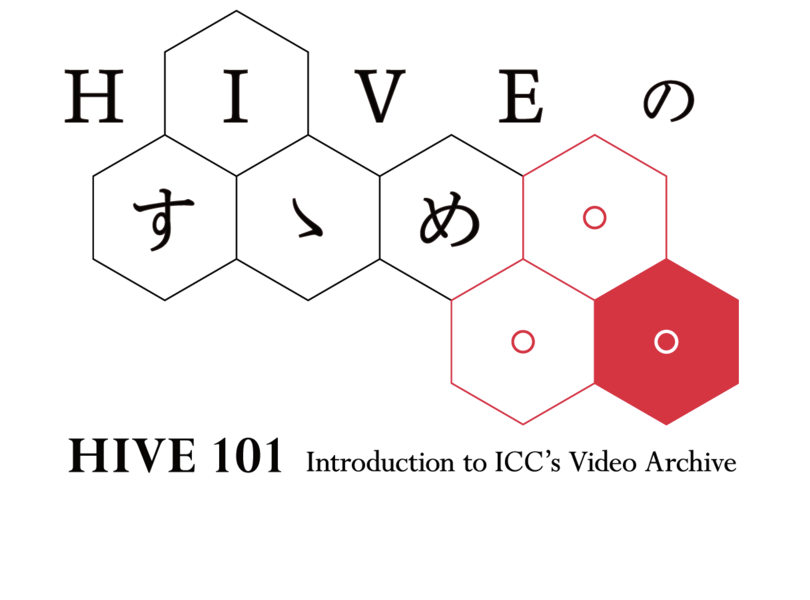横山由季子 YOKOYAMA Yukiko

1984年生まれ.金沢21世紀美術館学芸員.東京大学大学院博士課程(表象文化論)満期退学.世田谷美術館学芸員,パリ西大学ナンテール・ラ・デファンス校(美術史)留学,国立新美術館アソシエイトフェローを経て現職.主な担当展に「ルノワール展」(国立新美術館,2016),「ジャコメッティ展」(国立新美術館,2017),「ピエール・ボナール展」(国立新美術館,2018),「大岩オスカール 光をめざす旅」(金沢21世紀美術館,2019),「内藤礼 うつしあう創造」(金沢21世紀美術館,2020)など.
いまは現代美術館で学芸員をしている私ですが,もともと美術の道に入るきっかけになったのはフランス近代の画家,ピエール・ボナールです.2006年にパリ市立近代美術館で開催されていたこの画家の大回顧展「ピエール・ボナール:芸術作品,時間の静止」註1 を見て,画家の知覚や記憶が幾層にも織り込まれた絵画,しかもそれが実際に絵画の前に立つ私自身の身体にもつながっているような感覚に衝撃を受け,この画家の研究を決意しました.学生時代はボナールについて論文を書きながら現代美術にも関心を持ち,現代作家の作品を展示する美術館やギャラリーにも足繁く通っていました.2000年代の後半頃から,ICCにも足を運ぶようになっていたと記憶しています.
初めてICCを訪れる前は,自分の研究とは違うジャンルの作品を扱う場所だろうなと漠然と考えていましたが,実際に足を踏み入れると,人間の知覚や身体感覚の可能性を探求するような作品の数々に,徐々に夢中になっていきました.そして,こんなことすら考えました.ボナールの絵画の最大の特徴は,それを見ている人間の知覚のなかで生成するものであるという点です.たとえ小さな作品でも,一瞥で全体を把握することはほとんど不可能で,しばらく見つめたり,視点を変えたりすることで,先ほどまで見えなかったモチーフが浮かび上がってきます.その意味では,ボナールの絵画作品もインタラクティヴなメディア・アートなのではないかと.
思い起こせばボナールが画家として出発した19世紀末のパリは,メディア・アートの黎明期であったといえるかもしれません.コンパクト・カメラの普及,シネマトグラフの発明など,人間の視覚にまつわる革命が続いた時期です.今の私たちがタブレットやスマートフォンに没頭しているのと同様に,ボナールも当時の新しい視覚体験に夢中になりました.そのひとつが,モンパルナスのキャバレー「シャ・ノワール」で上映されていた
そんな影絵のパフォーマンスの記録を,HIVEのアーカイヴのなかに見つけました.西洋では18世紀半ばから19世紀半ばにかけて流行した影絵ですが,アジアの方が歴史は古く,中国では紀元前200年頃,インドネシアのジャワ島やバリ島では10世紀頃から存在したと伝えられています.2007年にICCキッズ・プログラムの一環として上映された影絵パフォーマンス「エレファント・アント・マン」は,インドネシアで結成されたガムランユニット,HANA☆JOSS*1 によるものです.インドネシアの影絵は「ワヤン・クリッ」(「ワヤン」は影,「クリッ」は皮の意)と呼ばれ,牛の皮でできた人形を用いました.本公演では,立派な舞台装置の中央にスクリーンが設置され,人やゾウの人形によるお芝居と,早川貴泰*2 によるアニメーションを組み合わせた,より複雑な映像表現が展開されました.とはいえ,人間の手が操作する人形の動きはどこか素朴で,ガムランの音楽やユーモアのある語りとも相まって,子どもたちを引きつけた様子が伝わってきました.
影絵を成立させている要素は,いうまでもなく「光」と「影」ですが,2008年にICCで開催された
ゲストとして招かれた,西洋美術史を専門とする岡田温司*7 は,光(透明性)と闇(不透明性)のあいだで,半透明性を帯びる領域としてプロジェクションを
プロジェクションに,空間的な広がりだけではなく,時間的な広がりをも取り入れたのが津田道子*9 の作品です.2016年の「オープン・スペース2016 メディア・コンシャス」に出品された新作《あなたは、翌日私に会いにそこに戻ってくるでしょう。》は,ICCの5階ロビーに,12個の黒いフレームを吊るしたインスタレーションでした.それぞれの枠には,鏡が入っていたり,プロジェクションが投影されていたり,何も入っていないものもあり,鑑賞者はその枠のあいだを自由に動き回ることで,実像と虚像が入り混じった時空間に迷い込みます.プロジェクションは,基本的にはリアルタイムの様子を映していますが,一つだけ前日(24時間前)の映像を投影しているものがあり,作品タイトルはこの仕掛けに由来しています.
アーティスト・トークのなかで津田は,現実のなかに入れ子状態に虚像が入った空間を前にしたときの心理状況を,「直接話法」と「間接話法」になぞらえています.ひとつの文章のなかで,話している主体が入れ替わるという構造は,作品を「見ている私」と「見られている私」がころころと入れ替わる本作品の鑑賞体験と,たしかに通じているようです.さらに津田は,直接は決して見ることのできない自分の姿を,映像を通して見ることで,「目だけ遠くに行って自分を見てしまった」という経験ができるのではないか,とも語っています.実像と虚像の森のなかで,他者としての「私(=あなた)」に出会うこと,それが《あなたは、翌日私に会いにそこに戻ってくるでしょう。》で私たちが体験したことの本質だといえるでしょう.
いかにして自分を客観的に見ることができるか——この問いを抱きながら制作しているアーティストはたくさんいます.持ち運び可能なサイト・スペシフィック作品「ファブリック・アーキテクチャー」シリーズで知られる韓国出身のソー・ドホ*10 もその一人です.金沢21世紀美術館でも,彼がニューヨークで暮らしていたスタジオの階段を,赤いナイロンの布を繋ぎ合わせて原寸大で再現した《階段》(2003)註4 と,幼少期を過ごした韓屋(ハノク)と呼ばれる韓国の伝統家屋をアメリカのタウンハウスと合体させ,1/11スケールで再現した樹脂による作品《家の中の家—1/11スケール—原型》(2009)註5 を所蔵しています.ソーの作品ではしばしば「家」が主要なモチーフとなりますが,それは彼の私的空間への関心からきています.
30代半ばのソーがICCのアーティスト・イン・レジデンスで東京に滞在した際に制作した作品《SIGHT-SEEING》(1999)は,より直接的にその関心を反映しています.それは2つのカメラを取り付けた帽子を装着して,東京や登京近郊の都市を歩き回って撮影した2面の映像作品で,一方にはソーが見ている光景が,もう一方には自身の顔が映っていました.鏡に写った自分は本当の自分ではなく,自分自身を客観的に見る方法はない,というジレンマから本作を構想したというソーは,ここで(のちに展開されるようになる)主観的な身体と客観的な身体の乖離をテーマにしています.このトークを聞いて,彼がその後取り組むことになる「ファブリック・アーキテクチャー」シリーズに思いを馳せると,世界中で私的空間を展開することを通じてアイデンティティを問い続けてきた作家の姿が浮かびあがってくるようです.
個人的な研究対象であるボナールから出発し,HIVEのアーカイヴのなかから,影絵,光と知覚(プロジェクション)を経て,津田道子,ソー・ドホと,関心の赴くままに紹介してきました.通常の美術史では繋がらないテーマや作家たちかもしれませんが,メディアの違いを超えて,人間が世界をどのように知覚してきたか,という問いへのアプローチには共通する部分があるように思います.
最後に紹介する,美術評論家の伊藤俊治
人間は自分自身を含む全ての自然を理解するために,サイエンスの旅に出た.
そして自然から得た感動を表現し,伝えるためにアートの旅に出た.
この映像は,一人の女性が奇妙に光る白い部屋のなかで日曜から土曜までの画集を次々と開き,案内人の言葉に耳を傾けながら,それぞれの時代のアートとサイエンスの旅に出るというストーリー.レオナルド・ダ・ヴィンチから未来派,キュビスム,ダダ,シュルレアリスム,ロシア構成主義,バウハウス,オプ・アート,キネティック・アート,ランド・アート,ポップ・アート,ライト・アート,そしてインタラクティヴ・アートまで,時代と地域を超えて,アートとサイエンスの接近を示す作品の数々が登場します.人間の飽くなき探究心が,新たな表現を生み出してきたという筋書きなのですが,興味深いのは,プロジェクション・マッピングやVR(仮想空間)といった,今日私たちが最先端と考えている視覚表現と同じアイデアを,何世紀も前の芸術家たちがすでに持っていたという事実です.宇宙や地球の長い歴史のなかでは,人間はずっと同じ問いの周りをめぐり続けているのかもしれません.
[註1]^ 「ピエール・ボナール:芸術作品,時間の静止」:パリ市立近代美術館で2006年2月2日から5月7日にかけて開催されたピエール・ボナール の大回顧展. パリ市立近代美術館ウェブサイト https://www.mam.paris.fr/
[註2]^ そのひとつが,モンパルナスのキャバレー「シャ・ノワール」で上映されていた影絵です:「シャ・ノワール(黒猫)」は,1881年にロドルフ・サリスがパリのモンマルトルに開いたキャバレー.文学,美術,音楽,演劇などジャンルを超えて作家や芸術家たちが集う場所となり,画家アンリ・リヴィエールを中心に上演された影絵芝居はとりわけ人気を博した.
[註3]^ 岡田温司は,光(透明性)と闇(不透明性)のあいだで,半透明性を帯びる領域としてプロジェクションを位置付けます:プロジェクションに限らず,ギリシャから脈々と受け継がれてきた半透明の美学については,岡田温司『半透明の美学』(岩波書店,2010)を参照.
[註4]^
《階段》(2003):http://jmapps.ne.jp/kanazawa21/det.html?data_id=232
現在,金沢21世紀美術館で開催中の「コレクション展 スケールス」(2020年10月17日—2021年5月9日)では,《階段》を展示中.
https://www.kanazawa21.jp/data_list.php?g=17&d=1784
[註5]^ 《家の中の家—1/11スケール—原型》(2009):http://jmapps.ne.jp/kanazawa21/det.html?data_id=835
プロフィール・ページへのリンク
*1 ^ HANA☆JOSS
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/hana-joss/
*2 ^ 早川貴泰
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/hayakawa-takahiro/
*3 ^ ヨッヘン・ヘンドリックス
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/jochem-hendricks/
*4 ^ インゴ・ギュンター
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/ingo-guenther/
*5 ^ ミシャ・クバル
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/mischa-kuball/
*6 ^ エイリアン・プロダクションズ
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/alien-productions/
*7 ^ 岡田温司
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/okada-atsushi/
*8 ^ 四方幸子
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/shikata-yukiko/
*9 ^ 津田道子
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/tsuda-michiko/
*10 ^ ソー・ドホ
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/suh-do-ho/
*11 ^ 伊藤俊治
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/ito-toshiharu/