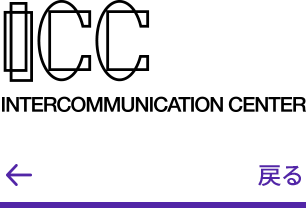|

|

|

|
|
|
|
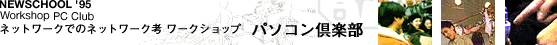
|
 1996年2月 [終了しました.]
NTT/ICC推進室
1996年2月 [終了しました.]
NTT/ICC推進室
|

|

|

|
| アニメ少年からコンピュータ少年へ |

|
森脇:岩井さんは,学校に入るまえから,基本的にはアニメーションをやるんだって思っていたんですか.
岩井:いや,最初僕は「生産デザイン」コースで入学したんです.「生産デザイン」というのはいわゆる工業デザイン,インダストリアルデザインですが,筑波ではそういう名前でした.2年まではずっとそこにいました.
ただ,僕はもともとアニメーションが好きで,高校の時かな,雑誌や本でいわゆるテレビアニメではない,個人作家がつくったアニメーションが世界にはいろいろあるっていうのを知って,すごく興味を持った.でも,僕は愛知県の田舎の出身なので,そのころは見ようと思っても見られない.で,大学に入ってから,東京に毎週のように通うようになって,いろいろな組織がやってる自主上映会でそういうインディペンデント作家のアニメーションフィルムを見るようになったんです.それにすごく刺激を受けて,専攻の「生産デザイン」とは関係なく,8ミリカメラを大学から借りたりとか映画研究会に入って自分でも作品をつくり始めたんですよ.
テレビだといわゆるセルアニメっていうのが主流だけれども,インディペンデント・アニメーションの世界に来ると「技法=作家の個性」みたいな感じなんです.ある作家は人形を使い,ある作家は粘土,またある作家は色鉛筆のすごく凝ったイラストを動かすとか,技法そのものが作家の個性になってるところがあるんですよ.僕の場合は始めたばかりで,そういう技法的なものはまだ模索してる段階だったので,なんでもやってみようという感じだった.
森脇:ああ,そのなかですんなりとコンピュータが入ってきた.
岩井:授業でつくった文字の重ね合わせによる絵がアニメーションになるんだろうかっていうような興味からやってみた.
森脇:それはすごく理解できます.授業でたまたま出会ったものを,違和感なくアニメーションの発想にすぐに結び付けたっていうところが,なんともおもしろい.
岩井:僕の場合,そういう入り方をしたので「こういうテーマがあって,これを表現したいからコンピュータとかのテクノロジーを使う」っていうよりは,「この機械,技術を使って一体どんな新しいものが見れるだろうか」っていうところに,基本的な興味がある.それは今でも大して変わっていないと思います.この素材が動くっていうことがどういうふうに見えて,どういうふうにゾクゾクするだろうか,そういう興味が先にあった.そのころ世の中はCGアニメーションが出始めたばかりで,ワイヤーフレームの紙飛行機がワイヤーフレームのシカゴの街のなかを飛ぶような,そういう作品しかなかったころです.CGといえばワイヤフレーム,っていう印象があったから,そうじゃなくて,紙の上に文字の重ね合わせで描いたCGがどういうふうに動いて見えるのかっていうことにすごく興味を持った.
|
|
| |
|