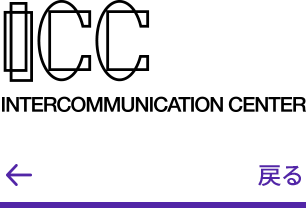|

|

|

|
|
|
|
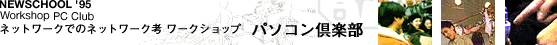
|
 1996年2月 [終了しました.]
NTT/ICC推進室
1996年2月 [終了しました.]
NTT/ICC推進室
|

|

|

|
| コンピュータとの出会い 1 |

|
森脇:岩井さんは,フジテレビの『アインシュタイン』や,『ウゴウゴルーガ』など,コンピュータを持ち込んで斬新な映像をつくられたことで広く知られているわけですが,昨年は,ICCのイヴェント「IC95'」でHotJavaを使った作品をつくられて,また話題を呼びましたね.きっとユニークなパソコン体験,コンピュータ体験がおありだろうと,インタヴューをお願いしました.やっぱりコンピュータとの付き合い方というか,どうとらえてどんな感じで付き合っているかというところが一番聞きたいですね.
岩井:森脇君は同じ筑波大学出身なので知ってる話も多いと思うんですが,知らない人向けにゼロからしゃべりましょうか.「そうだったよね」って相槌を求める話が多くなるかもしれないですが(笑).
森脇君も御存知のとおり,筑波大学というのは,大学1年生のときに情報処理の授業があるんですよ.普通,工学部とか理科系の学生はそういう授業を受けると思うんですが,筑波では芸術の学生も含めて,とにかく全学,1年生のときには必ず情報処理の授業を受けなきゃいけない.僕が入学したのは1981年ですが,そういう意味ではけっこう進んでいた学校だった.
そのときに教えていただいた先生が幸村真佐男さんっていう,日本のコンピュータ・アート界の草分けとして知られている方でした.筑波大の非常勤講師をいまもされてるかもしれないんですが,それ以外にも京都芸術短期大学でしばらく前まで教えられてて,いまは東北芸術工科大学で教授をなさっています.その先生の授業が非常にユニークだった.それが僕にとってはすごく幸せなコンピュータとの出会いだったなと思ってます.
僕が大学に入った81年ころっていうのは,ちょうど秋葉原の店にマイコンを触わりに来てる中学生,高校生が「マイコン少年」と呼ばれてテレビのニュースになってた.彼らは自分ではマイコンを持っていないのに,店先でプログラミングして帰っていくというのがすごく話題になってました.僕はそのころまだコンピュータをいじったことがなくて,そういうニュースを見て,ああ自分は取り残されてしまったなと思ってた.
筑波っていうのは,大学が3学期制になっていて,その3学期目に,情報処理概論と情報処理演習があった.概論のほうはコンピュータを使わずに,情報処理をするとはどういうことかというのをやるんですけど,そこで幸村先生がやってたことは,いまから考えてもすごくユニークなんですね.
たとえば,イスラム経典のコーランをテープで聞かせて,それをとにかく日本語で紙の上に書きとらせる.コーランって,文章が残っているわけではなくて,口から口に伝承されていくものなので,文字にはなり得ないものなんですよ.それをいかに記述するかというようなことを授業でやってみたりした.それとか,絵による伝言ゲームというやつで,教室の一番前に座ってる人にいろんな種類の写真を渡す.たしかアンディ・ウォーホルの版画のコピーかなんかだと思うんですけど,マリリン・モンローの顔写真とかアポロの月着陸船の一部の写真とか.で,前の人から順番に,絵を見ながら紙にその絵を真似して描いて,それを後ろの人に渡す.後ろの人は,その絵を真似して描いて3番目の人に渡す,ってやっていくと,どんどん絵が歪んでいく.最初の人がうまく写せないと2番目の人のはもうほとんどマリリン・モンローとは似ても似つかないような絵になっちゃってるわけです.それを順番にやっていって,あとで,ヴィデオカメラを使って順番に見る.ある列の人たちは目で見て真似をする.別な列の人たちは,写真の上に紙を乗せてトレースするというようなことをやって,どういうふうに変化が出るかを見たりした.
その授業がねらっていたことというのは,人間という情報処理機械を通してどのように情報が変わるかというようなことなんでしょうね.いまから考えてもすごくユニークでした.
森脇:ぼくのときは,星座っていうのがすごくおもしろかった.自分で勝手に星座をつくりなさいということで,天体図で星を好きに結んでいって,ある形を見出して何座ってつける.
岩井:それは僕はやらなかった.森脇君とは2学年ちがうんだよね.それでちがうのかもしれないね.
|
|
| |
|