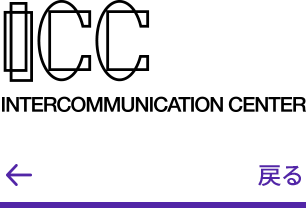|

|

|
| ダウンサイジングということ |

|
森脇:例えば西田さんは,これをどうお考えになるでしょうか.「マイクロソフト・オフィス」というソフトが書類の用意をしてくれる.じゃ,今度この先ね,例えば「ついでに中身まで考えてくれないかな」みたいな発展のしかたをするのか,そういう期待を寄せられるものなのか.どうなんでしょうね.この先があり得るとすれば.
西田:あり得るかもしれませんね.パソコン自身が仮想的な世界をつくってしまう.パソコンは無理かもしれませんが,大型コンピュータがつくってしまう世界というのが出てくるとは思いますけど.
森脇:パソコンと大型との区別が最近だんだん近づいてきたんで…….
西田:いや,それはウソです.それは全くのウソです.みなさんそうおっしゃってるんですが,それは,コンピュータの演算速度について言ってるわけです.486の33Hzぐらいで,かつて我々の夢であったDEC社のVAX780っていうマシンと同じなんだ,と言う.同じというのは,ただ中心部の1+1——というのは言い過ぎかもしれませんけど——をする能力は確かにそうかもしれませんが,システムで出来上がった場合はやっぱり断然速いわけですよ.だから処理の速さだけで言ってちゃいけない.
ただ,一般的に,コンピュータを一番多く使いたいのは事務ですよね.IBMのコンピュータって,事務処理だけの機械ですね.自動車の設計とかに使われることってほんの一部で,圧倒的に大型コンピュータは事務処理しかしてない.そういう事務処理の世界でパソコンがすごいというのは,パソコンが能力があるんじゃなくて,逆なんですね.
私が会社の社長で,会社のシステムを大型コンピュータで作ろうと思って,「こういうふうなものを作りたい」と言いますね.だいたい出来上がってくるのが5年後ぐらいなんですね.2年ぐらいは使って,リプレイスでまた金を払うということになるわけです.
いま,私らが酒呑んでパソコンの話をしてまして,昔そんなのあったよねっていうと,普通,3ヶ月ぐらい前が「昔」なんです(笑).
私なんか会社のシステムを作ったりしましたけど,そういうのでも,半年たつとだいぶ世界が違っている.1年たって納めたら,入れたときには相当時代遅れ.
6,7年前にシュッセルという男がアメリカでダウンサイジングって言い出した.日本では,コンピュータを小さくしてコストを安くするということをダウンサイジングと言うんですけれど,シュッセルは,問題は世のなかの進歩が速くなってライフサイクルが短くなったことだと言うんです.大きなシステムの上に載せようとすると,出来上がったころには古くなる.いかに速く仕事をするか,技術の進歩と一緒に動いていくかということだ,と.
リエンジニアリングという言葉がありますけど,企業のこれからの勝負というのは,いかに早く意志決定をするかということにかかっています.なんらかの意志を自分が決定するには情報が要りますよね.
大型コンピュータの世界では,みんなが寄ってたかって大型コンピュータにデータを差し上げて,時々まとめて情報を返してもらう.でも,意志決定を早くするにはリアルタイムで情報が返る必要がありますね.非常にプリミティヴに言えば,営業が,コストなんかがすぐわかる.どこか行くときには,その会社がこの前の契約時はどうであったかとかが全部すぐわかる.非常に速く結果が出るシステムを作るということがダウンサイジングであると,シュッセルは明解に言ってるわけです.
せわしい話ですけど,進歩が速いから,早い時間で作らなきゃならないわけです.いかに生産性があっても,馬鹿でかいシステムじゃ大変ですから,小さく作る.必ずしもコンピュータが大きくちゃけない,小さいほうがいいとかそういうんじゃない.結果的にはコストが安くなるけれども,いかに速くものを作って,いかに早く情報を受けて,いかにそれが分散化されているかということが問題だと言う.
大型コンピュータってのは,一人の偉いひとがいて,みんなが相談するようなものです.データ処理のエンジンは上にあるわけで,みんながそれを使う.みんなが使いますから,どうしてもこの機械はパワーの大きな強い機械になる.コンピュータの大きさとは,ひとつには記憶容量もあるんですけども,まぁ,速さですね.みんなが使いますから,相当速くないとならない.パソコンというのは能力があるんだから下でも仕事をさせよう,結果的にそういうふうになるんだと思うんです.文化的な形から社会の構造とか企業の経営とかがみんな似てきちゃうかもしれない.
森脇:社会がパソコンの影響をうけているのかな.
西田:それ,逆じゃないでしょうか.
森脇:どうなんでしょう,どっちが先なんでしょう.
西田:私はパソコンが社会の変化を追っかけているんじゃないかと思いますけどね.
|
|
| |
|