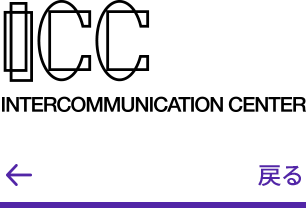|

|

|

|
|
|
|
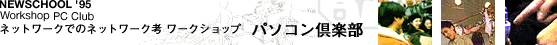
|
 1996年2月 [終了しました.]
NTT/ICC推進室
1996年2月 [終了しました.]
NTT/ICC推進室
|

|

|

|
| 光るパソコン |

|
森脇:いま,我々やもっと若い人たちとかいうのは,ピーピング・ジャップですか,ああいう体験はあまりない人が多いですね.
西田:ないです.かわいそうですよ.
森脇:どのパソコンを買うかとか,新製品が出たから買い換えるんだというパソコン体験しかしてないような感じなんですね.今回,ネットワークのなかで改めてパソコンを考えようと言ったときに,やっぱり,その中身はなんなんだろう,正体はなんなんだろうということにまずぶちあたる.くだらないことかもしれませんけど,意外とある世代にとっては……
西田:知りたいですよね.
森脇:というか,全く初体験のことでもあったりするわけなんですね.パーツを集めてきて組み立ててなんとか動くようにする.それを体験することでCPUってのがどんなもので,そこにどんな周辺機器がどんな形でくっついててとか,そういうことを体験するような企画を予定してるんです.パソコン少年が胸をときめかせたような,そういう雰囲気をいかにして伝えられるのかなと,悩んでるんです.
西田:なるほどね.
森脇:できるかどうかわからないんですけどね,BUSの信号のところにLEDを直接つけて,信号が通ると光る,などということを考えているんです.どういうふうな経路を辿ってメールを出してるのかということを目に見えてわかると面白いなと.でも速すぎて,目でみても全くわかんないかな.
西田:いまのマシンはものすごい進歩をしてしまいましたから,おっしゃる通り,目で見てわかんないですね.ぼくらは,CPUチップをTTLというICで作った.そうすると,いま,33MHzとかいってますけど,1Hzで動くコンピュータを作りますと……(笑).
森脇:ああ,なるほど.クロック1回やったらこんな動きをして,次1回やったら動くという(笑).それは理解しやすいですよね.
西田:初期のパソコンに「アルテア」という,ビル・ゲイツが使ってた有名なものがありますが,あれはデータを入れるときに,8ビットで8つ押しボタンがありまして,「10111001」と入れると,1のところにLEDがつくわけです.で,全部ついたところでもって,こっちに番地を入れまして,カチャッとやる.
森脇:すごくわかりやすいですよね.ビル・ゲイツは中学校のころそれを貸してもらって遊んでたんですよね.
西田:ええ,遊んでた.これはわりとみなさん御存知ないんですが,パソコンてのはカウンターカルチャーから出てきたものです.アメリカでは,「WHOLE
EARTH CATALOG」とかのヒッピー的な文化,フランスではヌーベルバーグ,イギリスではヤング・アングリー・メンっていう動きがあって,ベトナム戦争以降,反体制の動きがあった.そのなかで,IBMを倒せということで出てきた.でも,日本のパソコンは違う.大メーカーが作ってるんです.アメリカとは頭から違う.でも,メモリーやレジスタそういう世界のときめきというのは日本にも伝わったと思います.
いまおっしゃったことは,もしかしたらスタティックでCPUを組めば,作れることは作れる.ただ.これがわかったから何なんだと言われると,これがわかってもパソコンが動いてるのは全然わからないわけで…….
森脇:それこそ,さっきおっしゃられた「趣味の世界」で,なかなか…….
西田:コンピュータは,コンピュータに近いほど低レベルで,人間に近いほどハイレベル.「私は低級な言語をやってます」というのは,馬鹿だというのではなくて,一番コンピュータに近いことをやってる技術者を,そういうふうに言う.
で,ハイレベルに,コンピュータから離れて,ハイレベルなところにCPUという石があって,フロッピーディスクやハードディスクがあってCRTがある.これらがどうオペレーションしているかというのをお見せするのがまず,最初ではないでしょうか.昔はテレビが消えたらデータがなくなると思った方もいらっしゃったわけですよね.そういうことから入って,最後はパソコンを作ってみてもいいかもしれない.
森脇:でもね,「あ,動いてる」っていうリアリティっていうんですかね,それがなんかいまのウインドウズでもマッキントッシュでもない.なんかソフトが訳わからんように走ってて,すごくニコニコしたお面をかぶった機械に向き合ってるけど,その奥で何考えてるのかが全然わからない.
西田:たしかに視覚的に動くと面白いですよね.
|
|
| |
|