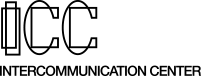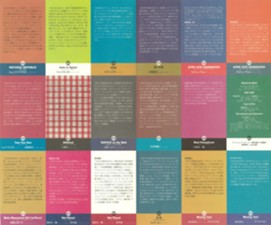1991年の「電話網の中の見えないミュージアム」は,電話網を使って多様な文化情報を交流させ,美術館の「情報場」としての機能を拡張するイヴェントであったが,「on the Web」では,急速に拡大する「インターネット」のなかに「見える美術館」を構築したほか,ISDN回線を使ったパフォーマンスやインスタレーション展示などを複合的に行なった.「ネット・ギャラリー」には,Netscape Navigatorのほか,Hot Java,VRML Viewerなどの最新のブラウザ・ソフトを使用して,観客が作品とのリアルタイムのインタラクションを楽しめる作品が公開された.
ネットワーク上で展覧会を開くということは,既存のメディアで展開されてきた作品やアーティストの行為をネット上に置き換えるということではない.また,それらが,これまでの「芸術」の枠のなかに収まるかどうかも定かではない.すべてはプロセスであり,まだ始まったばかりである.ユークリッド的時空間が適用できないネットワーク上でのアーティストの作品・行為を理解するには,まったく新しい「認識」が必要となる.「on the Web」では,観客自身の「ネットワークの読解力」も問われることになった.
『ICCコンセプト・ブック』(NTT出版,1997)より引用