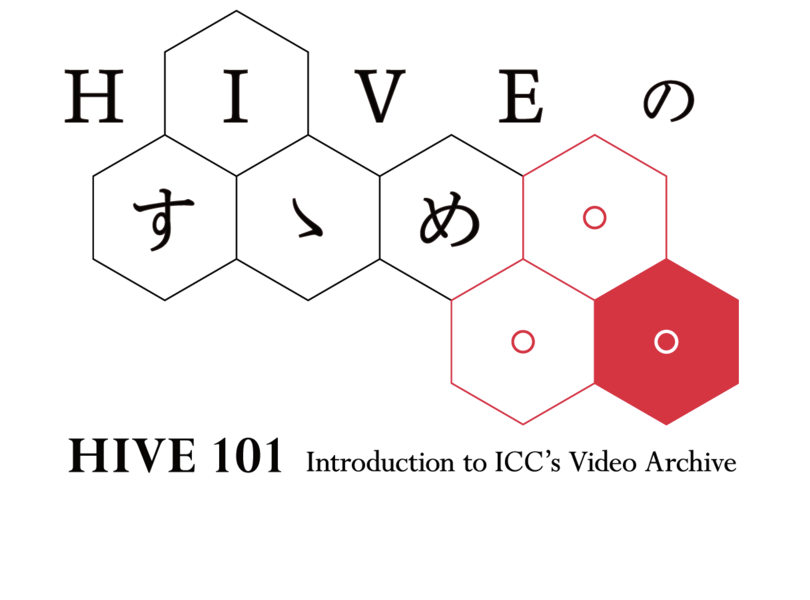飯田豊 IIDA Yutaka

1979年広島県生まれ.立命館大学産業社会学部准教授.東京大学大学院学際情報学府博士課程単位取得退学.専門はメディア論,メディア技術史,文化社会学.メディアの技術的な成り立ちを踏まえて,これからのあり方を構想することに関心があり,歴史的な分析と実践的な活動の両方に取り組んでいる.著書に『テレビが見世物だったころ』(青弓社,2016),『メディア論の地層』(勁草書房,2020),『メディア論』(共著,放送大学教育振興会,2018),『メディア技術史[改訂版]』(編著,北樹出版,2017),『現代メディア・イベント論』(共編著,勁草書房,2017),『現代文化への社会学』(共編著,北樹出版,2018),『趣味とジェンダー』(共編著,青弓社,2019)など.
HIVEで掘り下げる「メディア論の地層」
メディア考古学との出会い
私は2016年,初めての単著『テレビが見世物だったころ──初期テレビジョンの考古学』註1 を刊行しました.本書ではテレビの歴史を,博覧会や展覧会の中で成熟した見世物文化との相互作用を手掛かりに編み直しています.というのも,日本の場合,テレビに関する歴史記述は,1953年における本放送の開始――特に街頭テレビの登場――から始まるのが定番ですが,本書では,実用化を目指して研究が進められていたテレビジョン技術が,ラジオの全国放送網が成立する1928年ごろから,博覧会や展覧会における公開実験,あるいは戦時下における実験放送を通じて,繰り返し一般に公開されていたことに注目しています.
たとえば1930年代初頭,スクリーンに映像を投影する大型テレビジョンを開発した早稲田大学は,無線による大学野球の実況中継に成功し,博覧会場の群衆を大いに驚かせました.今でいう「パブリック・ビューイング」の可能性が提示されていたわけです.その一方,逓信省電気試験所が開発したテレビジョン電話は,北は樺太から南は台湾まで,博覧会場の呼び物として引っ張りだこの人気でした.われわれが慣れ親しんできた「テレビ」のあり方を前提として,その歴史を遡及的に捉えるのではなく,かつて「テレビジョン」という技術に開かれていた可能態の系譜を辿ることにしたわけです.
「テレビが見世物だったころ」という主題は,社会学者の加藤秀俊が1965年に発表した『見世物からテレビへ』註2 に対するオマージュで,「初期テレビジョンの考古学」という副題は,初期映画(early cinema)とメディア考古学(media archaeology)の研究潮流を踏まえたものです.
エルキ・フータモ*1 が長年にわたって先導してきたメディア考古学については,先だって遠藤みゆきさんが詳しく紹介されているので,解説はそちらに委ねたいと思います.ちなみに,私が初めてメディア考古学の視座に触れたのは,フータモが1995年,『InterCommunication』誌に寄稿した「テクノロジーの過去が復活する──メディア・アート考古学序説」という小論で,2000—01年頃に読んだ記憶があります.当時の私はまだ,工学部を卒業して大学院で“文転”したばかりで,これを日本のメディア史研究のパラダイムとうまく接ぎ木することができず註3 ,忸怩たる思いを抱いていました.日本では2010年代以降,とりわけフータモの単著『メディア考古学――過去・現在・未来の対話のために』 註4 が刊行される2015年頃から,メディア考古学の影響下にある研究成果が相次いで登場しています註5 .
フータモはとりわけ,1950—60年代におけるアートとテクノロジーの結びつきに強い関心を向けています. 日本では,1970年の日本万国博覧会(大阪万博)がその臨界点だったことは言うまでもありません.従来,博覧会や展覧会において新しい技術を展示するための手段は,開発者自身による公開実験(デモンストレーション)が中心で,私が『テレビが見世物だったころ』で焦点をあてたのもその一端だったわけですが,それが芸術家による「テクノロジー・アート」に大きく転回していくことになります.初期テレビジョン研究が一区切りしてからは,私自身の興味関心も60—70年代に移行していくことになりました.
マクルーハン,環境芸術,大阪万博
私自身が最初に興味を持ったのは,大阪万博の準備期間が,マーシャル・マクルーハンが最も精力的に言論活動を展開していた時期と合致していたことです.当時,大阪万博に関わっていた建築家や美術家のあいだでは,「インターメディア」や「環境芸術」といった新しい芸術潮流に対する関心と相まって,マクルーハンの思想がいち早く受容されていたようです.北米におけるマクルーハンと環境芸術の関係,日本における環境芸術と大阪万博の関係については,いずれも詳細な考察があるにもかかわらず,マクルーハン,環境芸術,大阪万博の相互連関については,ほとんど着目されていませんでした.1960年代,新聞やテレビ,週刊誌やビジネス誌などを席巻した「マクルーハン旋風」とは一線を画して展開された「環境芸術論」は,彼の死後――本格的には90年代以降――に精錬されていく「メディア論」の原像をなしているように思えたのです註6 .
その台風の目にいたのは,いうまでもなく,建築家の磯崎新*5です.一世を風靡したマクルーハンが忘却された1970年代以降も,磯崎の思索は都市とメディアのあいだを精力的に横断し続け(=建築外的思考),日本独自のメディア論の展開と伴走してきたようにみえます註7 .国内外の芸術家との幅広い交流,そしてICCとの深い関わりも,その一端を表しているといえるでしょう.2013—14年の「磯崎新 都市ソラリス」展では多数の関連イヴェントが開催されましたが,「お祭り広場」をめぐるトークセッションには,『戦争と万博』註8 で環境芸術と大阪万博の関わりを詳細に論じた椹木野衣が登壇しています.
そしてもうひとり.後にヴィデオ・アートやメディア・アートの先駆者と評される山口勝弘*6 もまた,「実験工房」,「エンバイラメントの会」などでの活動を経て,大阪万博に関わることになります.「お祭り広場」のための調査・研究を実施した「日本万国博イヴェント調査委員会」に参加するとともに,三井グループ館の総合プロデューサーを務めました.多岐にわたる山口の表現活動を端的に説明するのは容易ではないですが,HIVEに収録されているインタヴューでは,自身の活動の軌跡をとても平明な言葉で分かりやすく語っていて,その根底にあったメディア論的思考を感じ取ることができます(山口は1960—70年代に書いた文章のなかで,マクルーハンにも繰り返し言及しています).
ポスト大阪万博 ―ヴィデオ・アート,CATV(有線都市),市民表現……
大阪万博が終わると,山口は1972年,小林はくどう*7 ,中谷芙二子*8 ,松本俊夫*9 ,一柳慧,幸村真佐男*10 ,萩原朔美,東野芳明たちと「ビデオひろば」を結成しました.ビデオひろばは1970年代を通じて,欧米では反体制的なカウンター・カルチャーとしての色合いが強かったヴィデオ・アート註9を,もっとゆるやかで日常的なコミュニケーションの可能性を探る市民的プロジェクトとして,日本に定着させることを目指しました.
それに対して,磯崎は同年,『建築文化』誌に,「空間を情報の系で構成しようとする試み」のひとつとして,《POST UNIVERSITY PACK》――後に《COMPUTER AIDED CITY》と改題――という都市計画のプランを発表していて,その解説はマクルーハンの『メディアの理解』の引用から始まっています.千葉県の幕張を想定した《COMPUTER AIDED CITY》は,公共施設や各住戸にコンピュータ端末を行き渡らせ,有線のネットワークと無線の放送で覆い尽くすという壮大な都市計画で,半世紀前としては,あまりに現実離れしたものでした.
とはいえ,このプランは決して,日本社会の動向と乖離していたわけではありません.1972年といえば,日本では「有線テレビジョン放送法」が成立した年で,翌年から郵政大臣によるケーブルテレビ(CATV)施設の設置認可が始まることになります.CATVは1950年代なかば以降,全国各地に相次いで登場していましたが,当時はまだ山間部などでテレビの難視聴を解消するための共同視聴設備として運営されており,町や村で自主放送に取り組んでいた局は,数えるほどしかありませんでした(こうした取り組みは90年代以降,「パブリック・アクセス」や「市民メディア」の先駆として再評価されることになります).
ところが,1970年代に入ると,都市型のCATVが次世代のメディアとしてにわかに脚光を浴び,70年代なかばには放送業界や通信業界を中心に,いわゆる「有線都市論」が盛り上がることになります.CATVの普及が都市のあり方まで変えていくという議論自体は長続きしませんでしたが,現実には80年代以降,ニュータウン開発と結びつくかたちで,電鉄,建設,流通などの異業種企業が都市型CATVに参入していくことになりました.
1970年代のヴィデオ・アートとCATV,都市計画と市民表現…….一見した限りでは,互いに無関係な動きのように思えますが,私は現在,こうした動向の相互影響について調査を進めているところで
メディア・アートを社会に開くには――歴史資料としてのHIVE
近年においても,メディア・アートを社会に開いていくために市民表現との接点を探る動きが活発ですが,そのミッシングリンクを見出すことは容易ではありません.たとえば,2006年に行なわれたICCのリニューアル・オープニング・シンポジウムにおいても,ICCをいっそう社会に開いていくための試みとして,日本のメディア・アートと市民表現のあいだを,メディアに対する気づきやリテラシーなどの共通項を媒介にして接合しようという議論がなされています――パネリストの鳥海希世子*16は,民芸運動を補助線に持論を展開しています註11 ――が,その道筋が決して平坦でないことも明らかです.
世界的にみれば,1960—70年代のヴィデオ・コミュニケーション運動は後年,アメリカのハッカー文化に強い影響を与え,コンピュータやネットワークの革新を後押ししました.その思想や実践は少なからず,個人の参加を尊重する初期インターネットにまで継承されていきます註12 .最後に紹介したのは,マクルーハンのアシスタントだったコミュニケーション理論研究者のデリック・ド・ケルクホヴ*17,メディア・アクティヴィストとして国際的に活躍しているヘアート・ロフィンク*18のインタヴューで,どちらも1990年代後半に行なわれたものです.1990年代のインターネットについては現在,早期採用者だった人びとの懐古的な語りによって振り返られることが多い(=「インターネット老人会」)ですが,当時のネット・アートやメディア・アクティヴィズムを支えていたメディア論的思考を,その来歴も含めて検証するうえで,HIVEは今後ますます貴重な歴史資料になると思っています.
[註1]^ 飯田豊『テレビが見世物だったころ──初期テレビジョンの考古学』(青弓社,2016年).
[註2]^ 加藤秀俊は同書のなかで,見世物をはじめ,影絵や写し絵,パノラマや絵葉書,紙芝居や活弁といった視聴覚文化の伝統が,放送文化に継承されていることを多角的に論じている.「わたしは,日本の映像芸術を,映画にはじまりテレビに発展したという単純な文脈で考える通説に反対する.われわれの映像史は,もうちょっと長く,かつ複雑なのだ」(加藤秀俊『見世物からテレビへ』岩波新書,1965年,36頁).
[註3]^ 「最近のメディア史研究では「考古学」がブームのようだ.[…]それはマルクス主義的な発展段階論が決定的に信用を失った一九九〇年代以降,各ジャンルで模索された思考法である.ただし,私をふくめメディア史の第一世代は,まずメディアの俗説を改め,「正史」に近づく必要にせまられていた.メディア史というジャンルがまだ確定されていなかったためである.考古学であるより現代史の立ち位置を優先することになった」(佐藤卓己『メディア論の名著』ちくま新書,2021年,286-287頁).
[註4]^ エルキ・フータモ『メディア考古学――過去・現在・未来の対話のために』(太田純貴訳,NTT出版,2015年).
[註5]^ 赤上裕幸『ポスト活字の考古学――「活映」のメディア史1911-1958』(柏書房,2013年),大久保遼『映像のアルケオロジー――視覚理論・光学メディア・映像文化』(青弓社,2015年),早稲田大学坪内博士記念演劇博物館編,土屋紳一・大久保遼・遠藤みゆき編著『幻燈スライドの博物誌――プロジェクション・メディアの考古学』(青弓社,2015年)など.
[註6]^ 飯田豊「マクルーハン,環境芸術,大阪万博――60年代日本の美術評論におけるマクルーハン受容」『立命館産業社会論集』(第48号第4号,2013年)
[註7]^ 飯田豊「磯崎新のメディア論的思考――マクルーハン,環境芸術,大阪万博」『現代思想』(2020年3月臨時増刊号)を参照.
[註8]^ 椹木野衣『戦争と万博』(美術出版社,2005年).
[註9]^ 欧米では1970年前後,初期のヴィデオ・アーティストたちが,比較的安価になった機材によって映像作品を制作し,CATVを通じて従来のテレビとは異なるコミュニケーションの回路を模索していた.アメリカでは1969年,オルタナティヴ・メディアのシンクタンク「レインダンス・コーポレーション」が創設され,マクルーハンやバックミンスター・フラーの思想に強い影響を受け,雑誌『ラディカル・ソフトウェア』(1970—74年)や書籍『ゲリラ・テレビジョン』(1971年)の発行を通じて,独自のメディア生態学を展開した.『ゲリラ・テレビジョン』は1974年,中谷芙二子が日本語に翻訳している.マイケル・シャンバーグ+レインダンス・コーポレーション『ゲリラ・テレビジョン』(中谷芙二子訳,美術出版社,1974年).
[註10]^ 飯田豊『メディア論の地層――1970大阪万博から2020東京五輪まで』(勁草書房,2020年)を参照.
[註11]^ 鳥海希世子「コミュニティ・メディアをめぐる実践研究の地平――民衆芸術・デザイン・地域社会をキーワードに」『東京大学大学院情報学環紀要 情報学研究』(98巻,2020年)も参照.
[註12]^ たとえば,アレクサンダー・ギャロウェイたちが2000年に設立し,ソフトウェア・アートやインターネット・アートといった領域の開拓に貢献した「ラディカル・ソフトウェア・グループ」の名称は,70年代の『ラディカル・ソフトウェア』に由来している.
プロフィール・ページへのリンク
*1 ^ エルキ・フータモ
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/erkki-huhtamo/
*2 ^ 遠藤みゆき
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/endo-miyuki/
*3 ^ 南後由和
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/nango-yoshikazu/
*4 ^ 椹木野衣
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/sawaragi-noi/
*5 ^ 磯崎新
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/isozaki-arata/
*6 ^ 山口勝弘
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/yamaguchi-katsuhiro/
*7 ^ 小林はくどう
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/kobayashi-hakudo/
*8 ^ 中谷芙二子
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/nakaya-fujiko/
*9 ^ 松本俊夫
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/matsumoto-toshio/
*10 ^ 幸村真佐男
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/komura-masao/
*11 ^ 松田達
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/matsuda-tatsu/
*12 ^ 岡崎乾二郎
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/okazaki-kenjiro/
*13 ^ 鈴木健
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/suzuki-ken/
*14 ^ インゴ・ギュンター
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/ingo-guenther/
*15 ^ 水越伸
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/mizukoshi-shin/
*16 ^ 鳥海希世子
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/toriumi-kiyoko/
*17 ^ デリック・ド・ケルクホヴ
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/derrick-de-kerckhove/
*18 ^ ヘアート・ロフィンク
https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/participants/geert-lovink/