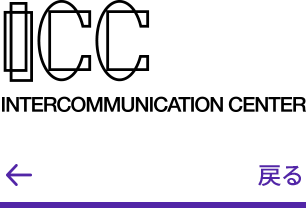|

|

|

|
|
|
|
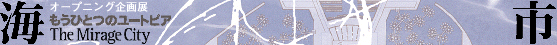
|
 1997年4月19日 〜 7月13日 [終了しました.] ギャラリーA
1997年4月19日 〜 7月13日 [終了しました.] ギャラリーA
|

|

|

|
| 2月18日 : 丸山洋志氏から古谷誠章氏へ |

|
古谷様へ
2月18日のファックスを今読んでいます.
時間をおくと「読みこなさなければならない」ので,直感的に読んでこれを書いています.古谷さんの「05」はなかなか良いアイデアだと思います.また,ワーク・ステーションへの過度の期待への警告も,賛成です.このへんにかんしては,鵜沢さんもいろいろな意見をもっていると思います(なにしろ経験者ですから).
デジタル・データと模型あるいは全体の計画の「概念」「理念的」「知覚的」的関係を,VISITORS全員がある程度共有しなければ今回の規格はお話にならないでしょう.データーもしくは「デジタル情報」そのものが「ブルー・プリント」だとしても,その「読みこなし」は千差万別でしょう.「データーのホモジェニティ」を限定(データを「概念的」「理念的」「知覚的」に限定)するという意味ではありませんあくまでも,古谷さんがおっしゃっているように「模型とデータ」の関係においてです.このへんに関しては,全員がいろいろなアイデアをだすべきでしょう.ある意味で,このへんを全員ばらばらにやったのでは恐らくvisitors 部門は意味がなくなるでしょう.
ということで,「越境」のところを興味深く読みました.これは古谷さんに聞くべきではなく,岡崎さんに聞くべきでしょうが「所与given」って,なんですか? マスター・プランは言わば「所与」ですよね.そこからわざわざ「脱出」や「越境」を企てるなら,最初ひゥら「所与」と思わなければいいのに・・・・共有したはずの「制度」から逸脱するなら,最初から共有しなければいいのに・・・・
すみません,小学生のような疑問を呈して.でも最近の私はデリダ流の「不可能性と不可避性」とか「外部」とか「余白」といった説明を身体的に受け付けなくなっています.
ある意味で,入江フレームはそのへんのところをうまくやり過ごしているから,「好き」なんです.
だから,私にとっては入江フレームの磯崎氏案=「プロトタイプ」キャビネットと岡崎氏の磯崎氏案=「所与」とは雲泥の差あるような気がします.(でも,そして,それにもかかわらず,入江さんも「動機」としての磯崎氏案というようなロマンティックな「始まり」を持ち出してきていますけれども).
磯崎氏の案はほんとうに「所与」なのでしょうか?
というわけで,愚痴はこのへんにして,私たちは川俣さんの意見「作業している姿はおもしろくもなんともないよ」をもっと考えるべきだと思います.実際,模型制作の場を「展示」するのでしょうか.それとも,ある一定の時間帯(「午前中」もしくは「夜」など)を作業時間として,後は展示(もちろん制作途中のもの)するようにするのでしょうか.
私は,はっきり言って川俣さんの主張に賛成です.そこで,吉松さんの「ワークショショップ」案との妥協ですが,作業を別室でしたらどうでしょうか・・・・このまえどなかたかが言ったと思いますけど.これも最初の週が問題ですが,会場には1stVISITORの案を展示する.どこかでその案を連歌的に変化させていく作業(2ndVISITOR)をすることにする.その光景を1stVISITORSの作品の横におかれたモニターで来場者が見れるようにする(だから,作業の光景を見たくないものは見なくとも良い).もちろん,別所での作業データは刻々会場のワーク・ステーションに送られるようにする.そして,来場者は,自分の構想を作業場に発信できるようにする.同じ階もしくは同じビルに作業上があれば実際に,制作に参加もできる.
これは場所とモニタリングの設定が可能かどうか(同じ建物内に作業場が設置できればわけないでしょうが)が問題になってくると思いますが,他の展示やコンピューターへの防塵配慮を考えるとこれしかないのではないでしょうか.
そして,2週間後にはその製作物が展覧会場に移され,3rd VISITORが作業場で次の連歌をスタートさせる.
少なくとも,来場者は各自の作品を鑑賞・批評できると同時にその作品の未来(2週間後の運命)を予感できると思いますが.また,作業効率もよいと思いますが.そして,各自の模型の寿命も実質3週間になるになる!
制作過程の公開(モニター上,作業場),製作物の展示(会場),それをもとにした他者の批評的介入(モニター上,作業場)・・・・・少なくともかくvisitorの模型の寿命が3週間で,これはもうそれだけで「歴史」だと思います.
急に,プラグマティックな話になってすみません.今,考えつくのはこんなところです.今度の会議でいろいろお聞きしたいことがあります.楽しみにしていますので.
FEB.18 19977 丸山洋志
|
|
| |
|
|