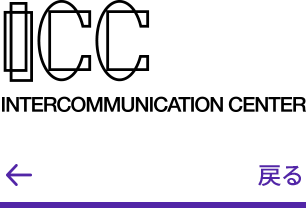「ネットワークは国境を越える」の1回目の研究会では,エンジニアリングの方々に集まっていただきましたが,そこで問題になったのは,結局,ネットワークにおける言語的な多様性ということでした.ネットワークができると,地域格差がなくなって誰でもが発信できると言われているわけですが,その一方,画一的な言語文化が流れていく.そうしたときに,どうしたら多様な文化が維持できるのか.今回は,人文系の研究をされている方々に集まっていただき,その問題をもう少し詰めていければと思います.
最初にお話しいただく桂英史さんは,「知の収蔵庫」といったものにずっと関心を持たれてきた方ですが,そうしたご興味から,新しいテクノロジーを使った「知の収蔵庫」でもあるネットワークについての発言も数多くしておられます.最近では,「知の収蔵庫」を構成する言葉の問題にご関心を持たれているとのことなので,前回の文字コードなどの問題とも関連したお話をしていただければと思います.
次にお話しいただく上野俊哉さんは,東欧とかオランダといった非英語圏に行かれ,そうした日本同様のマイナー言語圏でネットワークがいかに使われているかということを身近に体験されているので,そのあたりのことをお話しいただきました.
最後にお話しいただく水越伸さんは,アジアのネットワークやメディア状況に詳しく,中国や韓国などの漢字文化圏をふくめた近隣の国々の動きを語っていただきました.
【第四回研究会 目次】
●Talk 1——by 桂英史
<言語による連帯><語構成のアポリア><漢字のイデオロギー>
●Talk 2——by 上野俊哉
<グローバライゼーションの内実><ディアスポラの普遍化><メディア・アクティビズム>
<「Next Five Minutes」><ネット・クリティシズム>
●Talk 3——by 水越伸
<アジア文化のモード><ユニコード問題の位相>
<東アジアにおける「漢字」の勢力圏><「外国人」のメディア表現>
●Discussion
<日本人の言語感覚><エフェクトとしての「文化」>
<文化多元主義の陥穽><漢字の「不気味さ」><ハイブリッド言語>

|
|