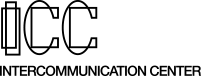科学と芸術の最先端で活躍する各国の論客によるシンポジウム.会議は冒頭モデレイターの浅田彰氏による趣旨説明に引き続き, まず, マーヴィン・ミンスキー氏(アメリカ,マサチューセッツ工科大学〈MIT〉メディア・ラボ教授,人工知能)は,脳の思考のメカニズムの解明とそれがもたらす文化的な影響について,ロイ・アスコット氏(イギリス,グウェント大学インタラクティヴ・アート高等研究センター所長,メディア理論)は,ネットワーク・テクノロジーの発達がもたらす芸術と意識の変容について,磯崎新氏(建築家)は,情報化の進展による都市・建築のメルトダウンについて,蓮實重彦氏(東京大学副学長,フランス文学,映画史)は,電子メディアの 「二度目の誕生」について,ジェフリー・ショー氏(ドイツ,カールスルーエ・アート・アンド・メディア・テクノロジー・センター〈ZKM〉映像メディア研究所所長,メディア・アーティスト)は,メディア・テクノロジーによりもたらされる鑑賞者と芸術作品をつなぐ新たな関係性について,それぞれショート・レクチャーを行なった.この後,パネル・ディスカッションが行なわれ,議論の内容は新しいかたちのミュージアム論からインタラクティヴィティの重要性に至るまで多岐にわたり,アートとサイエンス双方から多面的な展開がみられた.
マルチメディアを可能にした新しい電子情報技術は,経済社会を急速に変容させつつあると同時に,芸術文化の世界にも大きな影響を与えつつある.もともと技術と芸術は同じ一つの術だったが,近代社会にあって,それが非常にハードな技術の体系と主観的な芸術の表現とに分かれていたところを,新しいメディアのテクノロジーがそれをもう一度違うかたちで結びつけようとしている.シンポジウムはそのような情況を契機とし,ジャンルを超えたディスカッションを通して,マルチメディアを21世紀の「文化の問題」と捉え,情報社会をめぐる議論に新たな視点を提供することになった.なお,シンポジウムの模様は,インターネットを通じて同時中継された.
パネリスト:ロイ・アスコット,マーヴィン・ミンスキー,ジェフリー・ショー,磯崎新,蓮實重彦,浅田彰
『ICCコンセプト・ブック』(NTT出版,1997)より引用