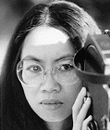
その眼が赤を射止めるとき
When the Eye Frames Red
アキラ・ミズタ・リピット──今回こうしてインタヴューに応じていただけることになりましたことを,まずはお礼申し上げます.近年,日本ではあなたの映画や著作に対する関心が高まっており,しばらく滞日されたことでもありますので,日本での体験や反応につきましても,あとで少しばかり触れることにいたします.
ところで,あなたに対してインタヴューを試みるということは,ある意味できわめて難題なんですね.インタヴューを通じてものを伝えようとすると,習慣的に何かはっきりとわかるような不変のアイデンティティという考え方を前提とし,インタヴューを受ける側の本質的なところは,既知の事実か理解可能なものであると見なしてしまうものなんです.
ところが,トリン・T・ミンハという名前を聞くと,人は映画作家や学者の姿を思い浮かべるだけでなく,微妙な味わいに長けたアーティストや永遠の旅人という姿,今世紀という時代とその思想を特徴づけた変動そのものを,一人の歴史のなかで体現している個人の姿すら思い浮かべることになる.『Framer Framed』に収められたさまざまなインタヴューを思い起こしてみると,あなたの語っている内容がじつに幅広いことに圧倒されるのですが,それと同時に,聞き手側がときにおぼつかないやり口であなたのことを,実験映画の制作,人類学や従来のドキュメンタリーに対する批評,民族誌,詩学,ポストコロニアリズムの思想,フェミニズムの思想や実践といった,あらかじめ用意された場所に何とか収めようとしていることに唖然としてしまいます.ですからここでは,いわゆる相手の居場所を確認したいという誘惑に逆らいながら,あなたの幅広い仕事から窺えるノマド的な特徴に,せいぜい準じていきたいと思います.
ところで,これまでのインタヴューは他者性というテーマとの関連で,あなた自身の文化に対する信条や立場を取り上げたものが多いので,今日は映画という地点からお話ができないかと考えているのですが,映画はあなたの仕事のなかでもほかとは違う,際立ったものでありながら,きわめて特殊な想いや欲望とつながっているように思えるのです.そこでまず,プロジェクトというものについてお尋ねしたいのですが――プロジェクトという考え方を受け入れるとすれば――映画のプロジェクトとはどのようなものであるとお考えですか.また,芸術家として知識人としてあなたが行なっている広範なプロジェクトと,映画の仕事をどのようにかみ合わせていらっしゃるのでしょうか.
トリン・T・ミンハ──映画のことを考えると,私は映像と音の世界にぐいっと引き寄せられてしまいます.つまり,ものを作ることもできるし,ものを積極的に受け入れることもできるような状態そのものが,まずは「プロジェクト」なのです.
しかし,映画を作るということは,ほかの手段を用いたもの作りに対しても扉を開くことになります.例えば,本を著わすことと映画のために書くことの違い――これは,言葉が映画という織物の一部を成しているかぎり,常に向きあうことになる違いなのですが――その両者の境目がはっきりとしてくる.言語の使い方が著しく異なるだけでなく,映画のなかで物語や詩,日常会話を扱っていると,以前には考えてもみなかったかたちで音楽というものを意識させられるんですね.中国の画家が喩えたように,詩が目に見えない絵だとしたら,映画は目に見える詩であるばかりか,音楽のような絵,絵のような音楽でもあるのです.
映像,音,テクストのあいだにある場とは,何かを生み出すことのできる多様性の場なのですが,そこではそれぞれの要素が互いに仕えたり従えたりするのではなく,緊密に連係しあうことで自らの限界を曝け出してしまうところがある.映画作りの要所要所においてどうしても避けられないのが,この三種の神器の利点と限界なんですね.
ですから,こうした限界や,限界をはっきりさせてくれる状況と格闘しながら,ただやみくもに突き進んでいるというのが本当のところなんですよ.言葉にすると,私のプロジェクトはどれも明快な思考に基づいているかのように聞こえますが,作る過程で形になってきたわけで,初めからそうだったわけではありません.たいていは自分からやみくもにプロジェクトに飛び込んでいくわけですが,そうすれば境目の位置そのものがズレてくるんです.
リピット──ものを書き,思考し,学ぶための場を開くものとして映画制作を考える.まさに作品を手がけている最中においても,そうだということですね.
トリン──それは強く感じますね.映像を作ることに直接関わることや,それを引金にして生まれてくることなど,活動全体は複雑に入り組んでいます.ただし,映画を通じて見せたいとか説明したいというものが,あらかじめ決まっているわけではないんです.そんなふうに始まるわけじゃない――むしろ人との出会い,人々との出会い,事件との出会い,あるいは特定の状況が引き起こすエネルギーのうねりと出会うことから生まれてくるんですね.

 次のページへ
次のページへ