
| InterCommunication No.13 1995 |
 |
InterCity TOKYO |
復活
ゴダール『勝手に逃げろ/人生』を見る
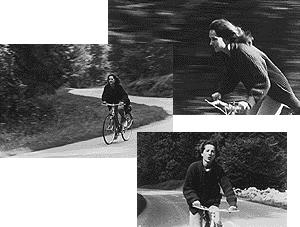
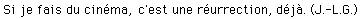
ジャン=リュック・ゴダールの1979年のフィルム『勝手に逃げろ/人生』が15年の空白を経てついに日本で公開された.70年代の孤独な戦いを辛うじて生き延びた映画作家が商業映画の世界に奇跡的な復活を遂げた記念すべき作品である.
そう,それはまさに復活なのだ.冒頭,あてどなくさまよう視線に開示される青空.時折り唐突に挿入されるコマ落としのスロー・モーション.いわば致命的なリリシズムをたたえたそれらの映像は,80年代以後のゴダールの映像世界をすでに予告している.音楽はまだガブリエル・ヤレドひとりに任せられているものの,それがところどころで中断され,さまざまなノイズとミックスされて,映像と微妙にずれた音のコラージュを織りなしてゆくプロセスは,やはり80年代以後のソニマージュ(音=映像)の実践にただちにつながってゆくものと言えるだろう.この映画は,15年経ったいま見ても,息を呑むほど新鮮だ.いや,映画が生誕百年を迎えるいまこの作品を見るとき,あたかも映画そのものがそこで新たに生まれ落ちたかにさえ見えるのだ.そして,この作品以後,ゴダールは,映画史の終焉において起源を反復しながら,一作ごとに新たな復活を遂げてゆくことになるだろう.
それに先立つ70年代がゴダールにとってもっとも危機的な時代だったことは疑いを容れない.67年の『中国女』などですでに5月革命を予告していたとも言えるゴダールは,68年以後,急速に過激化し,69年にはジガ・ヴェルトフ集団を結成して映画の集団制作を試みるが,72年には解散に至る.同時に,交通事故で負傷し,2年半にわたって病院通いを余儀なくされる.このとき彼を支えたのがアンヌ=マリー・ミエヴィルであり,彼女とともに設立したソニマージュ工房で,74年の『ヒア&ゼア』のような実験映画をはじめ,とくに76年の『6×2』をはじめとするTVプログラムが制作されることになった.コーリン・マッケイブのあからさまな記述を引けば,76年には「彼のミエヴィルとの性的関係は終わる」のだが,彼はミエヴィルを追って生まれ故郷のレマン湖畔に移り,ソニマージュの実験を続けるだろう.そして,70年代の最後になって,ゴダールは『勝手に逃げろ/人生』をもって商業映画に復帰するのである.
だが,ゴダールがそれによって長い不毛な沈黙から豊饒な映画の世界に帰ってきたと考えるのは誤っている.そもそも,波瀾に満ちた70年代を通じてゴダールはきわめて活動的だったのであり,この時期の実験がなければ80年代以後の作品もありえなかったのだ.とくに問題なのは,政治的に過激化しすぎて袋小路に入った前衛作家が故郷の自然に触れて映像の瑞々しさを取り戻した,というような単純きわまりないストーリーである.実際,ゴダールの60年代後半から70年代前半にかけての作品は,たんに政治的な内容を持っているだけではなく,映画という形式そのものを内側から批判的に問いなおす試みでもあったからこそ,深い意味で政治的だったのであって,そのような映画の内部における政治は以後もますますラディカルに展開されてゆくことになるのである.
そこで重要な役割を果たしたもののひとつが,映画について考える媒体としてのヴィデオである.実際,『勝手に逃げろ/人生』に先立って『「勝手に逃げろ/人生」のシナリオ』というヴィデオ作品が撮られており(助成金申請のためではあるが),次作に随伴する名高いヴィデオ作品『映画「パッション」のシナリオ』の先鞭をつける形になっているのだ.そもそも,ヴィデオを用いた70年代の映像の実験の成果は,『勝手に逃げろ/人生』のコマ落としのスロー・モーション――唐突でありながらさりげなく,冷徹でありながらはっとするほど瑞々しいあの映像を見るだけで明らかだろう.その名もポール・ゴダールという主人公がTV局で働いているという設定も意味深長だ.彼が学校でヴィデオの解説をするシーンでは,黒板に「カインとアベル,シネマとヴィデオ」と書かれており,両者が容易に協調し得ないことが示唆されているが,その間の関係は単純ではない.そもそもシネマとヴィデオのどちらがアベルでどちらがカインなのか.かりにシネマがアベルでヴィデオがカインだとしても,いわばシネマがヴィデオに殺されることで奇跡的な復活を遂げるさまをこのフイルムは体現してみせているのである.
形式的な水準でもうひとつ重視しておくべきは,音と映像の無媒介的な分離/接合の操作(son et imageならぬsonimage)である.それについてはマルグリット・デュラスとの同時性を指摘することもできるだろう.いまあげたシーンで,ポールはデュラスの77年の映画『トラック』のヴィデオを生徒たちに見せているらしいのだが,聞こえてくるのはデュラスの声だけである.「彼女は言った.ごらんなさい.世界の終わりよ.……」だが,この『トラック』という映画自体,トラックの運転手と彼の乗せたヒッチハイカーの女の会話らしきものをジェラール・ドパルデューと作者自身が朗読するシーンが,トラックの走る風景のシーンと交互に断続するばかりの特異な作品であり,普通の映画のように音と映像を統合しながら聴く=見ることはもともと不可能なのである.ゴダールはそのような音と映像の分離/接合の操作を徹底的に推し進める.登場人物は,いわば自分の映像を伴奏する音楽について「あの音楽は何?」と尋ねるのだが,だれもその音楽を聴いてはいない.かと思うと,ラスト・シーンでは,映画音楽を奏でるオーケストラそのものが映画のなかに登場する.もっとも奇怪なのは,売春婦を買った男が自分を含む4人の男女の絡みあう性戯を演出するシーンであり,他の3人の位置を決めた男は,「映像はこれでいい,あとは音だ」と言って,いかにもわざとらしい喘ぎ声を各々に割りつけてみせるのだが,その声と動きはどうしようもなくずれており,残酷にして滑稽な印象を与えるばかりなのである.先に触れたように,この映画では一応ガブリエル・ヤレドが音楽を担当しており,決してセンスは悪くはないものの,シンセサイザーの響きなどがいかにも70年代的だったりするのだが,その音楽はところどころで中断され,いま触れたような音と映像の分離/接合の操作にさらされるので,サウンドトラックは全体として少しも古い印象を与えない.むしろ,それは『パッション』以後のあの過激なソニマージュの実践へと直接つながってゆくように思われるのである.
この作品がタイトル・バックで「ジャン=リュック・ゴダールによって作曲(構成)されたフィルム」と記され,いわば音楽としてとらえられていることを,究極的にはそのような意味で理解することができるだろう.ただ,それはまずはセリエルな音楽として作曲(構成)されている.ジル・ドゥルーズはゴダールの作品に「一般化されたセリー主義」を見ているが,それは『勝手に逃げろ/人生』には文字通り当てはまるのだ.事実,そこには番号を付された4つのセリーがある.〈1.想像的なもの〉ドニーズ・ランボーは,都市を逃れ,田舎で静かな生活を送ることを夢見ている.〈2.恐怖〉ポール・ゴダールは,ドニーズを失うことを,しかしまた都市を離れることを恐れている.〈3.商売〉イザベル・リヴィエールは,田舎から都市に出てきて,売春に従事する.そして,これらのセリーが絡み合って作り出すのが他ならぬ〈4.音楽〉であり,その帰結は,ドニーズと別れたポールが,イザベルの仲間の売春婦の乗った車にはねられて(おそらくは)死に,彼の妻子がその場から平然と立ち去って行くというものなのだ.救いはない.しかし,この死をゴダールの「音楽」の必然的な終止点と見る必要もない.この映画のタイトルで,船が沈むときなどに「逃げられるものは勝手に逃げろ」という意味で発せられる言葉〈Sauve qui peut〉が「人生」〈la vie〉と無媒介的に併置されていることが示すように,だれもが勝手に逃げてゆく,その逃走の軌跡の絡み合いこそが,「音楽」であり,「人生」なのであって,そのなかでは死ぬ者もいるが,また別の者はそこから平然と逃れ去ってゆくのである
――あのポールの妻子のように.
作者自身の交通事故を思い起こさせずにはおかないポールの死のシーンは,『勝手に逃げろ/人生』で最後に現われるスロー・モーションである.それは,ある意味で『勝手にしやがれ』の末尾での瀕死の疾走と死を反復する,「破局的スローモーション」(蓮實重彦)なのである.だが,それは過去から未来に向けられていた流れがとつぜん断ち切られるという意味で破局的=悲劇的なのではない.むしろ,その切断は,過去も未来もないカタストロフ点としての現在を切り取ってみせるだけなのだ.実際,道に横たわったポールは――「ちょっとバカみたいに」――言うではないか.「ぼくは死にかけているわけじゃない,ぼくの全生涯が目の前を通りすぎるのが見えなかったんだから」.過去はない.未来もない.ただ,現在だけがある.そのような現在を,『勝手に逃げろ/人生』のゴダールは,『勝手にしやがれ』を反復するようにして,スクリーンの上に明滅させてみせたのだ.『勝手に逃げろ/人生』がもうひとつの始まりであり,この映画が公開されたときゴダールが自分は新しい人生の始まりに立っているような気がすると言ったのは,それゆえなのである.そのようにして復活したゴダールが,15年後のいまいかなる地点に到達したか.それは,しかし,また別の問題である.
(あさだ あきら・社会思想史)
 GO TOP
GO TOP | No.13 総目次 |
Internet Edition 総目次 |
| Magazines & Books Page | |