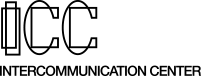荒川修作は,1961年末の渡米以来,世界各地での展覧会,マドリン・ギンズとの『意味のメカニズム』『死なないために』などの共著,また,《心・遍在の場/奈義の龍安寺》(1994),《養老天命反転地》(1995)などのプロジェクトで議論を巻き起こしてきた.荒川氏は,袋小路に入った西洋近代合理主義に対して,日本からの新しいパラダイム構築の必要性を身体性(幻影肢)や「聖地」などをキーに主張した.「無体系で無思想で感覚的で形式の好きな日本人は,市民権とは何かすら考えたことがない,だから文明と建築する行為が同等であることを知らない.文明がないところでは文化などは無意味である」「聖地などは無意味であり,家,村,町こそ聖地とならなければならない」という論点は,これまでの身体性への問いかけを発展させたものである.また,その具体例として,臨海副都心へ提案中の「建築」プロジェクトが,スライドで紹介された.後半の塚本明子(東京大学教授),工藤順一(評論家),丸山洋志(建築家)をパネリストに迎えた公開トークでは,丸山氏から,文明を論ずるには歴史の層が必要であり,荒川氏は性急に過ぎるという批判がなされ,一般の聴衆からの質問でも,氏の西洋批判が西洋的な論理のもとにある点を指摘された.しかし,思想にとどまらない行動の実現を重視する荒川氏にとっては,この種の批判は次元の異なるものであった.「私には時間がない,誰かがやらねばならない,私がまず先に行動すれば,誰かが後に続くのだ.君たちはその後に文章や思想で建築してほしい」という荒川氏の言葉は,パネリスト,建築関係者を含む200人に及ぶ聴衆に強く訴えかけた.
『ICCコンセプト・ブック』(NTT出版,1997)より引用