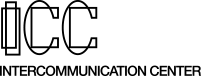侵犯行為は限界に関わる動作である.
そこ,細い一本の境界線においてこそ,
その稲妻のような通過が明らかになるけれども,
たぶんその全体としての軌跡
その起源そのものも明らかになるのだ.
言語はその起源において,発話という行為によって自然の調和を乱す侵犯行為だったに違いない.しかし同時に知覚が言語によって乗り越えられると,認識はあたかもあらかじめ存在したような世界を模造する.また記憶は「母の顔」「恋人の声」「空の青さ」のように無限に関わる動作として体験される.しかし,ここでも言語はみずからに備わった形式によって,本来対象化しえないものを連続的に編成する.このように言語は,無限ということを露呈することをやめて,空虚な空間のうちに,みずからが侵犯すべき限界を位置づける.今や私たちはこの言語の厚みにこそ,有限性と存在とを経験するのだ.そこに神秘は存在しない.そこでは全体と起源は,細い境界線上の動作によってこそ示される軌跡なのだ.祈祷の秘かな言語が,敬虔な愉悦の孤独のうちに,息絶えるような一点をしるしづけるように,それは絶えず語りつづけることによって不在そのものに触れ,存在が遅滞なく出現する瞬間なのだ.一つ一つの言葉のもとに,言語が実体として問題になってくるようなあの限界に思考を連れ戻し,繰り返し遠くから有限性を指し示す.そのことこそが神秘なのだ.
作家紹介
ともに京都市立芸術大学に学んだ砥綿正之と松本泰章のコラボレーションは,1991年のプロジェクト《ディヴィナ・コメディア》に始まる.
1991年8月28日から9月2日まで神戸のジーベック・ホールで行なわれた《ディヴィナ・コメディア—死のプラクシス—》は,秘儀めいたプロセスと大がかりな装置によって,そのタイトル通り,死のシミュレートをするという作品であった.5人の体験者は防塵服を着せられ,青いジェルで満たされた巨大なプールに浮遊しながら横たわる.そこでフラッシュ・ライトと音響効果による刺激をあびるうちに,次第に胎内回帰願望の満たされた至福の感覚を味わったり,身体感覚が失われて脳だけが取り残された状態に陥るという.恋愛の関係の絶対性を「死と再生」の叙事詩にまで昇華したダンテの『神曲』をテーマとするこの作品は,テクノロジーによる身体感覚の変容を通して,「死と再生」を実際に味わうものであった.
《ディヴィナ・コメディア》が,同時に参加する5人に対してある種の共有体験を与えるものであったとすれば,1992–93年に水戸芸術館で行なわれた《トロバール・クリュス》は,より孤独なかたちで体験するための作品であった.《トロバール・クリュス》とは,ヒエロニムス・ボッシュが作品に描いた透明な球体のイメージによるもので,閉塞体を意味する.人ひとりが横たわれる透明な容器にジェルがたたえられ,この700kgになるという水槽が2m近くの高さに細い鉄柱で支えられる.応募者の中から選ばれた体験者が一人でその中に横たわると,データ・フラッシュが開始する.そこでは多数の観客と体験者という見る-見られる関係がより明確に介入し,開かれた環境の中での「死と再生」の体験を試みるものであった.
一方,1995年5月に開催された「マルチメディアーレ4」(ZKM,カールスルーエ,ドイツ)には《重力と恩寵》と題された作品が出品された.作品の前に立つと,薄暗い鏡に映る自分の姿に,幽かな「精」がオーヴァーラップするように顕現する.阪神大震災の犠牲者に捧げられたこの作品のタイトルは,シモーヌ・ヴェイユの著作から取られている.ヴェイユによれば,たましいの自然な動きを支配するのは「物質における重力の法則と類似の法則」であり,唯一それから除外されるのが「恩寵」である.滅びやすい存在である人間の肉体と,精神を司る法則としての,ある超越的なものを感じさせる作品である.
これらは,タイトルにおける「引用」という手法によって導かれる思想性を背景としつつ,いずれも参加者の身体を介してはじめて成立する作品である.そこではとりわけ,ひとつのヴェクトルとして存在する「重力」というものが,さまざまなかたちで明らかにされるが,さらにその中で不意にたち現われてくる超自然的なもうひとつの力を予感させるものとなっている.それは,ヴェイユの言う「宇宙に君臨するふたつの力」を,まさしくふたつながらに体験させようとする試みなのである.