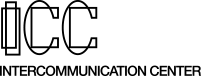季刊 InterCommunication No. 47 2004 Winter
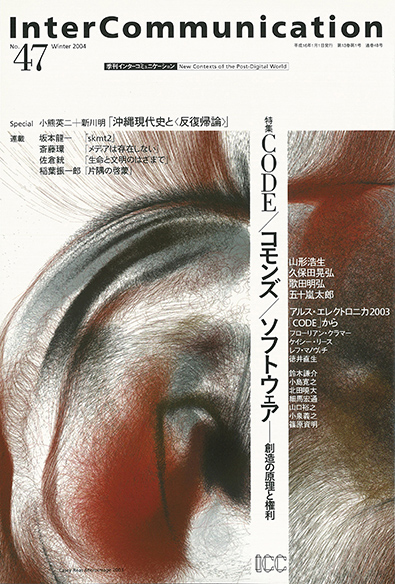
特集
CODE/コモンズ/ソフトウェア
——創造の原理と権利
アルゴリズムとしてのアート 山形浩生
Exe.cut[up]able statements:——ユーザー・インターフェイスへと急浮上するコード フローリアン・クラマー/大宮勘一郎[訳]
プログラミング・メディア ケイシー・リース/江渡浩一郎[訳]
それをアートとは呼ぶまい——アルス・エレクトロニカ2003「CODE」 レフ・マノヴィチ/白井雅人[訳]
ソフトウェアはアートになりうるか——アルス・エレクトロニカ2003「CODE」レポート 徳井直生
プログラミングと演奏——コレクティヴ・ヴァーチュオーソの誕生 久保田晃弘
友達の友達はみな友達?——セマンティック・ウェブとウェブログ 歌田明弘
[CODE/コモンズ/ソフトウェアの観念史]
民主的に支えられる資本主義——『CODE』と『コモンズ』とクリエイティヴ 鈴木謙介
環境と所有権——コース、ハーディンと「コモンズ」 小島寛之
チューリング・テストと対話アルゴリズム 細馬宏通
パサージュとヴァルター・ベンヤミン 山口裕之
「反ソフトウェア」——キットラーの言説分析、あるいはピンク・フロイドについて 北田暁大
機械とジル・ドゥルーズ 小泉義之
開かれた作品とウンベルト・エーコ 篠原資明
なぜ《ワラッテイイトモ、》のアラン・スミシー・ヴァージョンは、かくも猥褻で、美しく、そして笑えるのか 五十嵐太郎
TREND MIX
Film スタイル=コピーの時代——アメリカ映画の現在 1 青山真治
Books 「作者」はコードになるのだろうか——松澤和宏『生成論の探求』 石原千秋
Performance イギリス、フリンジ・シアターの新展開——shuntの実験にみる「68年的運動」の再生と進化 大野裕之
Music オーストラリアのサウンド事情 藤枝守
Mathematics まあそんなに急がないで、じっくり考えてみてよ 深谷賢治
“学術界のロック・スター”ジジェクの新著 小林浩
“2軸動作”で見る2003年のスポーツ界 小田伸午
うろこが語る、新・街並みの美学 ぽむ企画
Special
沖縄現代史と〈反復帰論〉 小熊英二+新川明
連載
坂本龍一skmt2 05
後藤繁雄+中島英樹
メディアは存在しない 6 三囚人のシステム理論は可能か? 斎藤環
片隅の啓蒙 5 人間の条件と動物の生 稲葉振一郎
生命と文明のはざまで 6 アラマタ的な知のあり方をめぐって 2 佐倉統
ICCのページ
活動レポート 企画展「サウンディング・スペース——9つの音響空間」
活動レポート シリーズ展示「as media——メディアとしてのICC」
活動レポート 夏の子どもワークショップ「サウンド・アーティストになってみよう!」
インフォメーション
ICCのご案内
関連書籍案内
バックナンバー情報
常備書店/購読案内