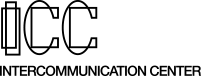季刊 InterCommunication No. 46 2003 Autumn
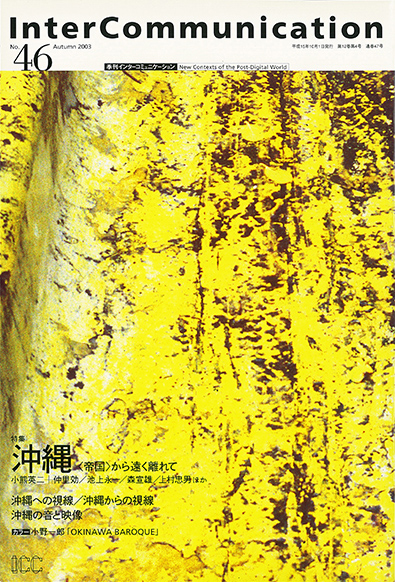
特集
沖縄——〈帝国〉から遠く離れて
カラー OKINAWA BAROQUE 小野一郎
対談 沖縄——視線と自画像の相克 小熊英二+仲里効
沖縄への視線/沖縄からの視線
〈沖縄〉の発見 1——琉球王国の自己呈示とヤマトからの視線を中心に 石原俊
〈沖縄〉の発見 2——欧米植民地帝国からの視線を中心に 石原俊
沖縄の原語——「琉球語」または「琉球方言」として 仲原穣
伊波普猷を読むということ——『古琉球』をめぐって 冨山一郎
『海南小記』の果て——民俗学・人類学と沖縄 原毅彦
「国文学」と沖縄——文化の三層 藤井貞和
米軍占領下の沖縄文学——異文化接触という隠蔽に抗って 新城郁夫
沖縄文学の現在——「他者の言葉」で/を書く 新城郁夫
芸術と沖縄——忠太・宗悦・太郎と沖縄の反応 翁長直樹
沖縄文学の回帰する台風——知念正真『人類館』 鵜飼哲
沖縄は植民地か——ポストコロニアリティの歴史認識 屋嘉比収
沖縄は植民地なのか?——「反国家」の「闇の奥」への遡航 森宣雄
物語世界のなかで——南島をめぐる言説と沖縄 田仲康博
沖縄ブームの陰で——メディアが表象する沖縄 田仲康博
ウルトラマンの作家たち——金城哲夫と上原正三 切通理作
「沖縄ポップ」について——「沖縄同士の差異」から「日本の中の沖縄」へ 新城和博
沖縄の幽霊——中江裕司と青山真治の映画から 北小路隆志
山形国際ドキュメンタリー映画祭2003 沖縄特集——琉球電影列伝/境界のワンダーランド
写真と〈沖縄〉——記録と表現のはざまで 大竹昭子
沖縄ポップと「しまうた」——融解する境界 久万田晋
インタヴュー 「物語」が生まれる場所 池上永一/大城譲司[取材・文]
「沖縄人プロレタリアート」と「琉球南蛮」——沖縄戦後史の終焉の現在 森宣雄
身体の奥の眼?——〈沖縄〉とヘテロトピアの思考 上村忠男
折込 沖縄マップ——基礎データ/歴史・基地・観光
TREND MIX
Books 屹立する郊外——川本三郎『郊外の文学誌』 石原千秋
Film 『ファム・ファタール』または天国は待ってくれるか?——ブライアン・デ・パルマ『ファム・ファタール』 青山真治
Performance 歌舞伎になったチャップリン——八月歌舞伎座の実験が教える日本文化の粋 大野裕之
Software Generativeなソフトウェア——プログラマとユーザのあいだの“ゆらぎ” 徳井直生
Mathematics (数学の)問題が解けないときはどうするか 深谷賢治
ハーバーマスとデリダの“共闘” 小林浩
発想の原点をめぐる本たち 柳喜悦
フォークトロニカ——オーガニックなエレ/アコ混合サウンド 松山晋也
ルチアーノ・ベリオ、はじめの10枚 白石美雪
開放的なユーモア——イオセリアーニの映画 細川晋
Special
to be continued——ビリー・クルーヴァーとE.A.T. 岡崎乾二郎
連載
メディアは存在しない 5 ゴースト、あるいは複製に抗う残余 斎藤環
片隅の啓蒙 4 虚構とポストモダン 稲葉振一郎
生命と文明のはざまで 5 アラマタ的な知のあり方をめぐって 佐倉統/荒俣宏[ゲスト]
ICCのページ
展覧会レヴュー コンサート「デイヴィッド・テュードア《レインフォレストⅣ》
音の降る雨林 川崎弘二
展覧会レヴュー 「サウンディング・スペース——9つの音響空間」
「サウンド・アート」とは何だったのか 柿沼敏江
音楽から音響へ 針谷周作
インフォメーション
関連書籍案内
バックナンバー情報
ICCのご案内
常備書店/購読案内