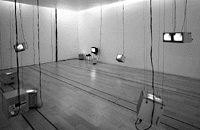
分断された時間へのフェティシズム
A Fetishism of Divided Time
「ザ・セカンド
――オランダのメディア・アート」
1998年11月13日−12月27日
ICCギャラリーA, D
"THE SECOND / Time Based Art from the Netherlands"
November 13−December 27, 1998
ICC Gallery A, D
1997年に開催されたドクメンタ10は,現代美術がますます映像文化に傾斜していく様子を提示した.ドクメンタに代表されるこのような流れのなかで「時間」という要素はどのように捉えられているのだろうか.ICCで行なわれた「ザ・セカンド」展は,決して大規模ではなかったが,作家たちの繊細な視線を示す印象的な展覧会であった.本展は,モンテヴィデオ/TBA,オランダ・メディア・アート・インスティテュート企画のもので,アムステルダム,メキシコシティ,台北を巡回し,東京ICCに立ち寄ったことになる.モンテヴィデオ/TBA,オランダ・メディア・アート・インスティテュートとは,本展のゲスト・キュレーターでもあるレネイ・コエルヨによって1978年に創設された組織で,オランダ国内のメディア・アーティストの育成とその作品の展示,販売,保管を旨としている.組織の名前にTBA(Time Based Art)とうたっているように,メディア・アートを時間との関連で捉えていることが特徴であろう.今回の展覧会は,1989年にコエルヨによって企画され世界8か国を巡回した,メディア・アートを主体とする「イマーゴ,オランダ現代美術の世紀末」展の続編にあたるものと言える.
音声素材やフィルム,ヴィデオを用いるメディア・アートは,その本質的な契機としてすでに時間を含んでいる.このメディア・アート自体がどのように時間を反省的に捉えるのかということに,筆者は関心をもった.当然のことながら映像を垂れ流しているだけでは時間を把握したとは言えないからである.しかし,展覧会全体を通して見ると,「Time Based Art」というよりむしろ「ディテールと全体」,「アスペクト(象面)と再構成」といったキーワードが相応しいと思われた.ヴィデオ・モニターやコンピュータを通じて,細分化・断片化された情報を観賞者に提示し,観賞者の側でその再構成を行なうといった基本的なプロセスが,どの作品においても期待されているように感じられたからである.その結果見えてくるものは,細かく分断・分析された時間だけであり,有機的な時間の流れや時間と相関する永遠といった要素はもはや(筆者には)感じられなかった.
例えば今回の展覧会の「中心となるインスタレーション」(R・コエルヨ)とされる,ペーター・ボーガースの《ヘヴン》(1995)を見てみよう.白く塗られた部屋の中に17台の小型ヴィデオ・モニターが設置されている.あるものは壁に掛けられ,あるものは釣り下げられ,あるものは床に置かれる.いずれも実際の空間であればそこにあるべきもの(時計,昼寝する猫,人物等)の一部分を提示している.そのおのおのは規則的に繰り返し1秒間音響と映像を流す.この奇妙な空間に入り込むと,われわれは提示された映像の断片を可能な限り捉えて,それを総合しようとせざるをえない(この空間の居心地の悪さから逃れるために).そこからどこか初期キュビスム的な時空間がたち現われてくる.つまり観賞者が主体的にモニターに向き合い,分析と総合を行なわなければ現われてこない世界がここにはあるのだ.
このボーガースはオランダでは評価が高くほかにも2作品が本展に取り上げられている.例えばその一つ《レトリカ》(1992)は,2台のテレビ・モニターにそれぞれ映し出された父と子がコミュニケーションを図るという作品である.テレビ・モニター同士が互いに対話するという発想はかつてのブルース・ナウマンにも見られた.ナウマンの旧作《ピエロの拷問》(1987)は不毛な物語を二人のピエロが延々と繰り返す,悪夢のような閉鎖的コミュニケーションの世界を展開していたが,一方ボーガースは赤ん坊の言葉にならぬ声とそれに応答する父という微笑ましい光景を見せている.しかし,父子の姿が眼と口だけで表現されるため,このコミュニケーションは次第に何か気味の悪い生物が身をくねらせながら会話しているようにも見えてくる.
同じボーガースの《サクリファイス》 (1994)は,会場入口にあってきわめて印象的であったが,バスタブの水におぼれかかっている(溶けかかっている?)作家自身の口をレンズの奥に覗かせる作品である.作品の制作現場を示す大きな写真が共に展示されており,その写真にはきわめて大仰な機械を用いて自分を撮影をしている作家の姿が示されている.複雑なプロセスを用いて自分の口という部分に執着する作家の姿は,サクリファイス(犠牲)という題名と相まって,どこか薄気味悪く見えてくる.テレビ・モニターというこの見慣れた装置は,人を微視的な視線へと導き,そこから部分への偏向,フェティシズムを否応なく生んでしまうものなのだろうか.同じフェティシズムへの傾向はA・P・コーメンの作品にも見られた.《フェイス・ショッピング》(1994)と題されたこの作品は,隣接された4枚のスクリーンに,女性の顔のふとした表情を投影しつづけるものである.彼女たち自身も気づいていないような頬や瞼のティックを,作家は執拗に追う.ここに投影されている女性たちの見てはならぬ瞬間をのぞき見てしまったような,怪しい感覚を観賞者はもつことになる.
このようなフェティッシュな視線とは離れたかたちで,分断された「時間」に触れているのがベア・デ・フィッサーとボリス・ヘレッツである.前者の《スキッピング・マインド/忘却についてのフィルム》(1994)で作家は,古い本から見出したある女性の一連の肖像画を「モーフィング」によってまるで生きているかのように動かしている.
後者の《時間/断片》(1994)で作家は静止したヴィデオ映像を回転させ,ストロボ効果を用いて動くパノラマを現出させる.両者の作品は,共にその仕組みをわかりやすく提示している.ヘレッツの作品は渾天儀めいたブロンズの台座に設置されており,その台座には「時間とは,動くことなき永遠の,動ける像である」という聖アウグスティヌスの言葉が刻みつけられている.この言葉が両者の作品を端的に象徴していると言えるだろう.ほんのわずかにずれた静止画像を連続させることで,われわれは「動き」と「時間」のイメージを得る.周知のとおりフィルムやアニメーションの原理であるが,この原理からフィッサーとヘレッツは「蘇生」あるいは「受肉」というべきプロセスを読みとったのだ.凍り付いた映像が生命をもって動き出す.彼らは分断されていた時を再び息づかせようとしている.
本展カタログでルディ・フックスは,オランダ絵画の伝統である「忍耐強い意志 a patient will」が現代オランダのメディア・アーティストたちの制作にも見られることを指摘している.確かに,「ザ・セカンド」展の面々は,対象に繊細な視線を忍耐強く向けることではじめて見えてくるものをつかんでいる.しかし,たとえそこから立ち現われてくるものが親密な相をもっていたとしても,それらは分断された破片にすぎないのだ.破片をつなぎ合わせることで有機的な時間の蘇りを目指すフィッサーやヘレッツのようなアーティストもいるが,彼らにしてもフランケンシュタインのごとく,いびつなモンスターを生み出すにとどまったのではないか.これら一連の作品に示されているのは,このメディア時代の時間感覚なのだろう.われわれの対面している世界を,断片的情報からなる知的構築物と捉えたとき,時間もまた断片的情報として理性的にのみ処理されねばならないものになるのだろうか.また人の視線はただ微視的になってしまうのか.そのような時間は筆者にとっては偏向した薄気味悪いものに感じられるのだが.ボーガースの作品と並んで本展入口に設置されていたヤープ・デ・ヨングの作品《O.T.S.》(1995)は,そのような断片的なヴィデオ作品を集めた作品である.しかし,モニター代わりのガラス玉を収めた,8角形の展示ケースは,作家のメディア・アートへの愛着をあたかも宝箱のように見せており,そのささやかな愛情が筆者には救いとなった.
- かりや・ようすけ
- 1970年横浜生まれ.
- ワタリウム美術館スタッフを経て,慶應義塾大学大学院修士課程(美学美術史学)在籍.ヨーゼフ・ボイスを中心としたドイツ20世紀美術を研究
