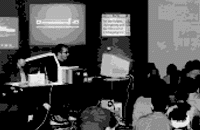
「ニック・フィリップ/
セレクテッド・ワークス」
ギャラリーD
サンフランシスコ在住の若手デジタル・デザイナー,ニック・フィリップを招いての当イヴェントは,彼の過去の代表的なデザインワークの展示と,計4回のワークショップによるものであった.彼は約10年前にロンドンで活動を始め,パンク・カルチャーに影響を受けた挑発的なデザイン,特にTシャツなどのデザインで注目された.そのTシャツや,その後サンフランシスコに移住し,デジタル・デザインを始めた頃の初期のグラフィック・デザイン,さらに雑誌『WIRED』創刊期の仕事など,パーソナル・コンピュータの普及と同調したデジタル・デザインの隆盛期の躍動感ある作品が展示され,注目されてきたデザイナーである.
この1990年代前半頃の,彼のデザインに特徴的なのは,デジタル・デザインという手法を採りながらも,急速に展開するデジタル・カルチャーへのアイロニカルな視点を常に保持している点にあろう.デザイナーという立場には稀とも言える社会に対する批判的なスタンスが,そこから明確に読み取れるのである.いまとなっては意外な印象すら受けるが,雑誌『WIRED』は,その発刊当初はそうしたスタンス,いわばアンダーグラウンドなイメージをもった雑誌であったことからも,彼がいわゆるコマーシャルなデジタル・デザイナーとはその出自を異にすることが窺えよう.
その後彼は西海岸のレイヴ・シーンを代表するデザイナーの一人となり,1960年代後半のサイケデリック・ムーヴメントの再来とも言える作風に転換していく.デジタルなテクノロジーが,外面的,生産的側面ばかりにではなく,人間の精神世界に与える影響について,彼はグラフィック・デザインや音楽など,幅広い分野の表現を展開したのである.その活動は昨年発表したCD-ROM 《ラジカル・ビューティ》に結実していると言えるが,そこでは特に人間の身体についての関心が強められている.また,今回も一部展示された最新作《ジ・エンド・オブ・マン》シリーズも,テクノロジーと身体との直接的な関わりに焦点をあてた作品であり,デジタルな手法によりながらも,有機的なイメージを常に感じさせるものであった.
さて,今回の展示で特筆すべきものは,新作インスタレーション《ノーウエア・コム(nowhere.com)》であろう.彼は近年のインターネットの動向にも強い感心をもってきた.その彼の現在のインターネット社会に対する痛烈な皮肉とも言えるこの作品について,やや詳しく述べてみたい.
「ノーウエア・コム」とは,いわば架空のインターネットにおけるドメイン名である.ご存知のように,インターネット上にはそこに参加する人々の「住所」であるドメインが無数に存在する.このドメイン名は,一元的に管理されており,決して重複しないようにされているのだが,架空の,すなわち実在しないドメイン名を騙って,電子メールなどを利用する連中が存在する.つまり彼らは自分の住所=身元を明かさぬようにして,他人にメールを送りつけるのであるが,そうした連中が任意に付ける架空のドメイン名の代表例が,「ノーウエア・コム」なのである.
この「ノーウエア・コム」ドメインより送り出されるメールは,ほぼ100パーセントがいわゆるジャンク・メールやスパム・メールである.怪しげな商売の勧誘や,誹謗中傷,いやがらせなど,インターネットの裏社会を象徴する内容のメールがそこから,日夜無数に送り出されているのだ.この作品は,その「ノーウエア・コム」ドメインからのメールをいわばリアルタイムにハッキングし,モデムに接続された12台のFAXから出力するインスタレーションなのである.
世界中のどこからか「ノーウエア・コム」ドメインからのメールが送られると,コンピュータがランダムにモデムを起動し,FAXに電話をかける.並んだ12台のFAXはそのジャンク・メールを次々と滝のようにプリントアウトしていくのである.FAXには100メートルのロール紙がセットされており,下には大きな「ゴミ箱」が置かれている.最初の一日で,もうFAX用紙はゴミ箱をあふれだし,最終日にはうずたかくその回りに積もっていた.
われわれは,ネットワークを流れる膨大なデジタル・データを,視覚的,身体的にリアルタイムに認識することは,日常的にまず不可能である.この作品は,多方向性,同時性,匿名性,簡便性といった電子メール=インターネットの特質の負の側面を,明解に視覚化した作品と言えるだろう.けたたましいダイアル音と着信音を立てながら,12台のFAXより延々と吐き出されていくその「ゴミ」メールの山は,ネットワーク社会の現状と未来の一側面を,まざまざとわれわれに見せてくれた.
また,会期中4回行なわれたワークショップでは,前半の2回が彼の作品についてのレクチャー,第3回が棟朝隆二,GEOの両ゲストを招いてのDJによるコンサート,最終回が彼の助手ジェフ・テイラーと共同でのグラフィック・アプリケーションPhotoshop5.0の講座であった.総じて,デザイン関係の学生など,若い客層がその参加者のほとんどを占め,日本ではテクニカルな側面ばかり追い求められがちなデジタル・デザインの世界で,そのコンセプトを中心としたレクチャーが新鮮なものに感じられた.
ストリート・カルチャーにその基盤をもつアーティストらしく,総じて展覧会,ワークショップともリラックスした雰囲気で進行し,来場者との直接的なコミュニケーションの場面も多くみられた.またアーティスト,来場者双方とも同時代的な共感をもって成功裏にこのイヴェントが終えられたことは,今後,ジャンルを問わず,ICCにおける若手アーティストによるイヴェントのありかたの,一つの好例となりうるものであったと言えるであろう
[後々田寿徳]

 目次ページへ
目次ページへ