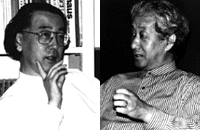
架橋される60年代音楽シーン
Bridge-Building
from the 1960s Music Scene
60年代の輻射熱
――昨年磯崎さんが企画監修され,一柳さんも参加された「日本の夏 1960−64――こうなったらやけくそだ!」展(1997年8月2日−9月28日,水戸芸術館)は意味深長かつ懐かしい謳い文句でした.1997年の時点で「こうなったらやけくそだ!」と謳ったのはどうしてでしょうか.
磯崎──あの展覧会は最初「日本の芸術1960s」というタイトルだったんです.「1960−64」という区切りについて言うと,1965年頃から,次第に何か混沌とした埃が舞うような雰囲気が消えていって,最終的に万博アートに至る動きが始まったのではないかという思いがあります.別の言い方をすれば,64年というのは「読売アンデパンダン」展[★1]を主催者の読売新聞社がその役割を終えたとして「やめた」年です.ちょうどそのときに東野芳明vs宮川淳の「反芸術」論争[★2]がありました.それまで「読売アンデパンダン」展などに集結してきた「汚い,臭い,危険」のいわば3K作品を背景にして具体的には工藤哲巳[★3]の作品を東野芳明が「反芸術」と名指し,それまでの芸術行為との線引をしたわけですが,結果的に見たら宮川淳の「反芸術といえども芸術という枠から逃れられない」という一言でけりがついた.つまり「反芸術」が終わった年が64年であって,65年から変わっているのではないか,それならその60−64年のあいだをターゲットにしようということになったのです.
「日本の夏」としたのも思いつきで,「芸術」じゃなくてホットな時代ということで「夏」のほうがいいんじゃないかとなり,ついでに牛ちゃん(篠原有司男[★4])へと流れていって,彼の作品タイトルを借用したわけです.《こうなったらやけくそだ!》という牛ちゃんの作品が出品されたのは59年の第11回「読売アンデパンダン」展です.
その頃一柳さんは帰国前に『朝日ジャーナル』にアメリカのジョン・ケージなどの動きを紹介されていたと思います.それが予告であり,一柳さんが現われ,ケージが現われた,という感じで僕は60年前後を受け取っていました.
一柳──私の場合は61年の夏までアメリカにいたものですから,60年代といってもどちらかというとアメリカに半分足をつっこんでいて,しかもむしろ50年代の後半から,熱気のある,いわゆる60年代的と言われるものをニューヨークで体験しはじめました.だから日本のことについては疎いところがあります.ただ私の感じでは,アメリカのその時期の盛り上がった活動の一番の口火は,ニューヨークで1958年にジョン・ケージの作曲活動25周年演奏会がタウン・ホールであった[★5]ということでしょう.このときマース・カニングハムが指揮をしたり,室内オーケストラぐらいの編成でデイヴィッド・テューダー[★6]が演奏したりして,過去25年間のケージの主だった作品をやりました.いわば偶然性音楽の最初のお披露目公演であったわけで,その演奏会にジャスパー・ジョーンズなどいろいろなジャンルの人たちが来ていました.
そしてニューヨークで66年の秋に「劇場と技術の9晩(9 Evenings: Theatre and Engineering)」[★7]という催しがありました.ここに50年代後半から60年代前半に活動してきたいろいろな分野のアーティストが集結して,しかもベル研究所のビリー・クリューヴァーという人がテクノロジーの方面から参加していました.そこで当時の芸術と技術の一連の活動の集大成が行なわれて,それから後はヴェトナム戦争が始まり,アメリカにおける芸術活動も拡散してきました.だからアメリカでは頭は58年のケージで,一つのけじめは66年秋の「劇場と技術の9晩」だと思います.
日本では,ちょうどそのまん中くらいになるんですが,音楽で言うと61年にいろいろなものが集中的に高揚して発生したということだと思います.
磯崎──帰国されてからの一柳さんは音楽家としての活動の中で,新宿の「ネオ・ダダ」[★8]の残党とか「暗黒舞踏」[★9],「グループ音楽」[★10]の連中と接触されたでしょう.
一柳──そうですね.61年の8月に二十世紀音楽研究所[★11]の音楽祭がアメリカ前衛音楽の特集をやってケージやフェルドマンらを採り上げたのですが,それらを演奏するためにその年の夏に帰国しました.高橋悠治はデビュー演奏会を10月にやり,ケージの《ウィンター・ミュージック》を全曲1時間40分かけて弾いたんですが,1曲に2時間近くかけるというのはあまり日本の音楽会にないことでかなり波紋を呼びました.そのひと月前に小杉武久たちの「グループ音楽」の演奏会があり,これは即興演奏を主体にしたものでした.非常に新鮮で,ぜひ彼らに11月の私の演奏会に出てもらいたいと思いまして,それからつきあいが始まったんです.じつはそういうものが日本にあるとは予想していませんでした.私の音楽会で誰にグラフィックの楽譜によるものだとかハプニング系統のものをやってもらおうかと考えていた矢先だったものですから…….

 次のページへ
次のページへ