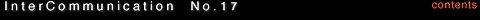
1972
長谷正人
本書は,文化人類学,精神病理学,生物進化論,情報理論(サイバネティックス)等,生涯に渡って様々な専門領域を自由に横断し続けたベイトソンの主要論文を網羅的に収めたものであり,彼の思想の全体像を一挙に知ることができる便利な論文集である.しかも,諸論文が扱う対象は多様であっても,彼の主張の核心部は常に一貫しており,どの論文から読み始めても彼の思想の大枠は明快に理解できるはずである.すなわちベイトソンは,彼自身が属しているアングロ・サクソン的な西欧文明が,目的達成の効率性をひたすら増大させて行くことによって文明的秩序のバランスを破壊しつつあることを痛烈に批判し,これに代わって,目的追求行動自体の「循環的」性質に気付くことができるようなサイバネティックス的発想(DDTによって害虫駆除という目的を達成すると,その虫を食料にしていた虫までが死んでしまって,結局ますますDDTに頼ることになる,といった)を西欧文明の中へ導入し,このバランス破壊に歯止めをかける必要性を訴えているわけである.タイトルの「精神の生態学」とはまさに,彼が理想とする,このようなサイバネティックス的発想法のことであると言えよう.
従って当然のことながら,「アートとテクノロジー」という問題も本書においては,こうした枠組みのなかで扱われることになる.ベイトソンにとって「テクノロジー」は,西欧文明の自己目的的な効率追求性を拡大するものとして,常に批判の対象となっている.例えば「今日では日々効率を増していく機械が,交通のシステムが,飛行機と武器と医薬品と殺虫剤が,意識の目指すところを強力に推進し(……)身体のバランスも社会のバランスも生態系のバランスも,突き崩」してしまっていると述べられているように(p.580).しかしわれわれは,こうした西欧文明の方向を転換するために,「意識の目指すところ」(害虫を駆除せよ)のみならず「生き物としてのシステム全体から差し出されてくる知識」(虫を殺せば鳥も死ぬ)を上手く受け止めなければならない.そのように人間の精神を訓練する役割を担うのが,ベイトソンにとっての「アート」(芸術)なのである.彼によれば「芸術」は,「部分的に無意識なメッセージ」を伝えるコミュニケーションである.つまり,なぜその技術が素晴らしいのかを言葉では説明できなくても(いや,できないからこそ),まさに素晴らしいものとして無意識的に伝達されるような独特のコミュニケーションである.このような「部分的に無意識な」コミュニケーションこそ,私たちの視野を,目前の目的のみならず,それを包み込むシステム全体へと広げていくというわけだ.このようにして,「芸術」は,「生に対するあまりに目的的な見方をよりシステミックな方向」(p.222)に転換する治癒的役割を持つものだとベイトソンは主張するのである.
しかし,私たちはここで注意しなければならない.ベイトソンはけっして,テクノロジー的なるもの(意識的なもの)とアート的なるもの(無意識的なもの)を単純な二元論によって,例えばデジタル対アナログのように真向から対立させているわけではないからである.事実彼は,無意識としての「情感」を始源的な「力」のようなものとしてロマンチックに賞揚する発想を,無意識を意識的に制御しようとするアングロ・サクソン的発想として批判している.逆に彼によれば,無意識は(フランス人パスカルに倣って)「精密な演算規則」を持つものとして捉えられなければならないのだ.つまり,アナログ的な無意識をデジタル的なものとして分析することにこそ,ベイトソン的「精神の生態学」の真骨頂があるのである.従って彼は本書のなかで,「芸術」とか「遊び」とか「ユーモア」とかいったアナログ的なものを,システム論の用語によってあくまでデジタル的に説明し続けているはずである.こうして以上のことから,ベイトソンにおける「アート」と「テクノロジー」の関係は,まさに両者が交差し統合される地点でこそ捉えられなければならないものだったと言うことができよう.
(はせ まさと・社会学)
■関連文献
モリス・バーマン『デカルトからベイトソンへ....世界の再魔術化』(柴田元幸訳),国文社,1989.
ポール・ワツラウィック『希望の心理学....そのパラドキシカルアプローチ』(長谷川啓三訳),法政大学出版局,1987.
R・D・レイン『好き? 好き? 大好き?』(村上光彦訳),みすず書房,1978.
ダグラス・R・ホフスタッター『ゲーデル,エッシャー,バッハ』(野崎昭弘他訳),白揚社,1985.