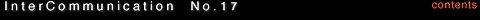
1947
梅津元
「カヴァー裏のカット〈走る牡鹿〉(ステップ芸術の小銅板)は,カヴァー表のカット〈エヴァ〉(ロマネスクの大壁彫)と較べるとき,原物は100分の1の小さなものであるが,複製の上では同等の迫力を見せる.しかしこの空想の美術館の力は虚偽の力ではない」.本書の主張は,カヴァーに配された写真の選択と,上記の短い文章に集約されている.
マルローは,まず,美術館が芸術作品と観る者との関係を一変したことを指摘し,「美術館は,芸術作品を他の一切(すべて)のものから引離し,それを対蹠的な或いは対立的な立場にある作品の傍近くに引寄せてみる」と述べる.しかし,美術館はさまざまな制約ゆえに,この比較を完全には行なうことができないため,写真複製による芸術作品の比較が必要とされることになる.これが「空想の美術館」であり,マルローによれば,「この空想の美術館は,現実の美術館による不完全な対照に端を発したところの知性化を極端にまでつきすすめる」ことを可能にする.当然,この「空想の美術館」では,芸術作品はその固有性を失うが,マルローは,複製が現実の作品の代替物にとどまるものではないことを様々な例を挙げて示している.さらにマルローは,「複製は,多くの作品を同時に見せてくれる故に,われわれに〈慎重な再発見〉の労を省いてくれる.そして或る芸術家を抽き出してくるように,或る様式を全体的に抽き出してくる」と述べ,写真複製がより積極的な役割を果たすことに大きな期待を寄せている.
本書でマルローがめざしているのは,まさに,この「様式の抽出」である.そして,この「様式の抽出」によってマルローが価値づけようとするのは,いわゆる古典主義美学とは相容れないさまざまな時代・地域の芸術である.ここで,マルローが乗り超えようとした古典的美の規範を成り立たせていたのが美術館という特殊な装置であったことに気づくならば,マルロー自身の言葉とは裏腹に,「空想の美術館」は「現実の美術館」を補足するのではなく,それを解体する試みであったことが理解できる.それゆえ,19世紀の美術館が見逃したものの再発見という視点が重視され,エジプト,ユーフラテス,ペルシア,ビザンティン,初期キリスト教美術,シュメール,あるいは東洋の美術までが広範に論じられる.知られていない様式は,それ自体として評価されにくく,すでに知られている様式からの逸脱,ないし失敗作と見なされがちである.しかし,写真複製を多数集めることによって,ひとつの様式を基準に否定されていたある作品が,別の価値を有する独自の様式のうちにあることが明らかになる.最終的に,マルローは,「〈芸術とは何か〉という質問にたいして,われわれはかく答えることになる.〈フォルムを様式にするものが芸術である〉」と結論づけ,芸術創造の心理はここから始まるとの宣言で本書をしめくくっている(本書は原題=『芸術の心理学』の第1巻にあたり,第2巻は『芸術的創造』となっている).
だが,本書でマルローが展開した様式論はあまり顧みられず,写真複製による「空想の美術館」という方法論の提唱だけが際立っている.なぜなら,マルローの様式論が個人的な趣味のレベルにとどまるのに対して,その方法論の提唱は,「美術史」という学問が写真なしでは成り立たないことをあからさまにしてしまったからである.本書の重要性は,写真複製を実物の代替としてではなく,芸術をめぐる議論において従来とは異なる見解を示すための「武器」として積極的に「使った」ことにある.写真以降のさまざまなメディア・テクノロジーが,さまざまな形態の複製を大量にもたらし,皮肉にもマルローの言う「芸術の知性化」に逆行するような状況が支配的な今日,マルローの提唱した写真複製による「空想の美術館」は,どのように読みうるのだろうか.
(うめづ げん・芸術学)
■関連文献
ヴィルヘルム・ヴォリンゲル『抽象と感情移入』(草薙正夫訳),岩波書店,1953.
ハンス・ベルティング『美術史の終焉?』(元木幸一訳),勁草書房,1991.
ヴィクター・バーギン『現代美術の迷路』(室井尚,酒井信雄訳)勁草書房,1994.
エルンスト・H・ゴンブリッチ「アンドレ・マルローと表現主義の危機」,『棒馬考....イメージの読解』(二見史朗,谷川渥,横山勝彦訳),勁草書房,1988.
ダグラス・クリンプ「美術館の廃虚に」,ハル・フォスター編『反美学....ポストモダンの諸相』(室井尚,吉岡洋訳),勁草書房,1987.