
| InterCommunication No.14 1995 |
 |
Feature |
TVに次の世紀はやって来るか?
渡辺保史
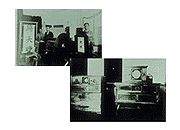
 前史,あるいは技術的混沌:19世紀後半 - 1920年代
前史,あるいは技術的混沌:19世紀後半 - 1920年代 黎明:1930 - 40年代
黎明:1930 - 40年代 発展:1950 - 60年代
発展:1950 - 60年代 グローバリズムとシステム化:1970 - 80年代
グローバリズムとシステム化:1970 - 80年代 再び混沌へ:1990 - 2000年代
再び混沌へ:1990 - 2000年代 ブロードキャストからインターミディエートへ
ブロードキャストからインターミディエートへ「遠くで起こっている出来事を居ながらにして見たい」――こうした視線の拡張への欲望と電子テクノロジーが接点を見出した時,それが「テレ=ビジョン」というメディアの生成史の幕開けとなった.しかし,TVは最初から今日のような社会的存在様態として構想されていたわけではなく,写真や映画,あるいは蓄音機や電信電話,ラジオといった他のメディア・テクノロジーと混然一体となった可能性の塊として社会に潜在していた. われわれが目の当たりにしているメディア技術の発達史は,結果としてリニアな構造の物語(たとえば電信から電話へ,無線からラジオ,そしてテレビジョンへ,というような)として一般に認識されているけれども,電子テクノロジーを用いて映像を送受するシステムは,電信電話や映画などのテクノロジーとほぼ同時期の1860年代より既に構想されていたのである.このTV前史と呼ばれる時期にあって,映像の電子的記録/送受のテクノロジーは,今日でいうTVはもとより,ファクシミリやTV電話,ケーブルTVなどの形態を含めた技術ヴィジョンとして夢想され,数多の試行錯誤が欧米で同時多発的に行なわれていた. 例えば,イタリア人のジョバンニ・カセリによる電信を用いたダゲレオタイプの伝送法「フォトテレグラフィ」や,フランス人コンスタンティン・サンレクによる電話を用いたカメラ・オブスキュラの伝送法「テレクトロスコープ」,電話の発明者アレクサンダー・グラハム・ベルによる動画を送ることのできるTV電話とでもいうべき「フォトフォン」などの装置が構想されていた. その後,1884年にドイツ人パウル・ニプコーによる,発光体を電気信号に変換するための金属円板の開発が機械式テレビジョン実用化のブレイクスルーとなり,また1897年にはドイツ人フェルディナント・ブラウンがTV受像機の原型である「オシロスコープ」(ブラウン管)を発明した. その後機械式テレビジョンのシステムは,1907年にロシア人のボリス・ロージングによりほぼ完成の域にまで達し,イギリス人ジョン・ベアードによって実用実験が繰り返されていた.だが,ロージングの弟子で,ロシア革命後に合衆国に亡命したウラジミール・ツヴォルキンは1923年に「アイコノスコープ」を開発.また,高柳健次郎がニプコー円板とブラウン管を用いて「イ」の文字を浮かび上がらせるのに成功した.これが電子式テレビジョンのキー・テクノロジーとなって,以後急速に技術開発のフォーカスは機械式から電子式へとシフトしていく(なお,日本のTV=「無線遠視法」の技術開発は,1940年に開催予定だった東京オリンピックへ向けてほぼ実用の域に達することになる).こうして,1920年代には今日のTVを構成する技術的要件はほぼ確立されるのである.
以上のようなTVテクノロジー前史を担っていたのが独創的な発明家による個人仕事だったとすれば,それがメディアとして確立する30-40年代を牽引するのが,資本の論理であることは間違いない.産業システムとしてのTVが合衆国において本格的に実用化したことは,ある意味で当然と言えるだろう.移動手段を市民に平等に与えようとするT型フォードと同様,TVもまた市民にとって情報消費の平等を実現する民主主義のメディアとして認知され社会化されていったわけだ. とりわけ,TVが結果として現在見られるような商業放送システムとして成立した背景には,TVに先行してマスメディアとしての地位を確立していたラジオの存在様態が強力に作用していた.水越伸が分析しているように,「ラジオはテレビジョンをみずからに準拠したニュー・テクノロジーとしてあつかい,放送の未来型として枠付けていった」(『メディアの生成』). アイコノスコープを開発したツヴォルキンが1930年に,当時のラジオ・ジャイアントRCAに招聘されて後,TVは放送という具体的な応用を射程に置いて開発が進められる.当時,RCAの実権を握っていたのはラジオ無線を大衆の娯楽メディアとすることに成功を収めつつあったデヴィッド・サーノフ.ツヴォルキンが自身の手になるテクノロジーを産業・医療用映像システムとして位置づけていたのに対し,サーノフはその価値をラジオの後継的存在としての可能性に見出していた. 商業放送以外に,TVの応用可能性は考えられていないわけではなかった.例えば,演劇やコンサートの模様を同軸ケーブルを使って中継し,遠隔地の劇場の巨大スクリーンに中継する「シアター・テレビジョン」,あるいは今日のケーブルTVのような有料式の「サブスクリプション・テレビジョン」,あるいは番組ごとのペイ・パー・ヴュー・システムすら構想されていたが,結局これらのシステムは一部の実験レベルで終わってしまう. もう一つ,この時期の重要なトピックはスタンダードの確立である.1940年に合衆国におけるTVの標準規格は,RCAとその他の企業の激しい攻防のすえ,走査線525本,毎秒30フレーム,FM音声伝送というNTSC(National Television Standard Committee)方式に落ち着く(もっともNTSCはRCA主導の色合いが濃かった). また,黎明期のTVにとって発展の鍵を握っていたのが「コンテンツ(番組)」であることは言うまでもない(これは今日の「マルチメディア」論議でも繰り返されている言説である).しかし,ラジオという音声メディアしか扱っていなかった放送業界の内部には映像ソフトを供給する能力はなかった.ここで,当時も現在も映像ソフトの世界的供給センターとなっているハリウッドとのリンケージが必然的な流れとなる.既に,ハリウッドはラジオ放送やレコード業界を含めたマルチメディア産業の中で強力なコンテンツ・プロヴァイダーとして機能しており,初期のTV番組の殆どは映画フィルムによって供給された. 結果的に,TVの定時放送の開始は国家政策のもとで実用化を進めていたナチス・ドイツや英国に先を越された(両国とも1935年に放送開始している)ものの,合衆国のTVシステムは民間が主導しつつ,ラジオに準拠した商業放送システムとして着実に足元を固めていく(合衆国におけるTVの定時商業放送開始は1941年).そして,家庭においてTVは「小窓のついたラジオ」あるいは社会学者セセリア・ティチの言う「電子暖炉」としてリヴィングの一隅を占拠し,人々の視線を集束させていった.
第二次大戦後,TVメディアは合衆国を中心としたNTSC方式,欧州のPAL方式,東側諸国を中心としたSECAM方式と,異なる3つの技術規格のもとで社会化されていく.特に,NTSCは,パックス・アメリカーナのもとで,日本を含めた環太平洋地域の防共・民主主義を旗印に掲げる国家群に採用されることになり,民主主義のメディアとしての機能を果たしていく. また,1953年の英国エリザベス女王戴冠式と,59年の日本の皇太子結婚式という二つの儀礼がTV中継されたことは,旧来の(伝統)社会における祝祭や儀礼を利用しながら,その伝統を脱神話化し,大衆社会に浸透しようとするこのメディアにとって絶好の機会であった.60年代に入るとカラー放送が実用化するとともに,合衆国大統領ジョン・F・ケネディの暗殺を速報した衛星中継によって,世界に開かれた窓としてのTVの「再現性」「同時性」がますます補強されていくことになる. また,この時期に重要なことは,TVにまつわるテクノロジーが,資本の論理に基づく商業放送に対抗する表現手段としてアーティストたちに徐々に開放され始めたことであろう.1963年,ナムジュン・パイクがTV受像機の上に磁石を置き,画面に映しだされるTV映像を歪めるというインスタレーションを発表した時,マスメディアとしてのTVシステムをその外側から撹乱するビデオ・アートという新たな表現ジャンルが産声をあげた.1965年にソニーが初めて携帯型ビデオカメラ「ポータパック」を実用化すると,それを真っ先に使ったのもパイクであった.ポータパックのような技術成果は,ENG(Electronic News Gathering)と呼ばれTV報道の現場を変えるとともに,「ゲリラ・テレビジョン」などのようなオルタナティヴなメディア・アクティヴィズムの勃興をもたらすのである.
70年代から80年代にかけて,TVメディアの進化を規定した技術要因は大きくいって二つあるだろう.衛星利用の本格化と,TV受像機のシステム化だ.これによって,TVは他メディアや視聴者との関係性,あるいは世界とコミュニティに対する人々の認識を組み換えるようになる.
通信衛星を使った直接配信システム(いわゆる衛星放送)の実用化と,それによるグローバル・メッシュ化された放送ネットワーク,特にアトランタのニュース専門局という本来ならば周縁的な存在だったはずのCNN(Cable News Network)は,衛星インフラを獲得することでTV報道の「グローバリズム」を実現し,その“真価”は1991年の湾岸戦争勃発時の報道ではっきりと示された.
さらに衛星放送はその広域性という特性から国境をやすやすと越え,東側諸国のいわゆる「民主化」への動きを加速させた.東側諸国のTV普及率は60-80年代にかけて急激に高まるが,それは決して社会主義イデオロギーのプロパガンダとしては機能せず,西側からの衛星波のスピルオーヴァーを受信して市民による体制変革の一助となったことは皮肉な事実だろう.
さらに,TVセットは単機能の受像機から,他の電子メディア機器と接続可能な「端末」へと進化していく.1980年,ソニーがチューナー機能すら備えていないモニター型受像機「プロフィール」を商品化したことは,80年代を通じて急激に普及する家庭用VTRやゲーム機はもとより,後に「ニューメディア」と総称されるような機器をも含めたメディア・システムの構成要素の中に,TV受像機が埋め込まれていく状況を先取りしていた.これは同時に,視聴者にとって地上波のTV放送が唯一の映像メディアではなくなり,映像メディアの利用行動に変容を促す契機でもあった.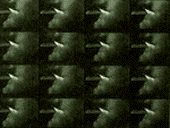 一方,マイナーメディアの実践も新たな展開を迎える.合衆国のケーブルTVでは一般市民やアーティスト,マイノリティの集団に無料で放送時間枠を開放する「パブリック・アクセス」が制度化され,商業放送というシステム内に異質な映像表現が流通し始める.
とりわけ,ニューヨークの「ペーパータイガーTV」は80年代に入り衛星を用いてオルタナティヴな映像表現者をネットワークするプロジェクト「DeepDish TV」を開始,湾岸戦争時にはCNN的な均質な映像で世界を包み込もうとする戦略に対抗した.
一方,マイナーメディアの実践も新たな展開を迎える.合衆国のケーブルTVでは一般市民やアーティスト,マイノリティの集団に無料で放送時間枠を開放する「パブリック・アクセス」が制度化され,商業放送というシステム内に異質な映像表現が流通し始める.
とりわけ,ニューヨークの「ペーパータイガーTV」は80年代に入り衛星を用いてオルタナティヴな映像表現者をネットワークするプロジェクト「DeepDish TV」を開始,湾岸戦争時にはCNN的な均質な映像で世界を包み込もうとする戦略に対抗した.
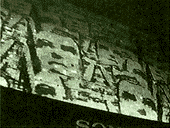 また,ブロードキャストTVにとって日常的な手段となった衛星中継を使ったパイクの一連のプロジェクト(「バイバイ・キップリング」「グッドモーニング,ミスター・オーウェル」など)や,ユビキタス(遍在)化するTV環境をハッキングする『TV WAR』(浅田彰/坂本龍一/ラディカルTV)といった試みがTVというメディアが成立している構造に揺さぶりをかけた.ここに来て,もはや巨大なマスメディアか,マイナーメディアかという二項対立は意味を失っていく.産業的なマスメディアがマイナーメディアを取り込み,あるいはマイナーメディアがマスメディアをハッキングする両義反転が繰り返されていくことになる.
また,ブロードキャストTVにとって日常的な手段となった衛星中継を使ったパイクの一連のプロジェクト(「バイバイ・キップリング」「グッドモーニング,ミスター・オーウェル」など)や,ユビキタス(遍在)化するTV環境をハッキングする『TV WAR』(浅田彰/坂本龍一/ラディカルTV)といった試みがTVというメディアが成立している構造に揺さぶりをかけた.ここに来て,もはや巨大なマスメディアか,マイナーメディアかという二項対立は意味を失っていく.産業的なマスメディアがマイナーメディアを取り込み,あるいはマイナーメディアがマスメディアをハッキングする両義反転が繰り返されていくことになる.
そして,TVメディアは再び,テクノロジー的な混沌状態の只中にある.デジタル・テクノロジー.確かにそれは,80年代から放送制作の現場に少しずつ浸透し始めていたが,今日顕著となったデジタル化に伴うTVの変容は,TVというメディアの内部における,映像の高精細化や制作の効率化,ダウンサイジングなどといった文脈に留まらず,TVメディアがこの半世紀間自明のものとしていた存立構造までも揺るがすインパクトを持っている.HDTV(High-Definition TV)にしても,それは70年代から構想されてきた高精細化=TVの内側の変化というだけではなく,デジタル化による他メディアとの融合の可能性=TVをめぐるコンテクストの変化として考えられるべきなのだ(その意味で,ハイビジョンはせいぜいが白黒からカラーへの変化程度のインパクトしか有していない). 90年に合衆国のカリフォルニア州オレンジ郡で開局した24時間ニュース専門局「OCN(Orange County Newschannel)」をはじめとして,「スモール・フォーマット」と呼ばれるデジタルTV局はローカルニュース局を中心に世界各地で続々と開局している(95年11月開局予定の「東京メトロポリタンテレビ」もその一つだ).それらの新たなTV局はHi-8ビデオカメラとマッキントッシュなどのパーソナル・コンピュータを核としたノンリニア/テープレスのデジタル制作システムを導入し,[★2],放送現場のダウンサイジングに留まらず,地上波からケーブル,インターネット,衛星など多様な伝送媒体を状況に応じて自在に選択し,ローカルからグローバルへと直接リンクする新しい映像チャネルを開拓しようとしている. 制作体制のみならず伝達インフラにおいてもデジタル・テクノロジーはTVメディアの存立基盤を揺るがせている.郵政省による電波行政のもとで既得権益と化している地上波アナログ伝送のアドヴァンテージは,衛星のデジタル伝送や光ファイバーといった通信インフラの整備が着々と進むに伴い,今や逆に放送ビジネスにとっての足枷にすらなり始め,伝送手段を持たないコンテンツ・プロヴァイダーまでもが自ら放送局化しうる可能性が出てきた.インターネットのマルチキャストやWWWを使ったサイバーキャスティングが放送の将来に与える影響については,今さら指摘するまでもないだろう.
デジタル・テクノロジーの急速な社会化が,TVメディアを内と外から大きく変えようとしていることはもはや否定しようがない.しかしながら,おそらく,TVの持っていたブロードキャスト性は今後も別のデジタル・メディアに受け継がれていくに違いない.マクルーハンが指摘するように,新しいメディアは常に旧いメディアの社会的存在様態を模倣し,コンテンツ化していく. 実際,インターネットでのWWWの急激な拡張を見る限り,数万もの超多チャンネル化したサイバーキャスティングTVをネットサーフするという,現在のTV視聴の構造と表面上は変わりのない状況が現われつつあるように思える.無論,そこにはマイナーな,オルタナティヴな実践の担い手が,既存のデジタル・インフラを自在に利用してメッセージを発信する可能性が開かれていることは否定できないだろう.とはいえ,ネットカルチャーにおけるエンターテインメント指向の高まりと,広告媒体としての利用増大は,マスメディア的なパラダイムを延命させ,情報を律儀に「能動的消費」する個人の端末市民化という方向に作用するだけではないか.と同時に,オルタナティヴで周縁的なメディア実践が,「マスメディア予備軍」としてブロードキャスト型の構造に回収されていく可能性も未だ拭い去ることはできない. おそらく,TVがその次世紀へ向けて「メディアサウルス」として滅び去るのではなく,新たな種へと進化する可能性が残されているとすれば,浅田彰が1986年に既に指摘していたように,TV局があたかも電話交換局のような中継点として,(様々な社会的文脈に属する個々人が発信する)多様な知を媒介/編集する場としてリ=デザインされる方向をこそ模索していくべきだろう[★3].それは産業的なブロードキャストTVに留まらず,オルタナティヴ・メディアの実践にとっても重要なポイントである.粉川哲夫が言うように,メジャー/マイナーの二項対立が無意味なものとなり,オルタナティヴという概念そのものの問い直しが迫られている現在,変革(alter)のインパクトを周りに拡げていくための拠点(native)をどのように設定していくのか.もはや,旧来のエスニシティや地縁的なコミュニティが立脚点として成立しえないとすれば,常に変容が繰り返されるメディア・スペースをその場その場で共有しつつ,人々の関係性を組み換えていく場を創出していく新たな戦略が浮上してくるだろう[★4]. 文化的多元性にみちた社会の情報編集ノードとしてTVメディアが生まれ変わる日へ.ブロードキャストからインターミディエートへの方向転換を志向しなければならない.
 原註
原註
★1――本稿の執筆に際しては,高柳記念電子科学技術振興財団顧問・松山喜八郎氏,東京経済大学教授・粉川哲夫氏,東京大学社会情報研究所助教授・水越伸氏,NHKエンタープライズ21メディア開発本部担当部長斉藤伸久氏,NHKソフト開発部ディレクター・窪田栄一氏の意見や提供くださった情報を参考にさせて頂いた.ここに改めて謝意を表したい.
(わたなべ やすし・メディア論)
★2――また,Mac以前に既にビデオの入出力機能を備えていたコモドールのAMIGAと,それをプラットフォームとする映像編集システムVideoToasterは,自身のビデオクリップを制作するミュージシャンから第三世界の自由テレビ局,街のテクノキッズに至るまでに共通する強力な武器となった.
★3――以下は1986年9月,フジテレビの深夜2時から4時間半にわたって放送された『TVEV BROADCAST』の終盤での浅田彰の発言.「そもそもいまのような巨大なマスメディアがこれからも必要なのか? それは,平均的大衆という虚像に向けて浅く広く同質的な情報を投げ与える送り手であることをやめ,むしろ異質な声の呼び交わす分散的なメディア網の局所的中継点へと,発展的に解消されていくべきなのではないか? そのために,多様なマイナー・メディアの実験が必要とされていることはいうまでもない.しかしまた,そう,たとえばTV局が,もっとも完全なエレクトロニック・メディアである電話網の交換台のようになる日を夢見ることもできます.電話網の中では,ある瞬間にビジネスの話がなされているかと思うと,愛が語られたり,冗談が交わされたり,また同時に,極めてハードな科学の情報や哲学の議論が交換されていたりもする――その傍らをデジタル化された情報がパルスの列となって走り抜けていくという具合です」.
★4――あるいは,「インターネット・カフェ」と呼ばれる情報空間と物理空間の交差点は,そうしたオルタナティヴな実践を保証する場としてリ=デザインされうる可能性を秘めているだろうか? 本誌前号の上野俊哉による論考「インターネット時代の公共圏」を参照のこと.
渡辺保史 e-mail:HGA00404@niftyserve.or.jp/yas-w@po.iijnet.or.jp
| No.14 総目次 |
Internet Edition 総目次 |
| Magazines & Books Page | |