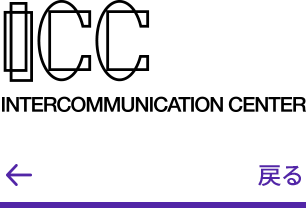|

|

|
| はじめに |

|
ロボットという言葉はチェコの作家,カレル・チャペックが初めて使用した造語です.この言
葉が作られて以来,欧米では,ロボットは人間に似た形態をもち,人間の労働力の代替をなす ものとして認識されてきました.また,ロボットは自分の意思をもたず,他の何かに支配され
て動く存在としても位置付けられています.このような考えに立てば,重要なことは人の命令 を従順に受け止めて,いかに効率的に単純作業をこなしていくかということになります.これ
によって,産業革命後の大量生産/大量消費の豊かな社会が実現することになりますが,働く 側からみれば創意工夫の余地は少なくなり,ロボットの存在が人間を疎外するものであるとも
言われてきたことも当然と言えるでしょう.
しかしながら,今日のロボット工学においては単純にそれだけでは説明できない状況が生まれ ています.ロボットの必要な機能としては「センサー機能」「動作機能」「AI機能」がありま
すが,これをスムーズに行なうには人間からの情報伝達をいかに行なうかといった問題だけで はなく,ロボット自体が人間の行動のパターンを「知覚」「判断」し,「人工知能」によって
人の望む行動を行なうことが求められるようになっています.
今回の展覧会は,これをさらに進めて,人からの一方通行に留まらず,人間とロボットの相互 交流(=インターコミュニケーション)を前提にロボットを考える機会であると位置付けてい
ます.
日本ではアニメーションの世界に象徴されるように,ロボットは言葉を交わしたり子供の夢を かなえたりすることができる,意思と感情をもった隣人として身近に感じられてきました.そ
こではロボットは人間と対峙するものといった意識はなく,人と同じ目線をもった友達のよう に捉えられています.今回,これらの前提をも踏まえながら,ロボットの創世から今日までを
歴史/文化/芸術の側面から概観し,展示/シンポジウム/ワークショップの一連の活動を通 じて,進化した新しいロボットのイメージを考えていきます.そして,人間とロボットの共生
により実現する21世紀の新しい社会の一端にふれることができればと思っています.
|
|