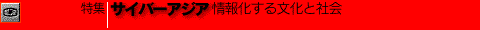
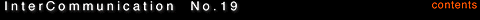
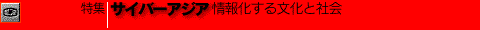


■■「メガ・トレンド・アジア」の潜在的な創造力
伊藤――きょうは「アジアにおけるテクノロジーと文化の変容」というテーマで話をしてみたいと思います.ただ,テーマがかなり広くてやや漠然としているので,いくつかの具体的な視点を僕のほうから用意したいと思います.まず最初に,現在,インターネットを始めとするさまざまな情報通信技術がアジアの国々に浸透してゆこうとしています.考えてみたいのは,この情報テクノロジーの浸透が,アジアのイマジネーションとどう結び付いてゆくのかということです.言い換えると,インターネットという均質な情報空間と,特異な「場の力」を持つアジアがどうショートしていくのかということが,これからのアジアの文化的な変容を考えるうえで一つのポイントになると思います.あるレヴェルではそうした画一的な情報システムが,場の特殊性を破壊し,均質なものが循環する回路を作りあげようとしている.また別のレヴェルでは,場の持つ潜在力を生かして,情報通信技術を自分たちのデリケートな感覚や知覚にあうように作り変えてゆくような試みも行なわれつつある.そこでは暴力的な性格を持つネットワークをセンシティヴで,流動的なネットワークに作り変えてゆくアジア的なテクノロジーが重視されているとも言えます.
![]() ジョン・ネズビッツという未来予測学者が『メガトレンド・アジア』(早川書房)という本のなかで,いままでのアジアは文化,言語,政治的イデオロギー,宗教,地理などによって区分されていたけれど,新しいアジアは経済的な統合や,特にテレコム・ネットのようなテクノロジーによって,ある共通したスフィアを形成していくのではないかと述べている.非常にアメリカ的なものの見方ですが,とりあえず,こうした側面から,ネットワーク・テクノロジーとかメディア・テクノロジーといったものが,アジアという現場に実際にかぶさってきたときにどうなっていくのか,ここから話を始めたいと思うのですが.
ジョン・ネズビッツという未来予測学者が『メガトレンド・アジア』(早川書房)という本のなかで,いままでのアジアは文化,言語,政治的イデオロギー,宗教,地理などによって区分されていたけれど,新しいアジアは経済的な統合や,特にテレコム・ネットのようなテクノロジーによって,ある共通したスフィアを形成していくのではないかと述べている.非常にアメリカ的なものの見方ですが,とりあえず,こうした側面から,ネットワーク・テクノロジーとかメディア・テクノロジーといったものが,アジアという現場に実際にかぶさってきたときにどうなっていくのか,ここから話を始めたいと思うのですが.
中沢――僕は宗教学をやっているのでキリスト教の話をしますが,その歴史を見ていくと,メディアの問題とかテクノロジーの問題と関連して,政治とは別のかたちで「アジア」が出てくる時期があるんです.もともとキリスト教は,パレスチナというアジアの地で発生した宗教で,最初の頃,それを思想的に発達させた人たちはみんなアジア人だったわけです.ところがローマを中心とするヨーロッパの人びとと合わなくなって,分裂を起こす.ローマの人たちが,自分は西の人間であり,東の人間とは思考方法が違うと認識しはじめる時期があります.それはだいたい中世ぐらいです.ローマの人たちはキリスト教の神を理解するのに非常に合理的にやりたがるわけですが,アジアの人たちは神を非常に不条理なまま理解しようとしたんですね.それが一番はっきりわかるのは,三位一体論です.もともと神というのは存在について語っているのですが,この世界が存在しているということについて語るだけではなくて,ハイデガー流に言うと「転回」あるいは「ターニング・ラウンド」しながら,別の位相にあるものがつねに位相転換を起こしながらこの世界があるというのがアジアの考え方です.言い換えると垂直性の場のことをいつも考えているというわけです.
他方,西の考え方はトランスフォーメーション,つまり情報なり価値なりのできあがったものがかたちを変えて――トランスフォームして――データ化したり輸送したりしていくという考え方だと思うんです.神とはいったい何だと言ったとき,ローマの考え方は抽象的な情報場みたいなものを想定しているわけですね.情報はすでに可視なものとしてあり,それを分配したり伝達したりしていくもの,あるいはそのシステム全体を含めて「神」と呼んでいるわけです.それがアジアとヨーロッパを分ける最初の分水嶺になるようで,僕はこの分裂がいまのテクノロジーやメディアの問題にかなり関係していると思います.
なぜ,最初に西ヨーロッパでテクノロジーが発達したのかというと,そのベースを作っているのは,ローマ人たちがアジアを切り捨てていくことによって,ある種の合理的な思考方法を可能にしたからだと思います.なぜ,アジアは科学的思考でも技術的思考でも大変高度な発達を遂げながら,それを現在あるテクノロジーのように組織化できなかったのか,しなかったのか.その理由はそういう深い問題に根ざしているような気がするんです.そして,知的能力ではアジアもヨーロッパもそんなに違いはないにもかかわらず,東と西の方向性を微妙に分ける事態が千年近く続いてしまったというわけですね.
もちろん,伊藤さんが言ったように,いま,ヨーロッパ経由のテクノロジーの発達がアジアに接続されて,それがアジアの技術発展を刺激して新しい物を生み出しつつあるという状況があるけれど,それは,西と東の分裂という事態が解消しつつあるということなのだと思います.にもかかわらず,ヨーロッパが発達したときの技術の思想の方向と,いま,アジア人たちが,ヨーロッパの発達から刺激を受けて自分たちのテクノロジー的な社会文化を形成しようとしている運動の方向には,まだ何か違いが存在していると思う.その違いは場の力というよりも,もっと抽象的な原理がそこで何か働いているんじゃないかと考えています.
武邑――ネズビッツの本は僕も読みましたが,インターネットはアジアをネズビッツ的な視点で切り取りやすくしてしまうんですね.たしかに表層的には統合化であり,「共通したスフィアを形成」する環境ができあがるにしても,もっと別の磁場を動かすというか,逆にアジアにおけるインターネットはそういうものを増大させる装置になると思うんです.デジタル化された情報テクノロジーによってあらゆるものがフラットで均質なシステムになり,文化や政治や伝統にしてもフラットな状況を作り出しているというのは,僕の考えでは,ユビキュタス・コンピューティングという言葉の内実に近いものだと思います.「ユビキュタス」というのはまさに神学用語で,神が遍在して世界に宿るということですね.つまり場という概念を一度棚上げして,あらゆる地球上の皮膜全体に神が遍在して存在する.われわれは空間の移動や,近代的な交通概念のなかから出てくる利便性というかたちでユビキュタスということを考えたりするんだけれど,じつはそこで提起されている問題はまったく別なレイヤーにあるわけです.
![]() つぎに,ある意味では情報化も体験化も難しかったアジアの場というものが,いかにコンピュータ・ネットワークと共振しうるのかという問いを伊藤さんは立てられましたが,一方ではインターネットなどのコンピュータ・ネットワークによる世界の情報の一元化を,情報の発展主義として批判的に考える傾向も出てきているんです.たとえば,インターネットに一種のデジタル・コンテントとしてアジアの国々のそれぞれの文化的情報を提示していこうとするとき,その提示の仕方はあまりにもフラットです.これがある意味ではユビキュタスのすごく大きな影響力なんです.つまり新しいサイバースペースのなかに,自らの文化的なアイデンティティを提示しなければならない,というオブセッションを含み込んで存在しているのがインターネットの現状だと思うんです.日本の状況はどうかといえば,この2年間で日本のインターネットのアクセス数は一挙にアジアで1位になった.ところが,本当の意味でのコネクテッドなインテリジェンスやセンシビリティというものは日本のなかではほとんど見られないんですよ.僕は台湾のMTV ASIAを見たとき,かつて初めてヨーロッパやアメリカのMTVを見たときよりも数倍のショックを受けたんです.そのなかに出てきている独自の言語は,映像的にも音的にも,僕らが数年来感じとっていたアジアではまったくなかったわけです.その新しいアジアがどういうルーツから来ているのか,あるいはどういう変換によって生じているものなのかということが,いま,僕にとって一番興味があることです.と同時に,僕はいまサイバースペースのなかで起きている無意識的,官能的な一種の共感概念みたいなものは,案外,アジアという原理あるいはアジアの原質と向かい合う大きな手段になるのではないかと思うんです.
つぎに,ある意味では情報化も体験化も難しかったアジアの場というものが,いかにコンピュータ・ネットワークと共振しうるのかという問いを伊藤さんは立てられましたが,一方ではインターネットなどのコンピュータ・ネットワークによる世界の情報の一元化を,情報の発展主義として批判的に考える傾向も出てきているんです.たとえば,インターネットに一種のデジタル・コンテントとしてアジアの国々のそれぞれの文化的情報を提示していこうとするとき,その提示の仕方はあまりにもフラットです.これがある意味ではユビキュタスのすごく大きな影響力なんです.つまり新しいサイバースペースのなかに,自らの文化的なアイデンティティを提示しなければならない,というオブセッションを含み込んで存在しているのがインターネットの現状だと思うんです.日本の状況はどうかといえば,この2年間で日本のインターネットのアクセス数は一挙にアジアで1位になった.ところが,本当の意味でのコネクテッドなインテリジェンスやセンシビリティというものは日本のなかではほとんど見られないんですよ.僕は台湾のMTV ASIAを見たとき,かつて初めてヨーロッパやアメリカのMTVを見たときよりも数倍のショックを受けたんです.そのなかに出てきている独自の言語は,映像的にも音的にも,僕らが数年来感じとっていたアジアではまったくなかったわけです.その新しいアジアがどういうルーツから来ているのか,あるいはどういう変換によって生じているものなのかということが,いま,僕にとって一番興味があることです.と同時に,僕はいまサイバースペースのなかで起きている無意識的,官能的な一種の共感概念みたいなものは,案外,アジアという原理あるいはアジアの原質と向かい合う大きな手段になるのではないかと思うんです.
■■最初のサイバースペースとしての漢字
中沢――コンピュータの原理そのものがアジアの思考方法から生まれたということは,ライプニッツの時代からはっきりしていることですね.中国人の思考方法のなかに,現代のデジタル・コンピュータの原型があります.それから,もう一つ重要なのは漢字の問題ですね.サイバースペースを人類で最初に作ったのは漢字だという気がするんです.ヴェトナムであっても,タイ,南中国,朝鮮,日本であっても,みんな漢字を使用します.それでその漢字にそれぞれ固有の音を当てたわけですね.僕らが漢字を目にするときに,ある共通の意味場にいったん降りて,それから自分の民族的独自性を持つパロール,音の場に戻ってくるという往復運動をします
これは万葉集を見るとよくわかりますが,かつての日本語の原型は非常にたらたらと喋ったりしていて時間軸が延びていくわけです.ところがそこに漢字が入ってくると言葉は空間性のなかに一気に凝縮され視覚化されてくる.しかも当時の日本人は漢字がアジアの共通文字として使われていて,それぞれ別の音で発音されるということ,たとえば中国の南ではこのように,北ではこのように発音するということをよく知っていたんですね.漢字には空間を一気に凝縮するという働きがあるし,同時に,意味のサイバースペースを開く力を持っていたんだと思います.アジアの文明が持っている潜在的な創造力はそんなところにあって,現在のメディア・テクノロジーが作り出そうとしているものの原型は,ひょっとするとアジア原産かもしれないなという感じを受けていますが,どうでしょう.
武邑――日本の資源というのは,正倉院以後,言ってみれば日本人自らによるジャパネスクだと思うんですね.奈良の斑鳩宮のような外来的な巨大な伽藍から自己解体して,日本というアイデンティティを再編成,再編集しようとした力学が平安京だったとすると,ひらがな,いわゆる日本仮名と能と雅楽という,日本独自のリズムを取り出していく再編集のプロセスは,じつはいま,僕らがサイバースペースでアジアの原理をどう発動できるか,あるいはそういったドメインとは何なのか,を考えていく作業と非常に近いような気がします.たとえば平安京創成というプロジェクト自体がそうだったわけです
![]() いま,巷のグラフィックではカタカナに非常に元気がありますが,たとえば,デザイナーズ・リパブリックなど,イギリスの若手の,アンビエントとかテクノのデザイナーは,日本のコミックスや広告、そして任天堂やセガのゲームのデザインに影響を受けた世代なんです.ヴィデオ・ゲームのなかに出てきた,当時の8ビットから16ビット時代の文字というのはカタカナなんですね.それらを見て育った彼らが,僕らが昔,子供の頃に,読めないけれど英語はカッコいいと考えていたようなニュアンスで日本語のカタカナを見ているんです.カタカナは一種の表音文字ですから,彼らもそれを読むことができるんです.そして何か非常に抽象的なデザインの核にカタカナをすえて,何の意味伝達も機能化させないけれども,カタカナというスタイルそのものにある種のシンボリズムを与えているわけです.それを日本のデザイナーが受け取って,「カタカナってすごいかっこいいじゃない」という(笑),カタカナのデザイン・レヴォリューションみたいなものが起きているんですね.こういう往復運動は,多分実際のネットワークにはなかったし,想像しなかったんだと思うんです.
いま,巷のグラフィックではカタカナに非常に元気がありますが,たとえば,デザイナーズ・リパブリックなど,イギリスの若手の,アンビエントとかテクノのデザイナーは,日本のコミックスや広告、そして任天堂やセガのゲームのデザインに影響を受けた世代なんです.ヴィデオ・ゲームのなかに出てきた,当時の8ビットから16ビット時代の文字というのはカタカナなんですね.それらを見て育った彼らが,僕らが昔,子供の頃に,読めないけれど英語はカッコいいと考えていたようなニュアンスで日本語のカタカナを見ているんです.カタカナは一種の表音文字ですから,彼らもそれを読むことができるんです.そして何か非常に抽象的なデザインの核にカタカナをすえて,何の意味伝達も機能化させないけれども,カタカナというスタイルそのものにある種のシンボリズムを与えているわけです.それを日本のデザイナーが受け取って,「カタカナってすごいかっこいいじゃない」という(笑),カタカナのデザイン・レヴォリューションみたいなものが起きているんですね.こういう往復運動は,多分実際のネットワークにはなかったし,想像しなかったんだと思うんです.
あるいは,槙原敬之が出したCDアルバム『デジタル・カウボーイ』にしても,ジャケットをウィルという日本のデジタル・グラフィックスのプロダクションが作っていて,一見すると,デジタル・デジタルしてるけれど,中身が全然違う.日本人にとって洋楽とは何なのかといって,かつてのカーペンターズのような心地よい洋楽を自分で作曲して英語で歌っているんですが,いわゆるベスト10みたいに,自分の欲しい洋楽は気持ちのいいものだといって作っている.それを自分ではテリヤキチキンバーガーと呼んでいるんです.そういう何か強力なデプロイメントを意識してできる人間がかなり出てきているんですね.これはけっして「アジア」とか「日本」とかいうアイデンティティとも違う,デジタル上の浮遊した場というかドメインのなかから出てきた編集の技術だと思います.
伊藤――テクノロジーという言葉をどう解釈するのか考えてみたいのですが,中沢さんは独特のテクノロジーに対する考え方を持っていますよね.人間の技術とは,自然のなかから,自然がやっていることよりも異常な力を引っぱり出してきたものであるという…….
中沢――ハイデガーですね.
伊藤――だから技術にはそういうデモーニッシュなところがあり,西洋のテクノロジーはそうした反コスモス的な本性を抱え持っていて,それはすごく自己暴走しやすい.けれども,アジアのテクノロジーにはそういうデモーニッシュなものとさまざまなレヴェルで,つねに何らかの折り合いを付けていくようなシステムがあるんじゃないか.つまり,アジアのテクノロジーは,エコロジー的発想のような調和的な方向ではなく,怪物性や狂気とつねに新しいかたちで折り合えるような何らかの方法を獲得していて,それが,西洋的なテクノロジーの行きづまりとともに,21世紀のテクノロジーの知恵へとつながっていく何かを秘めている――というのが中沢さんの視点だったと思うんですね.
中沢――そうですね.ヨーロッパの技術は終末論と結び付いている非常に特殊な技術だと思うんです.旧約聖書にもいっぱいそういうシーンが出てくるんですけど,神の出現というのは,ソドムとゴモラを見てもわかるようにその町を全部破壊する.それから『レイダース・失われた聖櫃』のように,聖櫃のふたが開けられたとたんに世界に大変なエネルギーが放出されてしまって,あたりが廃虚と化していく.おそらくアインシュタインが,自分が作ったエネルギー変換の方程式から原子爆弾が作られたということを聞いたときに持った印象は,こうした神学的な印象に近かったと思うんです.ヨーロッパのユダヤ・キリスト教のベースのなかには,いつも世界を終末の地点から見ていく視点があると思います.終末の地点とは何かというと,これはエネルギーでいうと核融合反応に近いエネルギーの放出,つまり原子の構造を解体させることによってエネルギーを引き出すという方向です.文明全体としても,終末論的思考法と,技術が持っているデモーニッシュなものが合体したと思います.ただアジアの場合は,デモーニッシュなものがユダヤ・キリスト教的な終末論とは合体せずに発達を遂げた.そして原子の構造を解体したところに出てくるエネルギーを引き出すことに対して,いつもブレーキをかけるものがあったと思うんですが,それは何なのかということが問題になってきます.たとえば長い中国の歴史のなかで,終末論的な世界に突入したのは1980年代です.それまでは,全面的に原子の構造を解体してエネルギーを放出させてしまうことに対する抑止力が――それは官僚制度であったり,共産主義であったりしたわけですが――いつも働いていたわけです.ところがおそらく秦の始皇帝以来だと思いますけど(笑),初めてそれがはずれかかっている.これがどういう事態を作り出すのかが新しいアジア時代の一つの重要なポイントですね.
![]() 僕らが生きているのは東アジアの世界ですけれど,東アジアは黄河流域の大国家とその衛星国で形成されていたわけです.カンボジア,ミャンマー,チベット,韓国,台湾,日本もすべて衛星国として国家の概念を持ち,民族的アイデンティティを持ち,中国の古くからの冊封制度というかたちで東アジアの秩序を作ってきた.ところが19世紀から20世紀にかけて日本がその構図を変形しはじめ,中国は停滞期に入ってしまった.この間の日本と中国の関係は東アジアの歴史にとって,ジグザグ・コースの,一つの過渡的なものだと思うんです.それが1989年の天安門事件を境に解体し始める.そして中国は再びアジアの新しい中心地になってゆくでしょう.そのとき出てくるアジアというのは,かつての黄河流域に国家ができて,その周辺に衛星国がある,というのとは全然違うアジアではないかという気がします.
僕らが生きているのは東アジアの世界ですけれど,東アジアは黄河流域の大国家とその衛星国で形成されていたわけです.カンボジア,ミャンマー,チベット,韓国,台湾,日本もすべて衛星国として国家の概念を持ち,民族的アイデンティティを持ち,中国の古くからの冊封制度というかたちで東アジアの秩序を作ってきた.ところが19世紀から20世紀にかけて日本がその構図を変形しはじめ,中国は停滞期に入ってしまった.この間の日本と中国の関係は東アジアの歴史にとって,ジグザグ・コースの,一つの過渡的なものだと思うんです.それが1989年の天安門事件を境に解体し始める.そして中国は再びアジアの新しい中心地になってゆくでしょう.そのとき出てくるアジアというのは,かつての黄河流域に国家ができて,その周辺に衛星国がある,というのとは全然違うアジアではないかという気がします.
■■デリケートな技術とナチュラル・ウィズダム
伊藤――アジアのテクノロジーを考えるときに重要なのは,記憶のテクノロジーと,共同体のテクノロジーが結び付いていく問題があると思うんです.これにはいろいろな観点が考えられると思うんですけど,たとえば「ドラッグによる幻覚体験とサイバースペースの体験は,自己表現がコミュニティ全体の出来事になりうるような新しいノンリニアな現実を作り出していくだろう」というテレンス・マッケンナのような人たちの思考がありますよね.彼はもともと東洋への志向が強いんですけど,個人的な営為としてではなく,集合的な営為として,ドラッグもVR体験も成し遂げられてしまうという思考です.これは,あるユーザーがコンピュータ・ネットに書き加えた変更が全体的地図をどんどん書き換えていくような,レゾナンス(共鳴)状態という問題とも重なってくるし,前にルパート・シェルドレイクが言ったみたいな,モルフォジェネティック・フィールド・セオリー(形態形成場理論)という考え方とも重なります.つまり種とか集団とか族の過去の行動や体験を記憶する一種の集合記憶の領域にアクセスすることで,あるメンバーが他のメンバーの経験や知識を共有できるようなシステムが成り立ってきている.そういう記憶のテクノロジーと共同体のテクノロジーの結び付きによって,通常のコミュニケーションでは考えられないような情報の伝播が連鎖的に起きる状況が,現実問題として出てきていると思います.それは,ある意味でアジア的な共同性の問題であり記憶の問題と結び付いているように思えて,いま,話に出た漢字の問題もそういうかたちで考えられるような気がするんですが.
以前,中沢さんがジョン・ハッセルと対談したとき(『ミュージック・トゥデイ』No.3,1988)にも,エレクトロニック・メディアが作りだす環境を生きる部族的方法について触れていて,そうした均質な情報環境のなかで,もういちど同質性と差異性を巧みに組み合わせて互いのバランスを作りだすことの重要性に言及していましたね.そういう西洋的なテクノロジーではない,デリケートな技術のあり方,それはあの時点でも有効性を持っていたわけですけど,いま,より身近な現実の問題として浮かび上がっていると思うんです.
中沢――テレンス・マッケンナの思考方法を見たり,アメリカでチベット仏教がものすごいブームになっていたり,アメリカ・インディアンの世界観の影響が強くなってきているのを見ると,これは意外なようだけれど,やはり「歴史の終焉」だとかベルリンの壁崩壊に象徴される,一連の出来事にリンケージしている現象だと思います.チベット仏教がなぜアメリカ人の心をあんなにつかんでいるかといえば,チベット仏教は仏教ではあるけれども,最後に自らを解体しちゃう宗教でもあるんです.それでどこに出ていくかというと,いわゆるナチュラル・ウィズダムを目指すんです.アメリカ人が関心を持っているのは,このナチュラル・ウィズダムを一種のテクノロジーとして,組織的に共同体験として作れるというところですね.それからアメリカ・インディアンの文化に対する関心も一種のナチュラル・ウィズダムに関係しているんだと思います.両方とも何が共通点になっているかというと,国家の権力が介入しなかった状態の人間のウィズダム,知性の状態なんです.それは宗教以前,あるいは宗教以後なのかもしれません.あるいは宗教は国家と同時に誕生するものですから,国家以前,国家以後,あるいは歴史は国家と同伴していますから,歴史以前,歴史以後,といったものを具体的に提起しているものだと思うんです.伊藤さんもずっと関心を持ってこられた問題は,テクノロジーの運動というものと,ヨーロッパ的歴史の終焉がリンケージしていくところだと思います.ですからナチュラル・ウィズダムとが歴史以前と歴史以後の両方に出てくる,それを加速しているのがテクノロジーの問題で,アジアのなかで僕らがヨーロッパ人よりもよいポジションにいると思うのは,ナチュラル・ウィズダムの部分をキリスト教のように徹底的に破壊しなかった,破壊できていないというところだと思います.
![]() ヨーロッパの場合は,いったんそれを地ならしするように破壊したうえで,近代カトリックの歴史の構築物を作り,そして大体そのプログラムを出し切りましたよね.出し切ったところでいま,迎えはじめている変容の世界,あるいはアメリカ人のように,自分の足下にアメリカ・インディアンの世界があり,さらに東洋宗教に対する関心が60年代からあったのが,いま新しいかたちで展開して当時と同じものとは思えないほどになっている,という状況が微妙に共鳴していると思うんです.だから日本人やアジア人がナチュラル・ウィズダムに対して持っている関心と,アメリカ人が持っている関心は,出発点が少し違うんだと思います.
ヨーロッパの場合は,いったんそれを地ならしするように破壊したうえで,近代カトリックの歴史の構築物を作り,そして大体そのプログラムを出し切りましたよね.出し切ったところでいま,迎えはじめている変容の世界,あるいはアメリカ人のように,自分の足下にアメリカ・インディアンの世界があり,さらに東洋宗教に対する関心が60年代からあったのが,いま新しいかたちで展開して当時と同じものとは思えないほどになっている,という状況が微妙に共鳴していると思うんです.だから日本人やアジア人がナチュラル・ウィズダムに対して持っている関心と,アメリカ人が持っている関心は,出発点が少し違うんだと思います.
武邑――それは同感ですね.日本とアメリカ,あるいは日本と西欧の違いは,ヴァーチュアル・リアリティを見ていると明らかだと思いますね.これに関していつも思うのは,日本語で「ヴァーチュアル」を最初「仮想」と訳してしまったでしょう,あれは非常にまずかった.リアリティというのは唯一無二の物質的な根拠を持ったもので,ヴァーチュアルはコンピュータ上で生成されたたんなる架空の時空間――あるいは「仮想メモリ」――であるということなんでしょうが,安定的な現実感といったものを立体化させる基盤をヴァーチュアル・リアリティに求めてしまったこと自体が,この5年間の間にきわめて大きな温度差を西欧社会と日本との間に生み出したと思います.これをアジアというレヴェルにまで拡げると,日本は非常に特殊なVRの磁場を作り出してしまった.いまさらリアリティを「実質的な」「事実上の」現実といい,ヴァーチュアル・リアリティを「可能態としての」リアリティだと説明してみても,ゲームの場なんかではもう影響力がないですね.NINTENDO64のマリオは,ターミナル・アイデンティティの問題としてあと一歩のすれすれのところまで来てしまっていると思います.アメリカでは最近,シェリー・タークルがオルター・エゴやターミナル・アイデンティティなどの,ネットワーク社会のアイデンティティの危機的状況を社会心理学的な側面から分析した程度ですが,電子メディアとエゴとのアフォーダンスをめぐるアイデンティティの新しい変容について考えると,64のマリオはやはり新しい問題を提出しているわけです.なぜかというと,このゲームには2メートルほどの距離からマリオの一挙手一投足に随伴できるモードがあるんですが,このモードでは当初のゲーム性はどこかにいってしまって,まさに「実質的な現実」空間のなかをマリオと一緒に浮遊することになる.こうした現実――ヴァーチュアルな現実によって編集されり,再編されているという回路の加速状況――は,日本は圧倒的に進んでいます.「バーチャファイター」でも,IIでやっていた子がIIIではプレイできなくなったり,いろんな変化が起きていますが,あれはかなり中毒です.1日3−4時間平気でやって,1週間もやらないとアイデンティティを取り戻せないという子供たちがいたり,いつも付き合っているキャラクターがたまたま負けると,涙してゲームセンターから帰ってくるというように,これはすごいところに来ていますよ.
中沢――最近のしりあがり寿の『真夜中の弥次さん喜多さん』がすごいところに来ている作品だと僕は思っているんです.あれは喜多さんがジャンキーで,弥次さんとホモ同士で,伊勢へクスリ中毒から抜けるために旅をしているという設定ですが,喜多さんは完全にマリオ空間に入り込んでしまっている.僕は連載のはじめから非常に関心を持っていて,あれは現代の漫画家が弥次さん喜多さんを題材にしてやるからヴァーチュアル・リアリティとかドラッグのようなものがでてくるのかなと思って原作を読むと,原作もそうなんですよ.弥次喜多が浮遊感覚というか,サーファー状態なんです.もともと二人はホモで,その関係が現実生活をしなければならないために破綻し,そしてその現実生活もまた破綻して二人で伊勢に行く.その間やっていることは,当時はテクノロジーを使っていませんから,言葉です.どんな真面目なリアリティにも接触しないような言語を駆使していくわけですから,どこにも引っかからずに,波乗り状態なわけです.いわゆる「リアリティ」なるものに俺たちは金輪際触れないぞというものすごい決意のもとに伊勢に旅していくわけですね.そういう原作から,しりあがりさんがジャンキーとしての喜多さんを作ったわけですが,いま,武邑さんが言ったたみたいに,日本人は現実に触れずにサーフィンをしていく,中毒なんですよ,しかもその歴史が異様に長い.つまり今日昨日ヴィデオゲームが発明されたからいまの子供たちがこうなったというものじゃないんだ,ということが大事だと思うんですね.
伊藤――もともと日本とか日本人という存在自体,危うさの連続だった気がするんですね.日本は西洋でも東洋でもない,どこにも確たる芯のない,いたるところがインターフェイスだらけの特殊な世界のなかで,微妙なアイデンティティを作り上げてきたわけです.そのなかで,西洋的なテクノロジーが作り上げてきた世界とは違う関係を世界との間に作り出して,テクノロジーの持っている危険性と可能性を,生活文化のなかの隅々に埋め込んできた.日本はヨーロッパ型のテクノロジーでもアジア型のテクノロジーでもない,奇妙なテクノロジーを持ってしまったわけですね.この日本の作りだしてきたテクノロジーをどう評価し,どう生かしてゆけるのか,という問題がありますね.
![]() 武邑――かつてVRのパイオニアの一人だったジャロン・ラニアーは「サイバースペースは欲望のスポンジである」と言っていますが,そのスポンジ理論から,このスペースのなかで,もうひとつの新しい重力場を建設しようという動きのなかに入り込みつつあるというのが現在のインターネットの世界だと思います.これにはビル・ゲイツのいわゆるカウント理論とか,さまざまなレゾリューションと,それを重量化して計量化しようという動きがあります.僕が考えるのは,日本のアニメにしても,いま,中国や台湾や韓国が生産拠点で,アニメのセルを作る環境からすると,日本はほとんどハリウッドだということなんです.
武邑――かつてVRのパイオニアの一人だったジャロン・ラニアーは「サイバースペースは欲望のスポンジである」と言っていますが,そのスポンジ理論から,このスペースのなかで,もうひとつの新しい重力場を建設しようという動きのなかに入り込みつつあるというのが現在のインターネットの世界だと思います.これにはビル・ゲイツのいわゆるカウント理論とか,さまざまなレゾリューションと,それを重量化して計量化しようという動きがあります.僕が考えるのは,日本のアニメにしても,いま,中国や台湾や韓国が生産拠点で,アニメのセルを作る環境からすると,日本はほとんどハリウッドだということなんです.
本誌16号でアジアのハリウッドは可能かという話題があったときに,それは物語資源と,新しいアニメーションだったりCGだったり,フォーマットを全面変換したら可能だろう,映画というメディアとかコンテクストでは,それはちょっと難しいだろうという話がありました.そのとき,たとえば中国に眠っている膨大な物語資源だとか,ディズニーがかつて東欧から物語資源を抽出してワールド・コンテントに仕上げたような機能を,つい最近までアジアは日本に求めていたんです.しかし現在ではハリウッドが動き出して,中国の物語資源を回収しはじめている状態のなか,グローバリゼーションのなかでもう一度ハリウッドの持っている役割が大きくなるという感じですね.しかし『孫悟空』にしても,『となりのトトロ』だとか『風の谷のナウシカ』,あるいは最近ナムコが出した「プロップ・サイクル」というアーケード・ゲーム――これは自転車を漕いで空中を浮遊できるというゲームなんですが――だとか,それから『安寿と厨子王』にしても,中沢さんが言うように,僕らのほうが西洋よりもある種そういうものを通過してきているなと思います.浮遊感と反重力というと,70年代にはどちらにしても制度なるものを超えていくというかなり特化したヴェクトルだったけれども,単純な反重力,浮遊ということにおいてはアジアはものすごく大きい磁場を持っているなという感じがしました.
中沢――中国だと仙人が必ず存在していて,あれは地面と糸一本でつながっているだけなんですね.それでその一本の糸を切るかどうかが,アジアのテクノロジーの微妙な均衡点を支えていたものだったと思うんです.ヨーロッパのテクノロジーは,それを近代にいったん切ってしまったけれど,アジアでは切らなかった.
■■ヴァーチュアル空間のなかの調和点へ向かって
伊藤――今のテクノロジーの話とは少し違いますが,アジアのトランスやエクスタシーの技術が西欧的な世界のなかで求められているというか,そういうことを軸にしてサイバースペース的なものの軸も変わってきているような気がするんですが,どうでしょうか.不可視の領域と交流したり,人間のランダムな回路を同時に引き受けるような,アジアに根付いていた無意識的な技術,精神上の技術が,世界を動かす原動力になるということがはっきりしてきたというか…….例えばトランスというのも,それは意識の喪失というより,新しい意識の生成に関わるものなわけで…….
中沢――それは相当なせめぎ合いだと思います.僕の体験の範囲で言うと,先ほども言いましたように,アメリカですごくチベット仏教が流行っているのですが,アメリカ人がそれについて何を考えているかを見てみると,非常にいい線まではいっているけれども,アジア人から見ると違うんです.ナチュラル・ウィズダムにも関わってきますが,チベット仏教を最初にアメリカで英語に翻訳して定着させたのはほとんどユダヤ人なんです.優秀なユダヤ人の分析的言語でそれを作り替えて,翻訳作業をして,いまの隆盛のもとを作った.しかし,僕らアジア人がそれを勉強しに行くと,違う回路なんです.つまり,僕たちはユダヤ人的な変換回路を通過しないで直接的にそっちの世界に入ってしまうわけですよ.表面上は,僕はあのユダヤ人たちと対話できる,だけどこの人の考えていることは違うぞ,というのが痛いほどわかる.
![]() それは何かというと,本当に不思議なんですが,日本人の僕と,かつてのチベット人の思考方法は,空間も時間も,直接的に地下水みたいにつながることができるんです.しかし,いったんそういうものを全部チャラにしてまったく違う物質文明のパラダイスを作ったアメリカの人たちが,今度は精神文化の情報の重要な部分を吸収してセット・インしようとするわけですが,そのセット・インされているものは,直接性とは違う.いま,世界中で起きている現象は,表面的には同じだと思うんです.僕らが直感的に触れているヴァーチュアル空間のようなものと,アメリカのテクノロジー社会の何かを保存するために作られているものとは,向かい合っているんだと思いますね.日本人がそれを一番意識できる立場にいると思います.当のチベット人たちは,そのことに気がついていないんです.うれしがってどんどんアメリカに行って教えるわけです.でも,僕らから見ると,あんなことを教えてしまって,みんなうまい具合にディズニーみたいにセットされているわけで,止めればいいのにと思うようなことが進行している.だから,日本人が,言語の問題――何がここで起こっていて何が違うのかというようなことを意識し出すと,それは相当激しいせめぎ合いになっていって,次元を変えた異質なものの闘争が始まるかもしれないという予感がしますね.
それは何かというと,本当に不思議なんですが,日本人の僕と,かつてのチベット人の思考方法は,空間も時間も,直接的に地下水みたいにつながることができるんです.しかし,いったんそういうものを全部チャラにしてまったく違う物質文明のパラダイスを作ったアメリカの人たちが,今度は精神文化の情報の重要な部分を吸収してセット・インしようとするわけですが,そのセット・インされているものは,直接性とは違う.いま,世界中で起きている現象は,表面的には同じだと思うんです.僕らが直感的に触れているヴァーチュアル空間のようなものと,アメリカのテクノロジー社会の何かを保存するために作られているものとは,向かい合っているんだと思いますね.日本人がそれを一番意識できる立場にいると思います.当のチベット人たちは,そのことに気がついていないんです.うれしがってどんどんアメリカに行って教えるわけです.でも,僕らから見ると,あんなことを教えてしまって,みんなうまい具合にディズニーみたいにセットされているわけで,止めればいいのにと思うようなことが進行している.だから,日本人が,言語の問題――何がここで起こっていて何が違うのかというようなことを意識し出すと,それは相当激しいせめぎ合いになっていって,次元を変えた異質なものの闘争が始まるかもしれないという予感がしますね.
武邑――僕もすごくそれを感じます.それはたとえばエレクトロニック・シャーマニズムだとか,デジタル・トライバリズムなどの,非常に大きなトレンドといわれている単位のなかでも,ある種の一定の共感覚だとか,わりと小さな無数のフラグメンツとのかなり強力なパルスのような振幅運動のなかで,このサイバースペースというのは動いていると思うんですよ.エクスタシーやトランス,あるいはサイケデリックの問題も,非常に経験的なある種の表層というか,とりあえずナチュラルな現代的な問題を含み込んだものだと思います.アメリカの巨大なテーマパーク状にセットされているダンジョンのキャラクターだったり,そういうものとしてあるエクスタシーやサイケデリックのアトモスフィアが,案外本当の磁場かもしれないという気もします.テレンス・マッケンナもそのことだけは意識していて,たとえばタイムウェヴ・ゼロといって,2012年にとりあえず歴史の終焉が起き,それをC言語でプログラミングして,いろいろなものに応用しようということをやっているわけです.だけどこれをやっていても,動かないもの,変化しないもの,あるいはモルフィック・レゾナンスじゃないけれど,一定量変わるモードと変わらないモードがあるというレイヤーが,中沢さんが言っていたことと関係するような気がします.
中沢――最初に伊藤さんが言っていたように,インターネット的世界,つまり均質化が進行していることと,場の特殊性の問題は,そういうところに来ているんじゃないかと思います.それを極限ぎりぎりまで問いつめていって,何がいったいアジアと西欧の違いなのか見極める作業を僕はしていきたいですね.
武邑――現在の画像生成世界の環境を見ていると,CGとかサイバースペースの画像生成と,70年代的なサイケデリックとの関わりは明らかに違うんです.デジタル技術によってサイケデリック体験のリプレゼンテーションの解像度が飛躍的に向上したことや,その体験そのもののセンスウェア化に拍車がかかってきたことは事実です.ソフトウェアの開発にしても,さまざまな画像をフィルター処理するプログラマーは,身体的なメディアを通してソフトを作っていると言っても過言ではない.このことを逆に言うと,身体性あるいは知覚性みたいなものを通過したソフトウェアの生産が,かなりあるということになるわけです.
伊藤――そういう往還というか統合の仕方によって,ある意味で新しいものを作り出そうとしているんでしょうか.
武邑――そうだと思いたいですね.
伊藤――それはすごく包括的,全体的,ホリスティックな何かを回収しようとしているのでしょうか.
中沢――先ほどの,日本人が「仮想現実」と訳したヴァーチュアル・リアリティの問題なんですけれども,このヴァーチュアル空間というものが相当重要な働きをしてくると思いますけど,まだその可能性の入り口に差しかかっただけのような気がしています.電話が発明されたときにみんなが感じた問題は,このヴァーチュアル空間の問題とよく似ていますよね.いま,ゲームやCGを通じた体験を語っている言語は,電話が発明された頃にテレコミュニケーションに関して語られていたことと,それほどレヴェルが変わらないわけですよ.だから,今後それを突破していくものについては,電話に対して言われていたこと以上には,ある点までしか言えないわけです.そこを超えないと,伊藤さんの言ったものは出現しないと思うんですけれど,僕には何が人間にストッパーをかけて先に進めなくしているのか,よくわからないですね.
![]() 伊藤――人間は,自分と世界の間を埋めるためのさまざまな技術をずっと持っていたはずですよね.それが僕らの時代に硬直したというか,亀裂を埋める技術を衰弱させてしまっていると思うんです.
伊藤――人間は,自分と世界の間を埋めるためのさまざまな技術をずっと持っていたはずですよね.それが僕らの時代に硬直したというか,亀裂を埋める技術を衰弱させてしまっていると思うんです.
中沢――それは近代というものが,その技術を軽蔑したからでしょう.調和とか全体的思考法を軽蔑するところにしか,モダニズムの推進力はなかったですからね.ですから,どの芸術や技術の分野を見ても,調和ということが主題になったことはここ150年位なかったんじゃないかと思います.伊藤さんの言っていることは,極言すると調和という問題になってくるんじゃないですか.調和のレヴェルをどこに発見していくか.そして,そのような調和点がヴァーチュアル空間のなかに見出されうるだろう,という予感まではきていますね.
伊藤――それは多分,広い意味でのイメージの技術の問題で,いま,サイバースペースのなかで起ころうとしているのは,そのような技術をどうやって新しいかたちで出していくかということだと思います.サイバースペースのなかで一種の流体的な電子の建物をどうデザインするかというか,本質的に非物質的なものをどう可視化してゆくかとか.かつての共同体や集団においては,思考よりも,イリュージョンというか,私にはイメージが見えるという体験のほうが,はるかに強い信頼に足る道しるべとして機能していた時代があったわけです.たとえば先ほどの漢字のように,そういうイメージの技術をすごく洗練させて,われわれの生活に活かしてきたようなものを,サイバースペースのなかでもう一回作り直そうとしているような気がするんです.
中沢――構造主義は――レヴィ=ストロースがそういう人ですが,もともとシュルレアリスムから発生していますね.シュルレアリストのマックス・エルンストが言うところの「イメージが生成する中間の空間」は,一種のヴァーチュアル空間なんです.そしてレヴィ=ストロースが言っている「構造」はそこにしかないものです.彼は,そこにある種の秩序を発見しようとしています.よく20世紀の知性の作り出した最高の産物の一つはポスト構造主義で,それはイメージが成立する空間をどうやって理論化していくかというところから発生しているからだと言われますが,僕は,ドゥルーズやデリダの試みというのは,このテクノロジーの社会のなかで構造主義の発想というものをどうやって変形,適用させていくかというところで出てきているのではないかと思います.そういう意味で言うと,イメージの生起する空間の問題と,ヴァーチュアル・リアリティという技術が作り出そうとしているものに直面しているわれわれの問題と,それから知的な領域で言うと,構造主義とそれが自己変容を遂げていくものの間には深いつながりが存在しているのではないでしょうか.
■■ピンクレディーとアジアのメチエ
伊藤――かつて,アントナン・アルトーがバリのダンスを見たときに,人間個人の無意識ではなく,世界の無意識に入っていくようだと言っていたと思うんですよ.彼はバリのダンスを見て,非常にショックを受けた.そして人は,バリのダンスにおいて言語以前の状態に落ちてしまう.自分の言語を選択できる状態に入っていける,という言い方をしてますよね.アジアのテクノロジーと言うとき,もう一つ身体のテクノロジーの問題が出てきて,その一つはダンスというかたちだと思うんです.デジタル社会における身体のテクノロジーの可能性については,言い尽くされた話題かもしれないけど,中沢さんはどうお考えですか.
中沢――バリ島での踊りが行なわれる空間というのは,わりと伸縮自在で,空間全体が広がったり動いたりしていてゴワゴワとリズミックに胎動している空間で,そこにはほかの世界と空間構造が違うという意識が濃厚ですね.ダンサーが踊り出すと途端にその人間の身体の周りにもう一回り大きい空間,その人間の神経が統御できる空間性が皮膚の外に広がる.ダンサーはその空間を統御してはいるけれども,意識が統御しているのではない.そこには,人間の意識の及ぶ,自由に柔らかく動きはじめる空間が作られていくわけです.そういう人間がたくさんいて,空間全体が計量,計測できない運動体に変わっていく,あるいはそうした時間を作ろうと意識的にやっているんです.
こういう人間の身体の技術は,アジアではすごく発達しています.外側の身体は労働したり税金を取ったりするためのものになりますが,人間の内側の身体は人間身体より大きいもので,それは計量不可能なものだという認識がすごく古くからあります.国家が税金を取ろうとすると,アイデンティティというものが必要ですから戸籍を作るわけです.そして人間を戸籍のなかにセット・インしていくというシステムがありますが,必ずそれとは別の空間がなければいけないということです.そして,人間の身体という空間がそういう場所を作っていますけれど,これは内的な空間ですから,要するにヴァーチュアル空間なわけです.だから,ダンスとヴァーチュアル空間が作ろうとしているものとの間には,決定的な共通性があると思います.
伊藤――バリを筆頭とするトランス・ダンスは,西洋的ダンスとは根本的に違いますよね.アジアのダンスは,超自然的,あるいは超越的なものと交流するテクノロジーを,いろいろなかたちでさまざまな場所に埋め込んでいるように思います.
![]() だとすると,じつはアジア的なものは身体のテクノロジーのなかに奥深くはらまれている,という言い方もできると思うんです.
だとすると,じつはアジア的なものは身体のテクノロジーのなかに奥深くはらまれている,という言い方もできると思うんです.
中沢――僕もそう思います.友人のアメリカ人カメラマンが日本人の身体の写真をいろいろ撮っているんです.お祭りのときの身体とか,花笠かぶった女の人,お茶をしている写真を撮っているんですが,僕はどれを見ても全然感心しない.こんなのは身体のテクノロジーじゃない(笑),と言って.ただ一つびっくりしたのがあって,それは温泉で肩にお湯を当てているおじいさんの裸の後ろ姿の写真なんです.要するに,その立ち方自体が僕には衝撃的だった.ダンスということではなくて,お尻がこうキュッと締まって,すうっと地面に立っている,それだけでダンスの原点かもしれません.日本人の身体というのならば,お茶とかではなく,これではないかという感覚をそのときに受けましたが,伊藤さんがいま,身体のテクノロジーと言ったのは,おそらくそこまで含めた広い意味においてだと思うんです.それはいろんなところに埋め込んであるんですが,それこそ納豆の練り方とか,そういうもののなかに,はっと驚くようなものが埋め込まれていて,それはなかなかデジタイズされないですね.
伊藤――アジア的なものは,インスタレーションとかメディア的な作品にはなりにくいんじゃないか,もう少し身体に内在化したものなんじゃないかと思いますね.
武邑――特に美術館や博物館みたいな無機的な空間にポッと持って来ちゃうと,本人達はハイテクとか言っているんだけれど,ものすごく浮いてしまうというか,ものすごいギャップを持つアートってありますよね.
中沢――この間,テレビでピンクレディーと安室奈美恵が競演しているのを偶然見たんですが,ピンクレディーはすごく存在感があるんです.安室は歌がすごく上手なんですけれど,バービー人形の世界ですね.確かに,その世界に突入しちゃっているという気持ちよさもあるんですけれども.アジアのアートというものを思い浮かべると,いまはまだすごくハイテクな環境のなかにピンクレディーが立っているみたいな(笑)感じがするんですよ.ピンクレディーと安室がやっていることの違いを,まだ日本人ははっきりと析出することができていませんよね.中国の美術だと,「あ,ピンクレディーだ!」という感覚がすごくする(笑).
ただ,ナムジュン・パイクは,易がライプニッツにコンピュータのアイデアを与えた,あるいは漢字が彼の普遍数学のもとになったんだ,という地点で,アジアの中国化された漢民族の技術の問題を,ヨーロッパ世界に提出した人だな,というのが長いことの僕の印象です.だから漢字とテレビ・メディアを彼はほとんど同列に置いていますよね.あの思考方法の元にあるのはかなりオーソドックスな地点で,そこに彼は地点をすえたんだろうと思うんですね.
伊藤――そうした意味で日本の現代美術も特別の危うい奇妙な存在ですよね.身体のテクノロジーと作品が遊離してしまっているというか.その延長線上に,突然,別方向から荒川修作さんの「養老天命反転地」みたいな場が出てくる状況については,中沢さんはどうお考えですか.
中沢――変ですよ(笑).現代美術には,一つメチエの崩壊ということがあるでしょう.ヨーロッパでは,印象派以降,メチエが崩壊してくるのと並行して現代アートが出てくる.あれは早晩,テクノロジー・アートにたどり着く運命にありますよね.メチエというのは身体のテクノロジー,つまり自分と外側の物質的世界との間のインターフェイスの技術です.アジアの現代アートにはそうしたメチエがまだ崩壊せずに残っている部分があって,さっきのピンクレディーというのは,そういうことじゃないかなと思うんですね.
武邑――デジタルなメディアは,ヨーロッパにしてもアメリカにしても,CGみたいなものの生成エンジンには,ヴェトナム人とかがすごく多いんですよ.ヴェトナム人は特に優秀で,フランスのCGはヨーロッパでは質が高い方なんですけど,そこにもヴェトナム人のメチエがあるんです.最近出てきている台湾のCGにしても本当にアジア的メチエという感じがします.
中沢――デリケート・テクノロジーというのはメチエの問題なんですけれども,日本はどっちつかずのあやふやな状況ですね.
![]() ■■「転回」がセットされたアジア世界の技術
■■「転回」がセットされたアジア世界の技術
伊藤――メチエに関してもう少し具体的な話になるのですが,以前,中沢さんと常滑とか西陣の工房の話をしましたよね.そのとき,職人的な身体には何十年もかからないとたくわえられない技術がつまっているということが出ました.そういう技術がないとこの赤や青の色が出ないとか,こういう肌ざわりが出せないとか.西陣なんかには,100工程くらいのプロセスがあって,その一つひとつに,特別な人と特別な工具などがはりついている.そういう職人的世界を中沢さんは夢見ていた(笑).
中沢――そうですね,僕はけっこう夢を見ていたときがあって,大きい仕事を企画したんですが,西陣の例の工程には原型がありまして,それは太地の捕鯨です.江戸の初期から捕鯨はあって,鯨を海から引き上げて最終的に油を絞り出すまでには何十工程もある.そこから学んで西陣が形成されたんです.それでもう一つ,これも夢見るような話ですが,戦後,中島飛行機にアメリカ軍が来て,零式戦闘機を分解したけれどその製作工程がわからなかった.日本学をやっている人がその工程は西陣とよく似ていますという指摘をして,初めて全工程の理解ができたと,吉田光邦さんから教えてもらったんです.これは歴史的事実で,それを一つの大きな流れとして日本人のメチエについての三部作を書こうと考えているわけです.まだ捕鯨しかできていないですけど,これは僕の一種の夢のようなものですね.日本の技術の特殊性の秘密はどこかその辺りにあるかもしれない.
伊藤――マニュアルのようなものを残さずに,すべて身体で記憶してしまう.そして,その人が亡くなるとそのテクノロジーは消えてしまうという状態ですよね.身体で確認して蓄積していく知恵といったものの重要性を,現在のわれわれは忘れてしまったんだと思いますね.その辺も何か「アジア」の現在に関わってくるんじゃないかと思いますが.
中沢――現在でも,ソニーとか東芝の技術は,中島飛行機の技術につながるような非常に特殊というか,ユニークな部分があると思うんですが,さらに,それをずっと辿っていって捕鯨までいったときに,では,この技術の特徴は何かというと,全体性とかホーリズムという言葉で言ってしまうのはちょっと惜しいと思います.見えない鯨が海中にいるのを戦争の技術を使って陸上にまで出してくる.つまりアジア世界の技術には,その最も基盤となる部分に,位相変換,ターニング・ラウンド,転回が意識的にセットされている,という特徴があるんだと思う.なぜ最初に神学の話から持ち出したかというと,ローマとアジア的なキリスト教の分裂のもととなったのは,まさにそこだったということなんです.ローマ的な神学は,鯨が海面に踊り出てこさせるために戦争技術,戦争装置を使う,まさにその部分をカットするんです.そして,初めて神の理解が出てくるんですけど,アジア的キリスト教はそこを焦点にすえる.だからアジア的思考法と戦争機械論が重要なところでつながっているだろうというところで僕は三部作を考えているんです.
![]() ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリが戦争機械という問題を出したときに,すぐにポール・ヴィリリオが言うような,兵站とか近代兵器の問題の方向に行ってしまったけれど,僕はあれを読んだときに,すぐにこれはキリスト教の三位一体の問題と同じ構造をしているなと思いました.アジアの技術として伊藤さんがずっと追求されている問題では,ターニング・ラウンドであって,トランスフォーメーションではないもの,それを引き出してくるものとしての身体とか,トランス技術,ダンスなどが,技術の下部構造にセットされてある世界を構想されていると僕は思っていたんですけど,どうでしょうか.
ジル・ドゥルーズとフェリックス・ガタリが戦争機械という問題を出したときに,すぐにポール・ヴィリリオが言うような,兵站とか近代兵器の問題の方向に行ってしまったけれど,僕はあれを読んだときに,すぐにこれはキリスト教の三位一体の問題と同じ構造をしているなと思いました.アジアの技術として伊藤さんがずっと追求されている問題では,ターニング・ラウンドであって,トランスフォーメーションではないもの,それを引き出してくるものとしての身体とか,トランス技術,ダンスなどが,技術の下部構造にセットされてある世界を構想されていると僕は思っていたんですけど,どうでしょうか.
伊藤――そうだと思います.まだ,あまり言語化して考えてはいなかったけど,無意識のうちにそういうことをやっていたんだとは思います.
武邑――匠の技術みたいなもの,身体的な蓄積みたいなものが,その人が死ぬとなくなっていってしまうという危機感は,京都にもかなりあるわけです.ところがいまの中沢さんの話にもあった,情報がプリセットされている場というのは,これはいろいろな意味で,時間をかけて成熟させてきたものですよね.風水がそうだし,『桃太郎』もそうです.尾崎紅葉に『鬼桃太郎』という続編があるんですが,その二つを京都に照らしてみると,すごく時間をかけてプリセットされてきていると言えます.多くの日本の伝統的な技芸が,身体的な継承というものをたしかに持ってはいるんだけれど,その身体の情報をいくらテキストにしても出てこないものをあらかじめ断念していると思うんです.たとえば京都の街並みの,さまざまな方位だとかポイントに置いてあるいくつかの装置を見て思ったのは,非常に重要なレファレンスをつねに身体のなかに成熟させていくことでしか実現されないものが,あの都市の構造とすごく結び付いているということなんです.
中沢――聖地というのは身体でそこに入って行かないと意味がないし,そこに必ず巡礼しなければならないんですが,なぜかということは謎ですね.その空間のなかに入っていかないとわからない.
伊藤――身体で入っていくというと,VRのテレプレゼンス・リサーチ社のマークは,アボリジニが水のなかにダイビングするシーンだったんです.あれは,ある意味でアボリジニのドリームタイムのような感覚を持っていたと思うんです.たとえばチュリンガってありますよね.じつはあれは目で見るというよりも,石とか木にいろいろなでこぼこがあって,つねに触り得る肉体,触ることによって初めて意味が生成してくるような場みたいなものです.そしてチュリンガも一種の聖地,触りうるポータブルな聖地のわけです.たとえばそれは口承伝承のシナリオになったり,何かを演奏するときの楽譜になったり,触っていくことによって足のステップを引き出す振付表になったり,実際の地図や神話のグラフィックになったりと,一つの情報の構造体のなかに非常に多面的な感覚を触発するような,いろいろな仕掛けがはらまれている.もともとコミュニケーション・エンジンというのはそういうものだったと思うんです.先ほど言った記憶のテクノロジーとも重なってくるし,同時にチュリンガの場合は先祖の肉体でもあるわけですから,つねに彼らはそれに触ることによって先祖の時間のなかに入っていけるという,ある種サイバースペースのモデル化といったところがあります.
![]() 中沢――レヴィ=ストロースが『野生の思考』のなかでチュリンガのことを書いていて,チュリンガは触って持って歩くもので,これはあたかもヴィクトル・ユーゴーの生家に行ったときに感じるようなものであると書いています.これは,尾崎紅葉の生家でも宮沢賢治のでも構わないわけですが,そこに行って触れた人間が何を感じとるかに関わっていると思うんですね.ヴィクトル・ユーゴーの作品をわれわれはいろいろと読んでいるけれど,僕らがそのとき関心を持つのは,これらの作品を生んだヴィクトル・ユーゴーという身体です.その身体とは何かというと,それらの作品が,書物のかたちに空間化される以前に,この情報が詰め込まれていた原 = 情報体で,それに関心があるんです.だからすべての作品を合わせたよりも巨大なヴィクトル・ユーゴーという情報体に関心がある.彼の生家に行ったとき,僕らはその空間に触れるわけです.チュリンガもそのようなものだと彼は指摘しようとしているんだと思いますけど,ここでも情報の問題と身体性は結び付いていますね.このことが,いまのテキスト論から欠如している問題だろうと思います.
中沢――レヴィ=ストロースが『野生の思考』のなかでチュリンガのことを書いていて,チュリンガは触って持って歩くもので,これはあたかもヴィクトル・ユーゴーの生家に行ったときに感じるようなものであると書いています.これは,尾崎紅葉の生家でも宮沢賢治のでも構わないわけですが,そこに行って触れた人間が何を感じとるかに関わっていると思うんですね.ヴィクトル・ユーゴーの作品をわれわれはいろいろと読んでいるけれど,僕らがそのとき関心を持つのは,これらの作品を生んだヴィクトル・ユーゴーという身体です.その身体とは何かというと,それらの作品が,書物のかたちに空間化される以前に,この情報が詰め込まれていた原 = 情報体で,それに関心があるんです.だからすべての作品を合わせたよりも巨大なヴィクトル・ユーゴーという情報体に関心がある.彼の生家に行ったとき,僕らはその空間に触れるわけです.チュリンガもそのようなものだと彼は指摘しようとしているんだと思いますけど,ここでも情報の問題と身体性は結び付いていますね.このことが,いまのテキスト論から欠如している問題だろうと思います.
伊藤――記号を使ってインタラクトする場合は,ミスを犯しやすいが,後ろにあるものを見るために頭を動かす身ぶりにミスはない.そういう直観的な動作こそが,サイバースペース上では重要になってゆくだろうという予測があります.本能的なアクセスや直観的なインタラクションは,ものごとを理解するためのわれわれの感覚・認知能力を活性化させる.『フューチャー・マインド』を書いたジェローム・グレンが来日したとき,ポスト情報化社会は“意識のテクノロジー”の時代であり,科学技術が支配する非人間的社会を阻止するためには,人間の直観力に基づく神秘主義とテクノロジーの良質な融合こそが,最重要になるだろうと言ったことがありますが,そういう意味でも,アジアのテクノロジーを考えることは,これからもいろいろな問題を提起してゆくように思います.今日は,ありがとうございました.
[1996年10月15日,東京にて]
(なかざわ しんいち・宗教学/いとう としはる・美術史/たけむら みつひろ・メディア美学)
