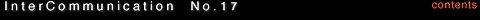
1987
野々村文宏
この本のタイトルは,偶然ながらハワード・ラインゴールド『思考のための道具』によく似ている.しかしこの二書のアプローチはぜんぜん違う.そもそも道具なり道具箱なりの言葉から連想するのは,実用,それも応用の,つまりはデザイン・ツールのイメージである.しかしここでラッカーが使っている「道具箱」とは,観念を作るための道具箱のイメージなのであり,つまり思考とは観念のことなのである.したがって,そのようなタイトルでは本は売れないだろうが,『観念の道具箱』と言いかえたほうがより本書の本質を理解しやすい.そして,読んでみて驚いたのは,ラッカーの説明が絵画的なイメージに満ちている(ラッカーが本書で引用する量子力学者ボーアの言葉「相補的」を使えば,本書で展開される数学の概念と絵画とは「相補的」である,と言い直したほうがよい)ことである.
この例は枚挙にいとまないが,たとえばひとつだけ.序章の締めくくり「観念の歴史旅行」のなかでラッカーは「ルネサンスにおける遠近画法が意味する重要事項キー・アクトは,物理的空間が数学的に取り扱われていることである.中世の絵画は平面的な仕切りであって,画面には数に似たメッセージを暗号コード化するための像が描かれていたが,遠近法によって描かれた絵は対象を単一の数学的空間と結びつけるものであった」(p.42)とさりげなく書いている,あまりにさりげないので困ってしまうのだが,たったこれだけの文にふくまれるラッカーの問題構制の重要さは,たとえば本ブックガイドにも含まれているパノフスキー著『〈象徴形式〉としての遠近法』などを参照しないかぎり....読者にもともと絵画についてかなりの素養なり読解力が備わっている場合をのぞいて....,それこそ空間として把握できないだろう.これを筆者の個人史的な文脈に照らし合わせてみれば, 80年代前半,たとえばキャロル・アーミタージュのバレエとデヴィッド・サーレの絵画のコラボレーションに代表されるようなポストモダンの饗宴の頃には,遠近法の問題など過去に片付いてしまった問題のように思われてならなかった.視覚の再現からいかに離れるかという問題構制を持った20世紀美術が再び視覚表象と結託しはじめたかのような(ニュー・ペインティングというよりは)ポストモダンのデヴィッド・サーレたちの絵画において,20世紀美術は一応の最終回答=勝利を迎えた.つまり,恥ずかしながら,「なにを今さら遠近法」,そう考えていたのである.しかし,コンピュータ・テクノロジーの発展により,時代が3Dになるにつれ(もちろんこれは皮肉),時代の退歩への強迫観念として,パノフスキーを実に新鮮に読むことができるようになった.
言葉を変えれば,10年前の筆者であれば,本書の絵画的な豊穰さに気付くことなく,よくある数学または情報科学の入門書としてこの本を読み捨ててしまっただろう.しかし現在の筆者にとってみれば本書において1行で済まされる「人間の生の本質は集合論(神学の数学者版)の逆説的パラドキシカルな無限と密接な関係にあると言えるだろう」(pp.9−10)が,ラッカーを執筆へと駆り立てる,そして多くの絵描きにとってもまた普遍の強迫観念であることに気付き,愕然とするのだ.やっぱり数学史は大切だ.それをラッカー流の唯物史観ならぬ観念史観になぞらえて言えば,中世=数,ルネサンス=空間,産業革命= 論理,近代=無限の時代であり,近代を超克するための「思考(観念)の道具」こそが本書で語られる情報理論であるということになる.しかし残念ながら筆者は,ラッカーの道具箱の普遍性について審判を下すことはできない.しかし,そのような留保をおいてもまだ,本書は次の時代を描こうとするアーティストたちにとってヒントが満載された本であり,ときどき立ち返って読むと新しい発見をすることができる数学と情報についての有効な副読本なのである.もちろん,逆に言えば本書を道具箱として使いこなすためにアーティストの側に求められるものは,たとえばライフ・ゲームなりフラクタルなりを名辞として扱うのではなく,最低限そのような名辞を成り立たせる考え方について考えることができる力なのである.
(ののむら ふみひろ・VR,マルチメディア研究制作)
■関連文献
柄谷行人『探究I』講談社,1986.
エルウィン・パノフスキー『〈象徴形式〉としての遠近法』(木田元,川戸れい子,上村清雄訳),哲学書房,1993.