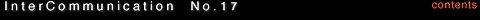
1982
御手洗陽
書くことは技術である.ただし,実践されるときにはつねに,すでに身体化されており,とりたてて意識されることがない.その結果,私たちの思考や表現において当然であると思われてきた諸特徴が,「文字に慣れた精神」の産物であることに気づくことはなかった.あまりに自明な先入見であるために,「声の文化(Orality)」との比較がなければ,「文字の文化(Literacy)」の住人であることを自覚できないのである.
オングが書くことの歴史という文明論的な射程において提出した問いとは,次のようなものである.ことばの具体的な様態,つまり「声」として発せられるか,または「文字」として書かれるかによって,社会という拡がりにおいて思考や感受性,表現のありようは大きく異なるのではないか.文字の文化を強化するものとして位置づけられる印刷を含めて,三者の関係は次のように示されている.「書くことは,本来的に声であり話されるものであることばを,視覚的な空間のなかに再構成したが,印刷は,さらに決定的に,ことばを空間のなかに根づかせた」(p. 253).
では声の文化の特徴とは何か.すでに文字の文化にある私たちにとってはなかなか想像し難いけれども,もっとも基本的なイメージはまさに声の文化でホメロスが述べた「翼をもったことば」に求められるであろう(p.163).声はまさに消えようとするときにしか存在せず,話す−聞くという関係に生ずる一過性の出来事である.ことばは関係のなかに力として現われるのである.それは私たちの「精神の所有物がいわば惰性的な心的空間のなかに保管されているという感覚」(p.270)からすれば,いかに異質であるかがわかる.
また声は一度発せられてしまうと再現することが困難である.そのために記憶が重視され,韻をふんだり形容詞を冠したりといった,馴染みやすくくり返しやすい決まり文句,抑揚やリズムなどが効果的に用いられた.思考は記憶のエコノミーに準じて紡がれたのである.それに対して書くことと印刷は分析的で抽象的な思考を可能にした.ことばは字句の連なりとして眼に視えるように固定され,そこに生じる意味をふり返って吟味することが可能になる.さらにアルファベット順(または五十音順)の辞書の成立にみられるように,文字は産み落とされた文脈とは無関係に独自の秩序で束ねられる.ここに論理や表現の正確さに対するこだわりとともに,権威化の地盤も用意される.
本書では以上のような自明性の引き剥がしの後に「内面への転回」が語られる.書くことと印刷は他人とは違う自分自身という感覚を強め,人びとの間に意識的な相互作用を生み出した.そのメカニズムは知る主体と知られる客体との分離や内面への分節化された注視など,さまざまな角度からいささか断片的に言及されており,組織的な解明が今後の課題として,広く読者に委ねられている.いずれにせよ人間の精神の力に対して深い信頼感を抱く著者は,その解放にもっとも貢献した技術革新として書くことをとらえる.そして比較のための声の文化の再構成という試みは,そのまま文字の文化の可能性を賭けた実践となっている.
もちろん「二次的な声の文化」とされる電子的な経験こそが,メディアへの関心を広く呼び起こす契機であったろう.本書はその解明のためにも一度,歴史的な省察に向かう必要を示唆している.その作業は自覚されないままに私たちの身体を貫く諸力の解明に向けられており,精神分析をはじめとする今世紀の思想動向とも深く連動している.私たちの現実を問うための知恵である.
(みたらい あきら・メディア論)
■関連文献
M. T. Clancy, From Memory to Written Record: England 1066-1307, 2nd ed., Blackwell Publishers, 1993.
E. A. Havelock, The Muse Learns to Write: Reflections on orality and literacy from antiquity to the present, Yale University Press, 1986.
Ivan Illich, In the Vineyard of the Text: A Commentary to Hugh's Didascalicon, The University of Chicago Press, 1993=『テクストのぶどう畑で』(岡部佳世訳),法政大学出版局,1995.