
| InterCommunication No.14 1995 |
 |
Feature |
ヴァーチュアル・リアリティの2000年
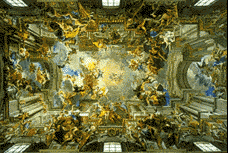
 Go English
Go English
 前書き
前書き 序論
序論 ルネサンス人文主義
ルネサンス人文主義 テクノロジーによるユートピア
テクノロジーによるユートピア 消費者文化
消費者文化 身/心のギャップ
身/心のギャップ 二重の肉体
二重の肉体以下に読まれるエッセーは1991年に書かれた.VRをめぐるメディアの興奮が起こる前のことである.この興奮も今ではひとまず沈静化し,VRはメディア・テクノロジー発達史の中の単なる一段階にすぎなくなり,VRを取り巻いていたナンセンスなユートピア的謳い文句から解放されることになった.著者は1992年から93年にかけて,何本かの論文[★1]を書くうちに,このエッセイを書いたころとはいく分異なる考え方を持つようになり,またそこには自ずと進展もあった.
テクノフィリア的謳い文句をまとったどんな反対論が出ようと,VRという名で知られるリアルタイム・インタラクティヴ・デジタル映像合成は,西洋文化の奥底に潜む根深い願望を実現しようとするものであることは明らかである.ジャロン・ラニアーはかつて,VRは「文化の極致」であると指摘していた.それはまさにその通りである.ただし,VRが完璧なものだとか,デジタル版総合芸術(Gesamtkunstwerk)であるとかいう意味でそうなのではなく,西洋の哲学的,文化的営為を継承するものとして生み出されたものであるという意味でその通りなのである.このエッセイのテーマとなるのは,VRがどのような形で西洋文化の歴史的側面と連続するのか,という問いである.これには,ふたつの関連し合う史的発達の軌跡,すなわち絵画表現および遠近法的錯 覚,そして演劇的スペクタクルおよびこれと隣り合う再現芸術という2点に注目してそこに浮かび上がる里程標とも言うべきいくつかの重要な問題点を素描して答えてみたい.こうした発達の軌跡は,それ自体一貫した哲学思想の流れによる裏づけを持っており,この連綿たる流れの中にはキリスト教思想,ルネサンス人文主義,啓蒙主義的合理主義,そして消費文化というものが含まれているのである.このエッセイを書くに至った一番の動機は,テクノロジーというものは単純に生まれるものではなく,具体的な社会的,文化的歴史から生みだされるものであるということを強調したいという点にあった.テクノロジーとは哲学的なさまざまな思想を具体化したものである.そこで,いくつかの重要な問題点へのアプローチを組み合わせて,VRと呼ばれるテクノロジーに具体化された思想を明らかにしようと試みたのである.
VR開発者たちはおそらく意図せずして,人文主義的世界観(生への姿勢と絵画制作の方法の両方における世界観)を継承していたのである.つまり見る者の視点を操作者の視点,つまり世界の中の特権的視点へと置いていたのである.従ってこうした視点は,総合的に見れば個人の概念の隆盛と結びついている.アジアの絵画はこれとは別の見方あるいは構図を教えてくれるし,また中世ヨーロッパの絵画もまたこれとは異なる見方,構図を示している.テレビジョンは第三の見方,すなわち複数の視点とすばやいカットの切り換えによって肉体の解体へと行き着く世界を示している.
VRがルネサンス人文主義以外の指導原理に従って発達したとしたらどうなっていただろうか.VRの世界に素直に入りこめると感じられただろうか.万人に理解されるような既得の文化知識に依存するいわゆるVRなるものは,いったいどれほど存在するだろうか.西洋遠近法,あるいは絵画表現システム全般は,われわれの感覚システムに本来的に根差したものではなく,学習によって(それも厳しい訓練を経た後に)獲得される習慣である.ところが,このことは絵画表現上の技術にとどまらないのである.ルネサンスの遠近法の習慣の中に根を下ろしたのは,見る者を単一の特権的な場に置く価値体系だったのである.遠近法とは眼差しの力である.VRはルネサンスの遠近法という制約を伴うテクノロジーを継承し(制約と言う理由は,この遠近法はわずか10-15度の視角しか持たなかったからである),そして(特権的な力を持つ)見る者の周囲を正確にこのテクノロジーで覆っていったのである.
インド舞踊に関して最近のあるエッセイには次のようなことが述べられている.「空間感覚が完全に違うのである……長々と走り回ったり空中高く跳ねたりといった努力をして舞台を無限の領域に見せかけることをまったくしない.舞台ははじめから一種の形而上的な遍在的場でありながらも,身体が作り出す世界の中の一部であり,苦もなくあらゆる大きさ,あらゆる重力に適応し,万事悠々として中心に収まっている」.エッセーの著者は舞踊教師の肉体に対する態度をこう述べている.「上昇や横への拡張という感覚はそこにはまったくない……肉体は自己充足的だ……とにかく内面へと向いている……ヒンドゥー教では彼方というものが存在しない」[★2].これはインドの舞踊教師の言葉として紹介されている.このような肉体=空間関係の認識はVR固有のそれとは真っ向から対立するものである.物に触るという体感は,当の物体との直接的な身体接触を必要とするが,目で見るという場合は異なる.VRは目に武装を施す.VRは目に対して手の代わりとなる力を与え,眼差しそれ自体の力でつき動かされる(ように見える)のである.視覚の優越性は対象と距離を置いた行為という点にあり,これがルネサンスの絵画空間の特権的視点へとつながるのである.身体全体は空間を展望しようという欲望でつき動かされるのである.
最近よく言われるように,VRは,ポンペイの壁画にもすでに例が見出せるような,錯覚を使った絵画表現の伝統に直接連なるものである.この錯覚を利用した絵画は,ルネサンス時代に古典的光学理論の発達と相俟って再発見されたのである.絵画技法と光学というこのふたつの要素はルネサンス期の人文主義的世界観を形成する総合概念となった.そしてこの世界観は依然としてわれわれの現代文化の基礎となっている.それ以後の世紀では,この錯覚的手法がひとつの技術と化し,最初は光学的描画器具の利用を通じて,さらには二次元および三次元写真映像の発達を通じて定着していった.こうした「完全」なまたは「包括的」な錯覚的手法へと向かう欲望は,映画の発明によって時間という次元を獲得した.
錯覚的手法が技術と化してゆく歩みと相即するものとして,一方では大がかりな演劇スペクタクルの連綿たる伝統,それに万国博やアミューズメント・ピア[棧橋に造られた娯楽センター],テーマパークの伝統というものがある.こうした例を見れば,錯覚的手法が,今やますます洗練を遂げるシミュレーション技術と連続していることもまた明らかになる.つまり錯覚を求める欲望はつねに西洋文化の奥底に存在して,いつの時代でも持てる技術の限りを尽してスペクタクルやシミュレーションを追求しようとするのである.次に取り上げるいくつかの例は,相互の歴史的な関連こそ薄いが,VRを考える上での視点を提供してくれるだろう.
大がかりな演劇スペクタクルはルネサンスおよびバロック期を通じて定期的に上演されていた.1548年ハンガリーの女王はスペインのフェリぺ二世を歓迎するに当たって,ダンス合戦を皮切りに2日間にわたる祝典スペクタクルを催した.ダンスのさ中,「野蛮人たち」が襲撃してきて,抵抗する女性たちを何人か連れ去ってゆく.翌日,「騎士たち」が野蛮人らの立て籠もる城に攻撃をかける.それに続く闘いの場面では,激しい乱闘の真ん中でフェリぺ二世はニンフやナイアスたちに饗宴のもてなしを受ける.王はこの観客没入型スペクタクルの中心に何事もなく坐って楽しむのである.
バロック期の天井絵画もこうしたシミュレーション技術史の中に加えてしかるべきものだろう.眩惑感を生み出す職人芸によって,見ている者は「天へと吸い込まれてゆく」ような感覚を味わい,建物という物理的要素はこの絵画的錯覚の中に消え去ってしまうのである.われわれが日常経験するものとは異なる現実をそれらしく表現するために教会が用いた,この歴史的な先端シミュレーション技術は,VRに対して教会が昔から興味を寄せてきたことを示す好例である.
19世紀後半では,前映画技術とでも呼ぶべき技術分野で爆発的な数の発明が行なわれた.1838年にはイギリスの科学者ホイートストンが早くも最初のステレオスコープを組み立てている.最初の多人数鑑賞型ステレオスコープは1890年リヨンで公開された.マレイ,マイブリッジの広く知られた連続写真の実験とともに,エジソンのキネトスコープやリュミエール兄弟のシネマトグラフ,それに大なり小なりの奇妙な光学/機械シアターが作られた.
ダゲールのジオラマもそうした見世物小屋のひとつで,観客が回転式の鑑賞席に坐って次々といろいろな情景を描いた絵を見てゆくという仕掛けになっている.絵は透明度を変えて丹念に描き分けられ,フロントとリアからの照明の当て方をコントロールすることによって,夜明けから日没そして夜の闇へという具合に,あたかも一日が経ったかのような錯覚的効果を生み出すのである.それまで凡庸な写実画家兼舞台の書割画家として鳴かず飛ばずの日々を送ってきたダゲールは,この発明で一挙に大成功を収め,この収入を元手に写真の実験に乗りだすのである.今日ではダゲールの名は,むしろこの写真の方でよく知られている.
1900年のパリ万博[☆1]には,こうした光学/機械装置を使った見世物小屋が競うようにいくつも並んだ.マレオラマはニースからヴェネツィア経由でコンスタンチノープルへと行く船旅をシミュレーションしたものだった.このシミュレーション航海では,高さ40フィート,横2500フィートに達する2枚のスクリーンが,次々と風景を繰り広げてゆき,観客は縦ゆれする船の甲板に立ちながらそれを眺めるという仕掛けだった.この装置の発明者も同じくしがない写実画家ユゴー・ダレジという人物で,彼は1年間船に乗り組んでスクリーンに使う絵を描き続けた.当時の新聞は次のように大風呂敷を広げて紹介している.「博覧会に訪れる人で,……こんなことを言われて試してみる気にならない人はいないだろう.……安くて,何の危険もなく,……それでいて高波にもまれ,悪天候の中を進むという本物そっくりの航海が味わえるというのだ.しかも好きなときに降りて固い大地を踏みしめることができるときている」[★3].
シミュレーション版シベリア横断鉄道もやはり同じ機械仕掛けの見世物で,背景幕を動かす複雑な装置が使われた.この鉄道小屋は戦略的にロシア館と中国館の近くに置かれ,これを制作したのは国際寝台車製造会社なる企業だった.ここには,企業PRにハイテクを利用するという今日の方法と歴史的に共通するものが見出せる.[ディズニーの]エプコット・センター計画などもこれとさほどかけ離れたものではない.
同じ頃,ド・セルビー侯爵という学者は,さらに本物そっくりの「仮想」旅行実験に没頭していたようだ.
「イギリスに滞在中,彼はたまたま一度バースで生活することになり,そこからフォークストーンまで緊急の用事で出かけなければならなくなった.それを行なう方法というのが彼の場合は通常とかけ離れたものだったのである.鉄道の駅へ出かけていって列車の問い合わせをする代わりに,旅行中に通過する地方の絵葉書と,入念に時刻を調整した複数個の時計,気圧計類,そして外光の変化に合わせて心地良くガス灯を調整するための装置を持ち込んで,自分の部屋に閉じ籠もったのである.部屋では何が起こったのか,あるいは時計やその他の機械がどれほど正確に作動したのか,いっさい分からない.7時間後,部屋から出てきたときには,彼は自分がフォークストーンに行ったことを確信し,さらには鉄道や船会社に対して極度の嫌悪感を抱く旅行者たちのための新たな旅行手段を開発したとの確信をもどうやら抱いたらしい」[★4].
テクノフィリア的謳い文句によって表わされるVRの側面は,VRのほかの側面と同じく,別にことさら新しいものではない.テクノ・ユートピア風の誇大宣伝は,産業革命初期以来,テクノロジー宣伝の一側面をなしてきたようだ.たとえばそれは次のような19世紀の滑稽詩に具体的に見てとれるだろう.
汝らの国のここかしこにレールを敷け,
ありたけの列車を蒸気の勝利なる車につなげ.
町と町を結べ.鉄の帯をもて,
久しく疎遠をかこち,時に相争った国と国とを結べ.
平和の神にして柔和なる瞳のケルビム天使,――知識の守護神なる光の神は,
あらゆる鉄路によりて使者を送らむ…….
科学に祝福あれ,そしてその僕なる蒸気に祝福あれ!
これらこそ理想郷の夢を半ば実現するものなり![★5]
西洋文化への機械の浸透の過程で,ユートピア的とディストピア的という対立する修辞的語彙が形成された.ディストピア的側面は,心理および行動の両面でのパニック状態という形で特徴づけられる.すなわち,労働と精神の両方における冗長性への恐怖である.ユートピア的側面については,セオドア・ローザックが,「救済願望は……新しいテクノロジーの周囲に群がり」[★6],上に挙げたような詩作を生み出すことになると指摘している.この詩の中には啓蒙主義時代にできたいわば結石が含まれている.すなわち平和,知識,科学,技術であり,どれもユートピアへと通ずるものばかりである.
トーマス・エジソンは,自分のフォノグラフが音による「素敵なスナップ写真」,すなわち故人となった親しい家族の誰彼の声を保存するための手段として,うってつけのものとなるだろうと考えた.企業資本主義が自分の発明を利用するとは夢にも考えなかった.要するに音楽ソフト産業に利用されるとは考えてもみなかったのである.バザンは映画についても同じような考察を行なっている.「映画の将来を一番信じていなかった人間こそは,誰あろうふたりの企業経営者エジソンとリュミエールだった.エジソンはキネトスコープの発明だけで満足していたし,リュミエールの方は分別のあるところを見せてメリエスに製造権を売るのを拒んだ.もちろんメリエスにして見れば多大の利益を見込んでいたのだが,ただ彼は映画をたんなる娯楽商品としてしか見ていなかったのだ」[★7].ブレヒトはラジオの持つ潜在的な解放力を讚えている[★8].それに対し,テレビは初期の理想的な謳い文句とは裏腹に,理想の民主主義的情報ネットワークへとは進化せずに,さまざまなソフトを売ったり,一定の価値観を叩き込むための空想的手段にしかならなかった[★9].VRは,こうした先駆的な新テクノロジーの波の周囲で発生した解放的で民主主義的な宣伝文句を引き継いだのである.ただ残念なのは,こうした場合のユートピア的宣伝文句は,これらの新テクノロジーを体制的な形に応用しようとするときには,厳しい反対論として機能してしまうことである.こうしたテクノロジーは,強力な支配,操作,管理の道具になる傾向を持つからである.VRに対する現在のユートピア的楽観論は,自由放任主義的な経済論的コンテクストの中でテクノロジーの発達が辿るおなじみの歴史的段階のひとつであることを,この際認識しておく必要がある.ユートピア的謳い文句は,発明者集団にとってはいかに真実のものと感ぜられようとも,結局は商売人集団にとってのきわめて便利な広告文句にしかならないのである.
「SIGGRAPH 90」[★10]での今や伝説的になったVR会議において,VRは,SIGGRAPH側に言わせるなら,「2万5千人の近しい有志の人々」からなる集団の前に「登場」したのである.質疑応答の際,私は主催者側に,私の知る限りでは支配者集団が権力の座を守るために最新の技術を使用しなかった例は世界の歴史上ただの一度もなかったはずだが,と言ってみた.その上で,彼らにとってみればVRも同様の手段だと考えない理由はないではないかと質問したのである.結局,質問は丁重に無視された形になったが,別段驚きもしなかった.
タバコやスナック菓子のメーカーが大枚をはたいて自社製品をハリウッド映画の中で使わせていることは,今や誰もが知る常識である.70年代に遡れば,リチャード・セラは,ケーブルテレビに加入するには,テレビ会社が投資した資金の1ドル当たり消費者側が40ドルの金を支払うことになると指摘していた[★11].こういう事実を前にしてもなおVRだけは特別だという幻想にひたれるのは馬鹿者だけである.何ならディズニーランド・スタイルの民生型ヴァーチュアル・ワールドを想像することもできる.そこにはインタラクティヴ機能を持つ,けっこうインテリジェントなコークとか,抱き締められるほど巨大で,セクシーなクスクス笑いをするホットドッグとかが登場するだろう.あるいはヴァーチュアル・スーパーマーケットでもよい.そこでは商品が棚から身を乗り出してこっちを見つめると,しきりに自分を買わせようと勧誘を試み,これこれを買ったらもっと楽しく,もっと健康に,もっとセクシーに,もっと裕福になる……云々と口上を言うだろう.
企業経済のもとでは,VRはコンピュータ産業にとって実に便利な代物になる.VRは直観的に操作ができる(学習曲線も描かなければ,消費者の抵抗もない)し,高い演算能力を必要とすればするほど高い能力のコンピュータの需要が起きて,企業戦略にとって有利な条件を作る.このテクノロジーへの欲望とは,つねに新鮮な対象へと向かうリビドー的欲望の転移にほかならない.新しい対象は今度こそ快楽を提供してくれるように思えるのだが,結局は完全な満足に達することはなく,消費者を次の商品購入へと駆り立て,こうして満足感を次々と先送りしてゆく連続的プロセスが成立する[★12].
早くも1967年にギー・ドゥボールは現代社会における消費者文化というものを論じていた.「……生活の全般はスペクタクルの巨大な集積として立ち現われる.直接的に体験されたものはすべて 表象 の中に追いやられる」[★13].彼はフォイエルバッハを引用して次のように言う.「ところが,現在の世代の人々は当然ながら,意味内容よりは記号そのものを好み,オリジナルよりはコピーを,現実よりは空想を,本質よりは外観を好む以上,……彼らにとって幻想だけが神聖なのであって,真実は俗なるものにすぎない.否むしろ,神聖さは真実度が低下するに従って強化されるような仕組みになっており,最高度の幻想こそが最高度の神聖さとなるのである」[★14].
VRは摩擦もなく易々とわれわれの文化の中にすべり込んで来るだろう.われわれの文化にはVRを迎え入れる準備ができているのだから.前のところで私は,ルネサンス以来開発された重要なメディア・テクノロジーは,すべて何らかのシミュレーション・シアターの創造に利用されたと述べておいた.このことはアンドレ・バザンの考え方とも共通し,彼は50年代に次のように述べていた.「映画の発明を導き……それに着想を与えたものとは,写真からフォノグラフへと至る,19世紀に行なわれた機械による現実再現技術を多かれ少なかれ曖昧な形で支配してきた神話の完成であった.その神話とはすなわち,完全リアリズムであり,映像による世界の完全再現であり,芸術家の自由な解釈や時間の不可逆性という軛を免かれた映像である」[★15].
このようなVR受容態勢は,ディズニーランド,ハリウッド,脂肪吸引美容,任天堂といった現象によく表われている.概念的には無内容のテーマパーク,非芸術的映画,インタラクティヴ・ゲームといったこれらのものはいずれも個人神話を追求し,自由としての暴力の崇拝を追求している.それに加えておそらくもっとも重要なのは,ある種のホットロッド・カーのように,好きなように,肉体を 特 化できるという考え方が人々に受け容れられている状況があることだろう.アメリカ文化は今や自動車をカスタム化するように肉体をカスタム化するのである.つまり肉体は表象にすぎない.外的な表われなのであり,所有者の好みに合わせて調節すべきものなのである.ヴァーチュアル・ボディの究極の可塑性とこれとは,たんに程度の差があるだけなのだ.肉体を外科手術的にカスタム化しようとする傾向,すなわち「 脂肪除去手術 」とヴァーチュアル・ボディのデザイン作業とは,肉体を純粋なる表象ととらえ直すことによって,デカルト的二元論を支持し強化することになる.こうして,肉体はすでに表象になってしまったのだから,VRまではほんの一歩である.1992年4月初め,昼のTV番組の司会者ヘラルド・リベラは,スタジオの視聴者の前で放送中に本番で脂肪吸引手術を受けた.ぶよぶよの黄色い脂肪の塊が彼の臀部から吸い出されると,次に彼の口元や目の周りに注入されたのだった.
VRはどれくらいリアルなのだろうか.VRの文化的な受容基盤はすでに出来上がり,VRがまさに適切に「現実」を表象するものであるという一般的認識を生み出している.TVと自動車はすでにこれをやり遂げた.時速60マイルで走るエアコン付きの車の車内から田園地帯を「体験」できると考える文化にとって,自動車はきわめてリアルなものである.VRは,歯痛に悩む人の絵くらいにはリアルである.しかし堂々と壁を通り抜けたり,何の臭いも温度もない現実というものは少しもリアルではない.そこでよりさらに複雑で高価なインターフェイスの開発が問題となるのである.
シミュレーションによる本物らしさの増大には逆説的な側面がある.すなわち,表象が複雑さを増すほどにギャップが大きくなるのである.要するに精度が増すことは,表象が現実を表現していない様と程度とをはっきりと露呈することにほかならないのである.これはアーサー・デントの「紅茶のジレンマ」というエピソードを思い出させる.「かなり落ち着きを失ったままどうにか一日の営みを始めたアーサーの心は,前日のショックでバラバラになった心の断片を拾い集め立て直しを始めた.彼は食物製造機なるものを発明していたのだ.その機械は彼にプラスチック製のコップとともに液体を差し出した.液体はほとんど紅茶と言ってよいものだったが微妙に違い,結局のところまるきり別物なのだった」[★16].
VRに関しては,VRによって心=身二元論から解放されるという主張がある.それができるのはVRが文字表象への/からの翻訳というプロセスを無視できるからであると言われる.これはウィリアム・ブリッケンその他によってポスト文字コミュニケーションと呼ばれている.こうした主張は,私の見るところいささか疑わしい.私の主張ではむしろVRはデカルト的二元論を強化し,肉体を肉体のイメージで置き換え,心というものを創造する行為である.そうである以上,VRは肉体と分離した精神を夢見る合理主義的夢想,つまり肉体の拒否という連綿たる西洋文化の伝統にはっきりと連なるものなのである.
ジャロン・ラニアーは,「人が自分の肉体に話しかけるときに文字は使わない」[★17]と言う.おそらくそうだろう.しかし,そこから論理的に導かれる系は次のようなものではないはずだ.「人はほかの人が手に取るコップを自分も手に取ることができる.……その行為に絵も『コップ』という言葉も必要がない.……このとき人は表象的対象ではなく体験的対象としての『コップ』を作り出している」[★18].しかし,VR内のコップは表象であり,立体的イメージにすぎないのである.それで飲み物を飲むことはできない.
VR体験には明らかにパラダイム転換が存在する.しかしそれによって表象的なものが「現実なるもの」(つまり体験的意味での現実)に置き換えられることはない.むしろ相互に入れ子状になる,あるいは互いに重ね合わされて,対象は同時に表象であるとともに体験的現象になるのである.VRは一方では「言語」をバイパスして直接肉体に,運動感覚にインターフェイスするコミュニケーション技術である.しかし一方では,VRはみなそれ自身ひとつの巨大な(インタラクティヴ)表象であり,そしてそうであるからには,そのほかのすべての表象と同様の批判的分析の対象になるわけである.
そういうわけで,共有するVR内で双曲放物面状のヴァーチュアル・オブジェクトを,VR内の相手に手渡すことができるということは,代数の等式を書いて相手に渡してそれをデコードさせるよりは,ずっと直接的なコミュニケーション行為であると言ってよいわけである.ヴァーチュアルな形態というものは,対象そのものが等式の中に封じ込められたデータの視覚的な正確な再現であり,また数学的情報としても処理できるという点で二重に便利である.同じ形態を石膏の型に取った場合,これほど流動的な情報へのアクセスは行なえない.事実,ウィリアム・ブリッケンは,あらゆる種類の記号を使ったあらゆる論理操作は,VR内で何らかの言語記号を使うことなくして実行され,また論理操作は視覚的プログラミングという形をとった推論と等価となると述べている.集合論,整数論,代数学は,いずれも非記号的にしてしかも完全に数学的に厳密な空間内で表象されうるのである.二値論理は開閉するドアとして,結び目理論は滝を登って上流へと遡る魚として表象できるのである.「すべての計算は代数的なパターン・マッチングと置き換えである(と証明されている)」[★19].現在必要なのは,新たな批判法であり,VR内で体験される肉体の直接的な心理的現実性と表象批判とが出会う場所を探る思考の方法なのである.
いくつかの軍事用,産業用のシミュレーターでは,実際の出力がフィードバックされたり,水圧動作のシミュレーションが行なわれたりしてはいるものの,現在の「民生用」システムでは視覚および聴覚情報入力を合成するのが精一杯である.ところがわれわれが自分の肉体の中に住まい,「この世界に存在する」という感覚は,主にわれわれの体内感覚,すなわち平衡感覚,とりわけ運動感覚ないしは自己受容感覚,それに言うまでもなく温度感や手触り感などと関連する皮膚感覚から成り立っている.完全なVRの「肉体」体験は,こうしたすべての感覚をシミュレーションしなければ得られないはずだが,これは現在の技術の手には余る事柄である.従ってVR技術は肉体をふたつに分割する.視覚および聴覚的シミュレーションは目と耳に対し肉体の表象を与える一方,本物の「肉としての身体」は生身の肉体の中にとどまるのである.
VRはひとつの肉体をふたつの部分的肉体で置き換える.そのふたつとは,物的肉体と(不完全な)電子的「肉体イメージ」である.どちらが上位かということは問題にならない.これは一種の感覚のアパルトヘイトのようなものだ.デカルト主義的二元論からの解放ではなく,その確認である.VRの肉体表象は,この意味で西欧文化の真骨頂である.VRの中に入り込むということは,プラトンの考えるような「イデア」の住まう,純粋な心的抽象物の世界へ入り込むことに等しい.VRに入り込むということはキリスト教的天上世界に足を踏み入れることと同じであり,厄介で混み入った肉体に最終的に別れを告げることに等しい.その結果,肉体に残される唯一のものとは,強力な眼差しの力であり,これが物理的限界を超えた彼方を眺め渡し征服するのである.かくしてルネサンス遠近法の権力的視点は遂に束縛を解かれて自由に行動し始めるのである.
 原註
原註
★1――Virtual Reality as the end of the Enlightenment Project[啓蒙主義プロジェクトの最終形態としてのVR]." in Culture on the Brink, the Ideologies of Technology (Bay Press, 1994); "Virtual Bodybuilding[ヴァーチュアル・ボディービル]," in Media Information Australia, no. 69 (1993 ?); "Consumer Culture and the Technological Imperative[消費者文化とテクノロジーの頼範]," in Critical Issues in Electronic Media, ed. by S. Penny (SUNY Press, 1995). 同種のテーマをめぐってのさらに最近の論文として次のものがある.
"Body Knowledge and Cognitive Diversity[身体知覚と認知的多様性]," in Kunstforum: Special Issue on the Body and Technology, ed. by Florian Rotzer(ドイツ語版,近刊)および "Platonic Machines[プラトン的機械]," in Proceedings of Multimediale, no. 4 (Karlsruhe: Centrum fur Kunst und Medientechnologie)(近刊予定).
★2――Ross Wetzsteon, "The Cosmic Dance[宇宙的舞踊]," Village Voice (Feb. 11, 1992), pp. 95.
★3――次の書物よりの引用.Leonard DeVries, Victorian Inventions (London: John Murray, 1971) , p. 125.[邦訳=『発明狂の時代』(本田成親訳),JICC出版局,1992].
★4――Flann O'Brien, The Third Policeman (Plume, 1976)[初版は1967年.邦訳=『第三の警官』(大沢正佳訳,筑摩書房,1973)].オブライエンはこの本の中で,ハッチジョーなる人物による『ド・セルビーの生涯とその時代』なる本に語られたエピソードを紹介している.
★5――『Illustrated London News[絵入りロンドン・ニュース]』紙より.引用は次の本より.Theodore Roszak, The Cult of Information (New York: Pantheon, 1986), p45.[邦訳=『コンピュータの神話学』(成定薫,荒井克弘訳,朝日新聞社,1989,65頁).
★6――同上書 p. 45[邦訳66頁].
★7――Andre Bazin, "The Myth of Total Cinema," in What Is Cinema, Vol. 1 (Univ. of California Press, 1967), p.22[仏語原文 "Le mythe du cinema total," in Qu'est-ce que le cinema I: Ontologie et langage (Paris: Ed. du Cerf, 1958). 邦訳=「完全映画の神話」,『映画とは何かII 映像言語の問題』(小海永二訳,美術出版社,1972,33頁)所収].
★8――Bertold Brecht, "The Radio as an Apparatus of Communication," reprinted in Video Culture: a Critical Investigation, ed. by John Hanhardt (Visual Studies Workshop/Peregrine Smith, 1987)[独語原文 "Der Rundfunk als Kommunikationsapparat" (1932). 邦訳=「コミュニケーション装置としてのラジオ――ラジオの機能に関する講演」(石黒英男訳),『ベルトルト・ブレヒトの仕事6“ブレヒトの映画・映画論”』(野村修・石黒英男責任編集,河出書房新社,1973)所収].
★9――最近ウィリアム・ボディは,「電子ヴィジョンの前VR考古学とジェンダー化された観客」という講演の中で,初期のラジオをめぐって言われた謳い文句の変容に関する研究を紹介した.William Body, "Proto-VR: archeologies of electronic vision and the gendered spectator," Society for Cinema Studies conference, 1992.
★10――「SIGGRAPH」は,コンピューティング・マシン協会に所属するコンピュータ・グラフィックスおよびインタラクティヴ・テクノロジーに関する特別研究グループが主催する年次会議の名称である.
★11――例えばリチャード・セラのビデオ作品《Tele-vision delivers People[TVは人を届ける]》を参照.この作品はつい最近,ジョン・ハンハードのキュレーションによるホイットニー美術館での「Image World Show」に出品された.
★12――ロン・クィヴィラと著者との個人的対話より.
★13――Guy Debord, Society of the Spectacle, (B&R, 1983), par. 1[仏語原著La Societe du Spectacle (Paris: Ed. Buchet-Chastel, 1967). 邦訳=『スペクタクルの社会』(木下誠訳,平凡社,1993)].
★14――フォイエルバッハ『キリスト教の本質』第2版への序文.引用は『スペクタクルの社会』より.
★15――前掲バザン「完全映画の神話」p. 21[邦訳32頁].
★16――Douglas Adams, The Hitch Hikerr's Guide to the Galaxy[初版はLondon: A Barker, 1979], chap. 7, p. 203.
★17――Tim Druckrey Interviews Jaron Lanier "Revenge of the Nerds[オタクたちの復讐]," in Afterimage , vol. 18, no. 10.
★18――同上.
★19――ウィリアム・ブリッケンの「SIGGRAPH 91」での発言(個人的メモによる).
[本文中の引用文献の翻訳は,すべて訳者による]
 編集部註
編集部註
Copyright Simon PENNY, May 1992 (with amendments 1995). All rights reserved by the author.
(サイモン ペニー・メディアアート/訳=すずき けいすけ・フランス文学)
 GO TOP
GO TOP
| No.14 総目次 |
Internet Edition 総目次 |
| Magazines & Books Page | |