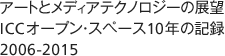畠中│「オープン・スペース」は,メディア・アートについて広く紹介するICCという施設の活動基盤となるような展示という位置づけで,2006年にスタートしました.当初は,過去5年間ぐらいに発表された作品の中から,わかりやすくて長期展示が可能な作品をチョイスしていました.それが2010年以降,メディア・アート自体の再定義や歴史的な位置づけがあらためて行なわれるようになってくると,メディア・アートの周辺動向まで含めた同時代的な潮流を,広いパースペクティヴで捉える企画展と言ってもいいような規模になってきて,現在にいたります.
その中で,最近の傾向として,いわゆるICCがこれまで紹介してきたようなメディア・アートが,他の現代美術館などでも展示されるようになり,現代美術とメディア・アートの違いに,作り手側もあまり意識的ではなくなってきていることが挙げられます.この10年間をかけて「オープン・スペース」では,ひとつには「メディア・アートとは何か?」ということを紹介してきたつもりですが,結果的にメディア・アートという意識がだんだんと希薄になっているのかもしれない.
そうした問題意識を通じて,藤幡さんと久保田さんに,メディア・アートのこれまでの10年とこれからの10年を考えたとき,どのような展望がありえるかを,今日はお話しいただければと思います.
「ザ・メディア・アート」とは?
久保田│去年の春,真鍋大度さんがオーガナイズしたイヴェント「六本木ダークナイト」に呼ばれた際……あれはテクノロジー・アートのカンファレンスという触れ込みでしたが,その冒頭の「日本のメディアアートシーン」というセッションで,「ザ・メディア・アート」という問題提起をしました.つまり「これはメディア・アートだ」とか「これはメディア・アートじゃない」だとかいつまでも言っていてもキリがないから,むしろ「ひとりひとりが〈これぞメディア・アートだ!〉と思っているものって何?」って訊いてみたのだけど,誰も直接そのことに答えてくれなくて残念でした.僕には,それこそ三上晴子さんや藤幡さんのいくつかの作品のような「ザ・メディア・アート」があったわけですが.
*注:その時の僕のスライドが以下にあります.
http://www.slideshare.net/AkihiroKubota/ropponngi-dark-night
畠中│あのとき,登壇者には久保田さんの質問の真意が伝わっていなかったかもしれませんね.たとえば「三上さんや藤幡さんは,メディア・アーティストだ」と言ったとして,登壇者の一部は「メディア・アーティストというより,もっと大きな意味でのアーティストでは?」と思っていた.
久保田│あそこで僕が具体的に訊きたかったのは,作家名じゃなくて作品名のほうでした.たとえば三上さんの《gravicells[グラヴィセルズ]—重力と抵抗》はメディア・アート作品だと言えるけど,彼女自身はメディア・アーティストじゃなくて,単にアーティストと呼ぶのがふさわしい,と僕も思います.
藤幡│それって簡単で「メディア・アートを作るアーティストがいる」ってだけの話じゃない? アートといってもいろいろあるわけで,ヴィデオ作品を作っていた作家が,ある日突然絵を描いたっていい.それが「新しい形式を発見するのがアーティストの仕事で,それを一生維持するのがアーティストだ」と限定されると……それって20世紀のパラダイムですよね.でも実際にはそうじゃない.形式が変わっても,そのアーティストのアイデンティティは継続すると思う.
これは今僕が作っている本(『Anarchive No.6:藤幡正樹』)の大きなテーマにもつながるのだけど,僕もいろいろなメディウムを使ってきたから,観る側の人にとっては「藤幡って何者だかわからない」と言われることもある.それこそ8ミリの作品もあれば,インタラクティヴ作品もあるからね.つまり「形式=作家のアイデンティティ」というのは,極めて20世紀的な美術の枠組みだよね.
だけど,あるアーティストがメディア・アートを始めたら,一生メディア・アートをやり続けるなんて,そんなことはないだろうし,第一そんな目には遭いたくない(笑).
久保田│(笑)僕も東京大学にいたときと今,多摩美術大学でやっていることは,自分としては本質的には何も変わっていないのに,外から見られると「どうして変わったの?」と今でも言われてしまいます.
畠中│たしかに,ある作品のスタイル自体が表現者のアイデンティティであると捉えられてしまいがちですよね.
でも,80年代終盤から90年代初頭頃,それまで絵や彫刻を制作していた作家がコンピュータを使い始めたケースは,当時けっこうありましたよね.それこそ関口敦仁さんとか,中原浩大さんとか.
藤幡│アーティストにとっては極めて自然なことだと思う.でもアーティストにも2つのタイプがあって,ひとつはそういう新しいメディウムに興味があるタイプで,もうひとつは,興味はあるけどやらないタイプ.本来,ほとんどのアーティストは新しいことに興味を持っていると思うけど,そうした新しいメディウムを「うまく使いこなせないな」と思ったときには,あえてやらない.
たとえば「写真に興味を持たなかった画家」っていないでしょ.デジカメが出てくれば,ペインターはほぼ全員買っちゃう.最終的に作るものは絵だとしても,作家はその時代のメディウムの変化にヴィヴィッドに反応する.そのうえで,新しい形式には手を出さない人もいるだろうし,チャレンジする人もいる.
だけど,先ほどの20世紀的な美術のパラダイムの中で言うと,やはりおいそれと形式は変えられない.ある程度古い形式で売ってきた人ならば,当然そうなる.むしろ自分が押さえている古い形式の中に新しいメディウムを取り込むやり方もあるし,そのほうが表現として強いこともある.
久保田│アーティストの営みとして,いろんなメディアに手を出したり,関心を持ったりするのはごく自然のことだけど,ある特定のスタイルがその作家のアイデンティティを固定してしまうと,他のことにトライしても,余技みたいに言われてしまう.絵が本道の人にとって,写真や映像作品は余技だ,とか.
藤幡│それはアートの価値を定義づけるものが,19世紀以前はいわばヴァーチュオーソ(virtuoso)の鑑識眼だったものが,20世紀に入って以降,マーケット・オリエンテッドになったからだよね.芸術作品の価値=お金になってしまった.そうすると,やはりアイデンティティが重要で,だからピカソは決して写真家にはならなかった.写真もたくさん撮っていただろうけれど,作品としては発表していない.マグリットもそう.そこは彼らも馬鹿じゃないからね.
もうひとつには……今の話は作家個人の問題だとして,「新しいメディウムを用いた成果を,作品として発表するか/しないか?」ということ.それを意図的に考えている人と,ほとんど意識していない人がいる.要するにその人のアート活動は意識的なものか,無意識的なものか? それってかなり重要な問題で……だって「アーティストになろう!」と思っても,思うだけではなれないでしょ.以前,科学畑の人から「藤幡君,僕はアートがよくわからないので,教えてくれないか? 教えてくれたら,やるから」と言われたの.でも,アートってそういうものじゃないでしょう.おそらく彼らのパラダイムの中には不連続なものがないのかも.ものごとには理由があって,連続してる.不連続なものがない.でも創造性というのは最終的に不連続なものを孕んでいるじゃないですか.「ある日突然,思いつく」みたいなことだから.
もちろんそれは,科学の場の中にもあると思うけど,論証する必要はない,個人でその不連続を引き受けるだけだからね.それが作ることなんだけど,結果として「新しい世界のドアを開ける」ことになる.ゆくゆくはそれがお金になるかもしれないけれど,そもそもの契機はやはり不連続だと.
そこで「プロフェッショナルなアーティスト」という用語が成立するか/しないかという話になる.20世紀のアーティストの8,9割は,いわば「プロフェッショナルなアーティスト」ですよ.彼らは(アートを)勉強しているから.で,残りの1,2割の中に天才的な人がいる.だけど彼らの多くは,自分のやっていることの意味をよくわかっていない.
社会的価値観という枠組みで見たら,アーティストなんてとても扱いようがない.だけど,そういうものこそが「重要だ」と言ってきたヨーロッパは偉いなと思います.説明するまでもないけれど,結局それって「近代社会」の成立と関わっていて,職業的芸術家=アーティストなんて,本当にこの100年,200年間ぐらいの概念だからね.
新しいメディアとアートの関係
久保田│今の藤幡さんの話はとても本質的で,メディア・アートについて考えるときに一番楽しいのは,やはり「新しいメディアの中にはきっと僕らがまだ見たことのない新しい形式や方法があるはずだ」という仮説を考えているときです.だから形式は規定できない.それを発見したら,n次元かもしれないし,物質でも情報でもないかもしれない.決して主観的や感情的に好き勝手をやっているわけではなくて,その部分に対して自覚的かつ理性的であることが,思考や制作の土台にある気がします.
畠中│そういう意味では最近はアーティストがある特定のメディウムを規定することがさほど重要ではなくなってきている.多様式主義,みたいな言い方もあるし.だから,いろいろなメディウムに隠された未発見の形式を探すポスト・メディウムなアーティストたちは,むしろメディア・アーティストではないか,という言い方もできそうですが.
藤幡│10年前から僕が言い続けてきたのは,「まずメディウム・コンシャスである」ことが始まりだから,「新しいメディアを作ってしまうこと」自体が即ちアートだと言われてもいいだろうと.実際の絵画史を遡ってゆくと,そういう人がいますよね.
ひとつの例が,キャンバスを実際に切り刻んでしまった(ルチオ・)フォンタナ.それによって,キャンバスが麻でできている平面で,そこにイメージが貼りついていることを意識せざるをえなくなる.
ちょうど映画館で,映写機とスクリーンの間に人が立って影が映ると,「じゃまだ,どけ!」と言って怒られるでしょう.そこで「映像がスクリーンに映されている」という事実が露呈してしまうのは,いわばフォンタナ状態です.ある種の彼の作品の中にはそうした要素がある.このように美術史を遡れば,メディウム・コンシャスなアーティストのことをメディア・アーティストと呼んでもいいと,僕も思う.
久保田│ちなみに藤幡さんからすると「ニュー」メディアという言い方はどう思いますか? メディア史の中で,たとえばレフ・マノヴィッチみたいな人がデジタル・メディアのことをニューメディアと言ったわけですが.
藤幡│でもそれは,その時々で常に何か「ニュー」があるわけで…….
久保田│はい,だからこそ21世紀の「ニュー」メディアとは何だろうか,と.もはやコンピュータはニューメディアではなくなったわけですから.
藤幡│たぶんそこでの「ニューメディア」には,発見的なものと発明的なものとの,2つあるんじゃないかな.ひとつは電波を見つけてきて「それがラジオになる」という,純粋に技術的な発明のこと.もうひとつは,過去のメディウムを新しく再構成して,使い方を変えるやり方.よく例に出すのは,ラジオ放送にハガキというメディウムをくっつけることで,ラジオDJが始まった.要するにDJ は,ラジオにハガキというメディアを加えることで,相互通行のメディアになることを発見したわけ.それってすごくメディア・アート的な発想じゃない? そういう意味の発見は,まだまだあると思う.
久保田│ちょうど昨日「Google のD-Wave 2Xという量子アニーリング・コンピュータが,「組み合わせ最適化問題」で既存のコンピュータの1億倍のパフォーマンスを出した」なんてニュースを見たのですが,それだけで無性に使ってみたくなってしまう(笑).
藤幡│初めて写真機が出てきたときに「撮ってみたいなぁ」と思うのと変わらないでしょ.
畠中│ただ,ニューメディアとニューメディア・アートはまた違う.前者は,そのメディアの登場で人間の意識や行動がそれ以前とは大きく変わってしまうような契機になるもの.かたや後者はそうした「新しいメディアを使っているアート」というわけで,そこにはやや違いがある.
藤幡│一般常識としては,メディア・アートも含めて,テクノロジー・アート,ハイテク・アート,デジタル・アート……などと称されているものは全部「新しく出てきた技術が表現のツールとして使えるか?」という問いかけに答えようとしているでしょう.そのときに危険なのは,ほとんどの作品が「新しい技術のデモ」でしかないこと.技術の驚き以上に,その作家にとって必要な表現がそこにあるかというと,99%はない.
久保田│それこそAppleやGoogleは,そうした新技術のデモを肯定的に見せて,どんどん洗脳しようとする.「今度のiPhoneはこんなに革新的になりました」という話題の尻馬に乗せられてそう思い込んでしまう.たいがいは,何ひとつ新しいことはないのだけど.
だから,そうしたマジョリティに対して「ちょっと待てよ」とか,先ほどのラジオDJの例のように,複数のメディアをつなげたり,「こんな使い方もできるよ」という新発見を積極的に見せていく方向が大切になってくる.マクルーハンが言ったように「アート」とは,反環境(Anti-environment)=反技術なのだから.
僕が好きな藤幡さんの《無分別な鏡》は,鏡像が正しく映っちゃいけないわけですよね.そこで起こる何かが,知覚や認識の裂け目やズレを露呈させてくれる.
藤幡│たしかにあの作品は,新技術を見せるつもりじゃないわけです.意図的にフラジャイルに作ってあり,鏡に近づくと追尾できなくなる.
ただ,以前あれをイギリスのマンチェスターで展示したときに(日本人作家の展示だという先入観のせいか)「出来が悪い」と言われた(笑).むしろフラジャイルだという部分に意味があったのだけど,そこは読み取ってもらえず,「技術=完璧」と捉えられてしまう.そうじゃなくて僕は,時として技術は(「相手のことを考えない」という意味で)すごく暴力的でグロテスクなのものだと言いたいのね.武器や兵器にも技術は使われるし,資本家にとっても重要なもの.そういうことから技術を自由にしてあげようと思っているの.
たとえばF1とかがいい例.「F1はアートだ」と言う人がいて,これはけっこう面白いテーゼでしょう.技術の集約だから,工芸的な意味でもね.
畠中│先ほど藤幡さんがおっしゃっていたように「メディア・アートはニュー・テクノロジーのデモではなくて,ある種のメディア批判/テクノロジー批判的な側面を持つべきだ」という考えがあります.一方でテクノロジーというものは,すごく透明性が高くなければ受け入れられなかったりもする.没入感という意味でもウェルメイドなものは,透明性が高ければ高いほどいい.でもそれは,むしろエンターテインメントの領域の話かもしれません.
久保田│ただ実際問題,たとえばノートPCからカリカリ音がしていると「あっ,ハードディスクが動いている」って思うわけで,それがSSDだと作動音がしないので,逆にとても不安に感じます.ビジネスやエンターテインメントの世界が「音をなくしてゆく」ような方向に向かうことが,じつはディストピアかもしれません.
藤幡│《無分別な鏡》の話のついでですが,あの作品のもうひとつの側面は「どうやったら自分をベストに認識してくれるのか」をユーザ自身が探すことで,そこから「ユーザが技術の意味を考えていく」隙間が生まれる.だけど,完璧に動いてしまうと,考えられないのね.
で,コンテンツは何かというと,ストーリー的には何もない.だけど,エンターテインメントの人からは「コンテンツが云々」と言われるし,かたやアート界からは「出来が悪い」と言われちゃう(笑).
メディア・アートとしか呼べないもの
畠中│たとえば90年代のメディア・アートはインタラクティヴという側面が喧伝されていましたが,同時にインタラクション自体の形式化や陳腐化も指摘されていました.そこでの作品の反応は有限なもので,結局インタラクティヴといっても,ある複数のシナリオのとおりに観客が反応させられているにすぎない,といった批判です.
そう考えると,先ほどの藤幡さんの《無分別な鏡》は,そのインタラクションにガイドがなく,ある種のインタラクティヴ批判にもなっている.そうなると,2000年以降は「メディア・アート=インタラクティヴ・アート」の時期をとうに過ぎて,また新たなメディア・アート批判のパラダイムに入る.それが2000年頃から2010年くらいまでだとすると,最近またメディア・アートの様相は変わってきている.
それは,かつてのメディア・アート的な作品,それこそガジェット的なものであったり,よりエンターテインメントに近いような作品が,メディア・アートとして再登場してきたこととも関係があるのではないでしょうか.それが最近のメディア・アートをまたわかりにくくしているような気がします.
久保田│インタラクション批判の話を聞いて僕がいつも思うのは,インタラクティヴであるということは,作品の評価の半分を観客が担当しているということ.つまり藤幡さんの鏡の作品の場合,手を振ってつまらなかったとしても,それは「作品がつまらないのではなくて,あなたがつまらないんだよ」と言わないとダメだと思う.
藤幡│そうですね.インタラクティヴ・アートの重要なところは,まさに観客自身がそれを読み解いてゆくプロセスにあるわけで,従来の絵画のように何か面白い体験を作品から一方的に与えられると思って来た人は落胆するでしょう.それでも20世紀美術は勉強しないとわからないところがあったから,けっこう予習してから来るので,美術館でいざ作品の前に来たときには,今度はそれを確認するだけになってしまう.
久保田│そういう意味で,すでに言語化されたものを解体して,新たな何かを自分で発見しなければならないし,そうさせるだけの力が作品になければならない.
藤幡│おそらく今のメディア・アートの弱いところは,そういう意味での「なんじゃこりゃ?」感が弱いんじゃないかな.今は思ったとおりのものが,そこにあるから.
畠中│しかも,かなりの精度とスペクタクル感でもって観客も満足してしまう.
久保田│冒頭の話に戻りますが,だからこそ「メディア・アート以外とは呼べない作品」とは何か,ということを考えたかったのですね.たとえばPerfumeのステージは,メディア・アートと呼ばずに「テクノロジーを使ったアイドルのパフォーマンスだ」といっても,その価値や意味は変わらない.でも藤幡さんの《無分別な鏡》は,ゲームともエンターテインメントとも言えない.
最近話題になるアーカイヴ問題を逆に適用して,「メディア・アート作品とは既存の方法でアーカイヴできないもの」と定義するといいんじゃないのかな(笑).すでにある形式の作品のアーカイヴの方法はだいたい確立しているから.
畠中│作品そのものがアーカイヴできないので,映像を撮ったり写真を撮ったり,といったドキュメントを残す.でも結局は「作品そのもの」ではありえない.そう考えると,「どうすれば体験そのものをアーカイヴできるか?」という問いに辿り着くような気がします.
久保田│先日,文化庁の仕事でゲーム保存協会の人と会ったのですが,結局彼らがアーカイヴとして辿り着いたのは,ゲームのアーカイヴは「ソフトウェア」のデータとそれを実行できる「エミュレータ」,そしてプレイしているときの「映像」があればいい,ということ.それがあれば「ゲームは保存できる」というわけです.
だけどメディア・アート作品は,それらだけで保存できたとはとうてい言えない.そういう方法や形式には収まらないものこそが,メディア・アートの本質的な部分を照らしているのかもしれません.
藤幡│今の話に補足すると,つまりその時々のテクノロジーが持っているスペックや能力を100%使いきるみたいなことをプログラマーはやるわけだし,そういう作品が結局面白い.だから,後世に残らなくなってしまうこともある.
久保田│そうですね.ゲームは破綻なくちゃんと動いてくれればいいわけで,エミュレータで十分なんですが,メディア・アート作品はそのテクノロジーの一種の裂け目みたいな部分を攻めている.美術とは,そもそもがそういうものではありますが.
藤幡│あと,その「追いつかなさ」が逆に可愛いかったりもする.
久保田│遅さや解像度の低さも含めて作り込んでいきますよね.すると今度は,それを可能にした技術自体の変化をどのように考えていくのか,いわゆるメタ・アーカイヴ論争のことですが.
藤幡│保存するとか,取っておく方法には,「アップデートし続ける」方法と,このまま置いておく方法があるよね.
久保田│それこそ三上さんの《Molecular Informatics》などは,視線入力のハードウェアも,表示デヴァイスも,ソフトウェアもすべてアップデートをし続けたわけですから,彼女が亡くなったあとも,さらにヴァージョン・アップさせていきたい.
藤幡│極端なことを言えば,平安時代の絹で織られた支持材(絹本と言います)の上に描かれた絵を今の時点で修復するとき,その絹が平安時代から現代まで経ったのと同じくらいに傷めるために,保存修復の人たちはわざわざ放射線を当てたりする.だけど平安時代の人は,自分の描いた絵巻物を1200年後の人が見ると思って,描いてはいないよね.
だから本当に重要だと思われたら,今から500年後の未来でも,500年前のiPadを部品から集めてゼロから作っちゃうと思う.そうするとアーティストの役割は「それくらい残るものを作れるかどうか」.「残らない」んじゃなくて「それでも見たい人がいるかどうか」だと.
ちなみに僕は「プログラムで書かれたものは,何百年経っても再現可能だ」という立場ですよ.「OS が変わったら無理だろう」とか言われるけど,全然そんなことはない.
久保田│ソースコードと言語仕様さえ残っていれば再制作可能ですよね.古文や漢文と同じ.
畠中│たとえば最初のICCの構想には「具体的な場所も,モノとしてのコレクションも持たないミュージアム」という考え方がありました.まさに「プログラムさえ残っていれば作品を保存できる」という観点だった.でも,藤幡さんが以前,「ヴィデオ・アートがアートとして認められるようになった理由のひとつは,インスタレーションという展示方法によるものだ」と書かれていたと思いますが,ICCも実際にセンターをオープンしてみたら,「ソースコードだけ」というわけにもいかないわけですが.
藤幡│ZKMのペーター・ヴァイベルが言っていたヴァーチャル・ミュージアムのコンセプトは,アルゴリズムのコレクションだった.つまり,アルゴリズムとそのサポート・システムがあれば再現は可能になるから.ただ,そのサポート・システムは,その時代によって変わってもよいと.
今の話の中のアルゴリズムというのは,言い方を変えると楽譜ですよ.音楽の世界は,17世紀に記譜法が成立したことで,楽曲が楽器から自由になった.だって同じ楽譜があれば何度でも演奏できるわけだし,もともとチェンバロのために書かれた曲をサックスで吹く人が現われたりするけれど,それでもいい.同様に,Macromedia Directorで作った僕の作品のプログラムが将来,何か違うものになることだってあるかもしれない.それでも残るものこそが大事だと.
久保田│作品のコアがソフトウェアだと考えれば,あとはその時々で,テクニカルライダーを参照することで,ディスプレイやデヴァイスを再制作することができる環境が大切なのでしょうね.そういう「環境を残す」ことが,アーカイヴには必要なんだと思います.モーツァルト時代のオーケストラと今のそれは全然違うけれど,どちらで演奏しても「モーツァルトの音楽」というアイデンティティは維持されている.
藤幡│やはりそれはモーツァルトがすごいんだよ.つまりアルゴリズム=譜面だけ見ても,モーツァルトの本質は伝わるから.そういう意味では今メディア・アートに関わっている人たちも2つのタイプがいて,「このブラウン管じゃないと嫌だ」みたいなこだわりがある人と,いわゆるサポート・システムには興味がない人.前者は500年後にソニーのプロフィール・プロを,それこそブラウン管から作っちゃうかもしれない.後者は譜面さえあればいいという人.
畠中│ただ,美術館でのメディア・アート作品のコレクションの現状は,どちらかというとやはり「モノ」主体ですよね.
久保田│たとえばZKMは,もう生産されていないブラウン管型モニターを,ネット・オークションで買えるだけ買い集めることを自分たちの使命だと思っている.
畠中│ZKMのチーフ・キュレーター,ベルンハルト・ゼレクセがICCに来たときに話を聞いたら「作動しなくなったときに置き換えられるような対策を講じているだけで,基本的にはオリジナルを保持すべきだ」という意見でした.
藤幡│以前ピッツバーグで《Beyond Pages》の展示をやったとき,NuBusのヴィデオカードが1枚飛んでしまったら,彼らが「替えはたくさんあるから大丈夫だ」って.だからヴィデオカードもたくさん買っているのね……そのフェティッシュな感覚には好感が持てるけど.
畠中│今,文化庁がメディア芸術作品のアーカイヴを進めていて,今年(2015年)は古橋悌二さんの《LOVERS》の修復作業をやっています.それも「オリジナルを損なわない」ような方針だと思います.
久保田│たとえば,今の明るいプロジェクターだと黒が落ちなくて作品の再現ができない.「プロジェクターは明るければいい」というのが今日のメーカーの常識だとすると,そうではない価値観で再現しようとすること自体が,技術や社会に対する問題提起ですよね.そうした「黒が落ちるようなプロジェクター」はもちろん,作ろうと思えば作れるわけです.
畠中│そうすると,藤幡さん的な「メディアを使う人よりも作る人のほうがアーティストだ」という話に近くなってきますよね.
久保田│結局「メディアそのものに直接コミットしようとしている」作家は,そこで新たな形式も方法も発見できるだろうし,場合によっては自分で作ってしまう.そうしたことに意識的であることが,メディア・アートの最も本質的な部分だと思います.それがあって初めて,作家個人の問題意識や美術館のサポート体制が議論できるようになる.
藤幡│表現を支えているメディアの様式で捉えない,つまり,サポート・システムに依拠しない表現という考え方はラディカルですよね.アルゴリズムに注目する.でも,同時にネット空間にまで言及しているメディア・アートは,空間の形式に疑義を呈しているので,作品に触れるという経験の問題も,同時にとても重要だということになる.この2点は,一見二律背反しているように見えるけれど,異なったメディアを通しても残る創造性とは何か,という問いかけとして読むこともできるんじゃないかな.
社会を変えるような「創造性」
藤幡│ここ10年間の僕の関心事で言うと,2002年に出てきたProcessingと,2005年に開発が始まったArduino,この2つの登場が大きかった.
あと,比較的最近だけど「ラズベリー・パイ(Raspberry Pi)」が出てきたことで,OSやC言語の開発環境がタダ同然になったことも大事だよね.そうした外部デヴァイスが出てくると,今度は「これなら俺でもできる!」ということになる.メディア・アートとの関係では,それらが大きかった.
そもそもメディア・アートって「何かすると何かしてくれる」という関係性が,コンピュータとユーザの間に起こる……「キーボードを叩けば文字が出る」のはあまりにも自明すぎるけど,ごく初期のテレタイプ・ターミナルのときには,[A]というキーを押して画面に[A]という字が表示されるだけで「インタラクティヴだ!」みたいな驚きがあったものね.
そういう「コンピュータと人間との間をどうつなぐか」というテーマが,一般の人たちが見てもわかるレヴェルにまで落ちてきた.そこで初めて,メディア・アートが文化現象化する事態が起こり,昨今のライゾマティクスやチームラボの活躍につながってゆく.
そこでICCとして明確にしておいたほうがいいことをあえて指摘すると,「メディア・アートにおける創造性をどう考えるか?」ということ.つまり「技術開発における創造性」と「アートという意味での創造性」を,ICCは比較的曖昧にしてきた気がする.
たぶん創立初期の90年代の雰囲気がまさにそうだったので(これはICCに限らない話だけど),つまり「メディア・アートが技術を創造的に使うことで,社会にそれが広まり一般化され,ビジネスにつながる」……そういう期待がどこかになかったか.微妙な話だけど,たとえば「より新しい携帯電話の開発にメディア・アートが役立つのでは?」みたいな話だよね.
だけど「技術開発における創造性」と「アートにおける創造性」ははっきり違うということを,この際明言しておいたほうがいいのでは? Processingの言語を作った人も,Arduinoをボードにしてオープンソースで広めようとした人も,2人ともすごく創造的な仕事じゃないですか.
工学系研究者の創造性について忘れられない事件は,Winny開発者のケースですね.あれだけ創造性を持った人が社会的に叩かれてしまうと,次の世代が出てこられない.非常に困った話なんだけど,そういう国なんだよね,日本は.
だからこそ,ICCみたいな場所が,そうした「創造的な技術開発」を社会化するためのひとつの場所になってくれると面白いのだけど……ProcessingはMITメディアラボ開発で,かたやArduinoはイタリア発だよね.どうしてイタリア? 税金が安かった?
久保田│Arduinoボードのお膝元のイヴレーアは,かつてはオリベッティというタイプライターの会社が支えていた街で,その市場が小さくなって溢れてしまった人たちをArduinoで再雇用できた,まさに地域振興事業にもなったそうです.そういう意味でも,Arduinoは文化だけでなく社会の役にも立った典型例にもなった.
藤幡│なぜそういう波に日本がひとつも乗れていないかを考えるべきだし,何かアクションを起こしたほうがいい.
もうひとつのポイント,アートにおける創造性の問題は,モダン(近代)という概念と密接な関係がある.要するに近代社会における個人主義のシンボルとして,アートがある.ひとりの人間の創造性が社会を変える.それぞれの個々人の創造性がないと近代社会は更新されてゆかない……そういう前提の中にあるから,美術や芸術が非常に称揚されている.だけど日本におけるアートはせいぜい「上手に作る」という江戸時代以来の概念のままで,つまりまだ近代社会を迎えていない.
久保田│コンピュータのような新たなメディアがパーソナル化していくプロセスと,そこから起こるさまざまなことこそが面白いわけです.やはり僕は,アヴァンギャルドのスピリットなるものが,アートには常に存在している気がする.
藤幡│アヴァンギャルドと言うとヨーロッパ的な概念なので,ちょっと危ない感じもするけれど……要するに「個人の自由な発想が世の中を変えることがある」ということね.
とくにアメリカ西海岸のベンチャーがまさにそれで,だから新しい技術が入ってきたときに,ボイジャーやAppleを始めた連中は「これで世の中を変えてやろう」という確信を持ったと思う.「コンピュータ・レヴォリューション」という概念が前提にあってスタートしていたから,僕らもそのヴァイブレーションを受けて,当時1台100万円もしたMacintoshを買ったの(笑).そういう中から生まれてきた道具を使っていながら,日本人はまったく,そういう「風」を浴びていない.
だけどそこで,チームラボの猪子寿之君やライゾマティクスの齋藤精一君なんかも,逆に苦労しているんだろうとも思う.「本当にこれでいいのか?」と思っているところもあるんじゃないかな.でも彼らがとりあえず成功しているのは,「何も日本人が作るものを西洋人の基準に合わせなくてもいいじゃないか」って開き直ったからで,村上隆的なポジショニングですよね.
別に僕らだって,連中に合わせようとしているわけじゃない.つまりそういう過去を引きずらなくてもいいじゃないか,とは言いたい.だけどそこがうまく伝わっていなくて……だから若い子たちはすごく混乱していると思う.
20世紀の,とりわけ「60—70年代の経験」から出てきたものは,いわば「自分たちの親のような生活をしなくていいのだ」ということ.いわゆる「意識の解放」がヒッピーイズムの中にはあった.そういう意味でも,自由という言葉の意味について再度考えたほうがいい.
先ほどのProcessingもArduinoもそうだけど,先端技術を大衆に解放する……要するにハイソなものじゃなくて,誰でも手に入れられるものにする.そうすると,技術が自分の手元に降りてきたときに,やはり意識が変わるんです.僕の場合,80年代にCGをやれるような場所に入ったとき,1台3億円もするようなコンピュータを独り占めして使っていました.でもそれが今はもう,1台5ドルの「ラズベリー・パイ」も出るくらいにまで落ちてきている.
そのとき,意識や世界の見え方が変わらないはずがないのだけれど,でも大方は便利さの次元で満足しちゃう.要するに「この技術で製品を安く作って,たくさん売って,儲けよう」みたいな価値観でしか技術が見えない.そのときに,アーティストのひとつの重要な役割は,それがどのように人間の意識を変える可能性を持っているかを,実際に作品を作って見せてあげることだと思う.
[2015年12月10日 ICCにて収録]