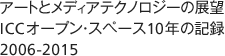はじめに
2006年より開始されたICC オープン・スペース(以下オープン・スペース)は,2015年度をもって10年を迎えた.当初は,毎年展示内容を替えて展開される長期の展示を含んだ,ICCのセンターとしての活動を総称するための名称だったが,2012年度以降は,展示部分を主軸にした「オープン・スペース展」として展開し,現在にいたっている.一貫して,作品展示や関連するイヴェント,アーカイヴなどによって現在のメディア環境を照射し,理解することをねらいとした活動を行なっている.
この10年間には,アーティストをはじめとする参加者の方々の協力によって,多くの作品や活動を紹介することができた.ひとつのテーマを持った活動が10年間継続され,10回の展覧会として展開された,その履歴をながめてみれば,同時代のメディア・アート作品をはじめとする,現代のメディア・テクノロジー環境における多様な表現の変遷を概観することができる.それは,そうした動向の,潮流のひとつを捉えたドキュメントともなっているのではないかと思う.
本稿では,ICCにおけるオープン・スペース以前・以後の状況,そして,オープン・スペースにおける10年間の傾向の変化をまとめてみたい.
オープン・スペースの成り立ちと構成
オープン・スペースは,2005年度をひとつのくぎりとして,2006年に行なわれたICCのリニューアル・オープンに際し構想されたものである.
ICCでは,1997年の開館時から2000年度まで,コレクション作品による常設展示を行なっていたが,2001年度から2005年度までは,常設展示の公開をやめ,企画展を主にした活動を行なっていた.それは,ICC館内の展示すべてが企画展ごとに変わっていくスタイルに変化したということである.そのぶん,企画展の展示領域は拡大し,大規模かつ充実した展覧会の実施が可能になった.しかし,その反面,展示施設としての機能のみがクローズ・アップされてしまったという反省から,ICCのセンターとしての機能を再考,検討することになった.そして,ICCの活動およびメディア・アートをはじめとする科学技術と芸術文化の接点となる表現をより広い観客層に向けて紹介するために,展覧会およびICCの施設を,年度を通じて入場無料で公開する,ICCの活動の基盤となるものとして開設されたのがオープン・スペースである.オープン・スペースは,より「開かれた」施設をめざし,ICC活動の入口として,そのコンセプトを明解に提示することをめざした常設展示の機能を,展覧会ではなく,施設の活動によって拡張しようとした.
オープン・スペースでは,当初4 つのゾーンおよびコーナーで構成された展示を行なっていた(別稿「ICC オープン・スペースの会場構成」参照).現在では,明確なゾーンを示してはいないが,「オープン・スペース展」とそれに含まれる,研究開発コーナー,HIVEの閲覧コーナー,メディア・アート年表といった展示エリアは,継承されている.
館内の常設設備を活用した展示としては,本来,ICCコレクションの三上晴子作品のために館内に作られた無響室がある.当初は無響室の「無響」の状態を体験できるように部屋を開放していたが,2008年度以降は,その特殊な環境を生かした作品展示や,アーティストに作品の制作を依頼し,他の施設では実現できない,ICCのオリジナルな作品展示を行なっている.また,新進作家紹介コーナー「エマージェンシーズ!」のような,アーティスト育成のプログラムも行なっている.
「オープン・スペース展」では,現代のメディア環境における表現としてのテーマが端的に表わされている作品ということを主眼に,ICCが活動してきた97年からの,あるいはそれ以前からのメディア・アートの歴史的なパースペクティヴが捉えられるような構成をめざし,年度ごとの展示替えに際しては,企画時点での特徴的な動向,傾向などを考慮しつつ展示を企画している.
また,これまでに,ある主題にフォーカスした展示構成を行なってもいる.たとえば,2009年度に小企画展として展開された「ミッションG:地球を知覚せよ」や,2010年度の作品同士を作品解説とコラムによって関連づけた「アート&メディア・テクノロジーの考古学」,2011年度のテキストとアーカイヴ映像によるテーマ展示「アート&コミュニケーション・テクノロジーの50年」などがあった.
もうひとつ「オープン・スペース展」の特徴のひとつに,長期間の展示であることが挙げられる.現在,国内外の美術館でもメディア・アート作品の保存修復の方法が議論されているように,メディア・アート作品が美術館での展示あるいは収蔵の機会を持ちにくい要因のひとつには,作品の維持の問題が少なからず関係している.その意味では,長期の展示に耐え得る作品,通常の美術館のファシリティでの展示方法の確立ということの事例ともなっており,その意味はことのほか大きいと思われる.また,それには,作品の可動展示状態を維持するテクニカルスタッフの存在も欠かせない.
ICC開館から,2006年以降,この10年間のメディア・アートの動向
90年代に入って以降の社会的なマルチメディア環境の趨勢は,ICCの成り立ちにも大きく関係している.90年代当時の「メディア・アート」が,行政や企業が主導する形で発展してきたことはその証左となるだろう.それはやがて,同じ時期にICCと同様のメディア・アート・センターとしての活動を開始した,オーストリアのアルス・エレクトロニカ・センターやドイツのZKM(カールスルーエ・アート・アンド・メディア・センター)などの世界の動向とも協調しながら,科学技術やメディア社会との関わりを持った芸術表現分野として認知されるようになった.ICC開館と同じ97年には,ベルリンで開催されていたヴィデオ・フェスティヴァルがトランスメディアーレと名称を変え,また日本国内では「文化庁メディア芸術祭」が開始されてもいる.
そうした時期から10年を経て始まった2006年のオープン・スペースでは,90年代に制作されたメディア・アートの歴史的な作品(クリスタ・ソムラー&ロラン・ミニョノーの作品など)から,テクノロジーを使うことがより一般的になった現在の作品まで,それぞれ異なる時代の作品が並置されることで,サイエンス,インタラクティヴ,デヴァイス,インターネット,ゲーム,といったような要素が,作品の背景にあるテクノロジーの同時代性とその変遷も含めて捉えられるように考えた.
一方,オープン・スペースで展示される作品には,その展覧会の目的ゆえ,ある種の「わかりやすさ」「近づきやすさ」が求められる.作品のテーマや,作品に用いられているテクノロジーとの関係性が明解であることが重視されたり,よりスムーズにインタラクションが誘発されたりする要素を持った作品が多く選ばれている.
2000年代の中頃以降,2010年代に入るくらいまで,ちょうどオープン・スペースの初めの5年間にあたる時期には,現在のメディア・アート的な表現は,インターネットの普及やメディア技術の浸透を背景にして,より一般に認知されるものとなった.
そうした流れの中で,藤幡正樹の作品にも顕著な,技術の本質を捉えていく視点や,新しいテクノロジーをより根源的なところで考えるきっかけを与えるような作品が,メディア・アートとしての意味を持つ.また,ハッキングやベンディングといった手法によって,既存のテクノロジーを改変することで,与えられたものを自身に奪還するような態度が見受けられるようになっている.
また,2010年以降にはSNSの隆盛やスマートフォンなどの携帯情報端末の普及といったことも,作品の変化につながっているし,ゲームなどのエンターテインメントといった領域が「メディア芸術」と称されることとも関係して,メディア・アートという芸術分野が,領域を乗りこえた,より広範囲な表現を守備範囲とした,大きな動向となっているのが特徴だろう.
「メディア芸術」という言葉は,2009年頃より衆目を集めるようになった.そして,メディア・アートをはじめとしてゲームなどのエンターテインメントやマンガ,アニメーションなどが含まれたそのジャンルの規定がメディア・アート周辺の関係者にもたらした一種の混乱が「メディア・アートとは何か」という再確認を促した.さらには頓挫した「メディア芸術総合センター」問題も,メディア・アート再考の契機となったことは記憶に新しい.
オープン・スペースに限らず,ICCがその活動範囲としてきたものも,とくにメディア・アートのような芸術領域のみを扱ってきたわけではない.エンジニアリング,デザイン,あるいは,いわゆる「メディア芸術」の中の,エンターテインメントに分類されるようなウェブ・コンテンツなども含めた,より俯瞰的な視点で捉えている.
2011年以降には,デジタル・ファブリケーションやスペキュラティヴ・デザインなどの近年の特徴的な動向をはじめ,人工衛星を芸術制作のためのメディアとして活用するなどの宇宙芸術,生命科学と芸術表現の関係を探るバイオ・アート,デジタルとフィジカルをつなぐインタラクション・デザインなど,新たな領域を開拓するフロンティアとしての芸術活動にもフォーカスしている.
また近年では,より歴史的なパースペクティヴを持った展示も行なっている.中ザワヒデキ,八谷和彦といったアーティストの90年代の作品の再展示をはじめ,2014年に紹介した,ZKMを主幹にした「デジタル・アートの保存プロジェクト(digital art conservation project)」では,ジェフリー・ショーによるメディア・アート黎明期の作品《レジブル・シティ》(1989-91)の再制作を展示し,メディア・アートの保存のための修復や再制作などの方法論の事例を紹介している.